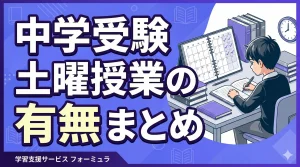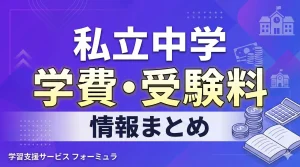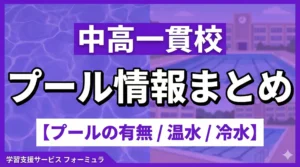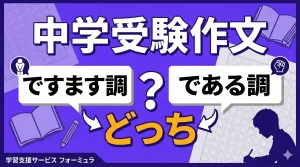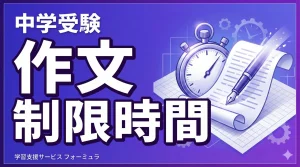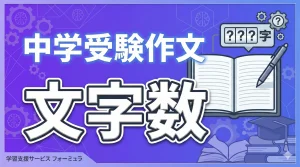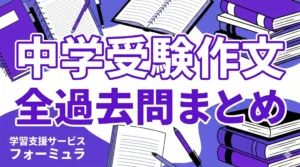この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
【中学受験】親のサポートなしでも大丈夫?共働き家庭必見!合格へ導く親の関わり方

中学受験を控えるお子さんを持つ保護者の皆さま、こんにちは。「学習支援サービス フォーミュラ」の神泉忍です。
お子さんの中学受験に向けて、日々奮闘されていることと思います。
「中学受験は親のサポートが不可欠」「親次第で結果が決まる」といった言葉を聞き、焦りや不安を感じていませんか?
特に共働きで忙しく、「十分なサポートをしてあげられない…」と罪悪感を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そのような悩みを抱える保護者の方に向けて、親のサポートが少ない状況でも中学受験を乗り越えるための考え方や具体的な方法について解説します。
この記事でわかること
- 親のサポートが少なくても中学受験は可能か
- サポート不足で起こりうる課題と対策
- 忙しい親でもできる具体的なサポート方法
親のサポート不足…中学受験への不安を感じていませんか?

中学受験は、お子さんだけでなく保護者にとっても大きな挑戦です。塾の送迎、宿題の管理、説明会への参加、精神的なケア…やるべきことは山積みです。しかし、誰もが十分な時間をかけられるわけではありません。
共働きで時間がない
- 「仕事が忙しくて、子どもの勉強をじっくり見てあげられない」
- 「周りの家庭は手厚くサポートしているのに、うちは…」
そんな風に、ご自身を責めてしまう保護者の方は少なくありません。共働きが当たり前の現代において、仕事と中学受験サポートの両立に悩むのは決してあなただけではないのです。
中学受験は「親次第」と言われるけど…
「中学受験は親次第」という言葉は、保護者にとって大きなプレッシャーとなります。確かに親の関与は重要ですが、具体的に「どこまで」「何を」すれば良いのか、正解はありません。家庭の状況やお子さんの性格によって、最適なサポートの形は異なります。 周囲の声に惑わされず、ご自身の家庭に合った関わり方を見つけることが大切です。
 塾長 神泉
塾長 神泉確かに、親のサポートがあることは理想ですが、サポートが少ない中でも合格されている事例もあります。色々な工夫ができますので、この記事で紹介していきたいと思います。
サポートできない状況での中学受験、諦めるべき?
時間的、あるいは精神的に「これ以上サポートできないかもしれない」と感じたとき、「中学受験自体を諦めるべきか」と悩むこともあるでしょう。しかし、結論を出すのはまだ早いかもしれません。サポートの「量」が少なくても、「質」を高める工夫や、子どもの自律性を促す関わり方によって、道が開ける可能性は十分にあります。 諦める前に、できることや考え方を変えてみることから始めてみましょう。
親のサポートが少ない場合に起こりうる「問題」5選


親のサポートが少ない場合、中学受験においていくつかの課題が生じやすくなる可能性があります。大きく5つに分けて解説します。
①学習習慣が身につかない可能性
特に低学年のうちは、自分から机に向かう習慣を身につけるのが難しい場合があります。親の声かけや一緒に勉強する時間がないと、学習が後回しになりがちです。日々の学習リズムを作るためには、最初のうちはある程度の関与が必要になるかもしれません。
②宿題や課題の管理が難しい
中学受験塾の宿題は量が多く、難易度も高いものがあります。どの科目をいつまでにやるのか、どの教材を使うのかなど、子どもだけで全てを管理するのは大変です。計画を立てる手伝いや、進捗を確認するサポートがないと、宿題が終わらなかったり、提出物を忘れたりすることが増える可能性があります。
③モチベーション維持の難しさ
受験勉強は長く、時には思うように成績が伸びないこともあります。そんな時、親からの励ましや、目標達成に向けた声かけがないと、子どものやる気が低下してしまうことがあります。特に精神的に不安定になりやすい時期には、親の精神的な支えが大きな力となります。
④情報収集の遅れや偏り
志望校の情報、入試説明会の日程、塾の特別講座など、中学受験には親が積極的に収集すべき情報が多くあります。忙しさから情報収集が後手に回ると、重要な機会を逃したり、情報が偏ったりする可能性があります。効率的な情報収集の方法を確立することが求められます。
⑤親子関係への影響
受験のプレッシャーや、「もっとサポートしてあげたいのにできない」という親のストレス、子どもの反発などが重なると、親子関係がギクシャクしてしまうこともあります。サポート不足が直接の原因でなくても、受験期特有のストレスが関係悪化の引き金になる可能性は否定できません。
親のサポートが少ない状況で中学受験を乗り越えるポイント


ここまでサポート不足による課題を見てきましたが、決して悲観する必要はありません。考え方や工夫次第で、サポートが少ない状況でも中学受験を乗り越え、成功を掴むことは十分に可能です。
重要なのは「量より質」
毎日長時間勉強を見ることはできなくても、短い時間で質の高い関わりを持つことは可能です。 量ではなく、関わる時間の「質」を意識しましょう。



例えば、寝る前の10分間、今日の出来事や頑張ったことをじっくり聞いてあげるだけでも、子どもの安心感や自己肯定感に繋がります。
子どもの自律性を育てる
親が何でもやってあげるのではなく、子ども自身に考えさせ、行動させる機会を作ることも大切です。「自分でできた」という経験は、子どもの自信と自律性を育みます。親は指示するのではなく、子どもが自分で考えて動けるように、そっと背中を押す存在を目指しましょう。
「合格だけがゴールではない」という視点を持つ
中学受験は、合格が全てではありません。目標に向かって努力する過程で、子どもは多くのことを学び、大きく成長します。たとえ思うような結果にならなかったとしても、その経験は必ず将来の糧となります。 結果だけに囚われず、子どもの成長を見守る視点を持つことで、親のプレッシャーも軽くなるはずです。
親が「最低限」やるべきサポート4選


忙しい中でも、これだけは押さえておきたいという最低限のサポートがあります。全てを完璧にこなそうとするのではなく、ポイントを絞って効果的に関わっていきましょう。
親が「最低限」やるべきサポートまとめ
- ①子どもが安心できる「心の安全基地」になる
- ②集中できる学習環境を整える
- ③基本的な生活リズムの管理サポート
- ④塾や学校とのコミュニケーションを大切に
①子どもが安心できる「心の安全基地」になる
勉強の出来不出来に関わらず、「いつでもあなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けることが、何よりも大切です。 子どもが安心して挑戦できるのは、帰る場所があるからです。家庭を、子どもにとって心の安全基地にしてあげましょう。
②集中できる学習環境を整える
勉強に集中できる環境を整えることは、親ができる重要なサポートの一つです。静かな学習スペースを確保し、整理整頓を心がけ、必要な文房具が揃っているかなどを確認しましょう。 環境が整っているだけでも、子どもの学習意欲は変わってきます。
③基本的な生活リズムの管理サポート
質の高い学習のためには、健康的な生活が不可欠です。
- 十分な睡眠時間の確保
- 栄養バランスの取れた食事
- 規則正しい生活リズム
などを意識し、子どもが万全の状態で勉強に取り組めるようサポートしましょう。 特に睡眠不足は集中力低下の大きな原因になります。
④塾や学校とのコミュニケーションを大切に
子どもの学習状況や様子を正確に把握するために、塾や学校の先生との連携は欠かせません。忙しい中でも、定期的な面談にはできるだけ参加し、連絡帳や電話なども活用して、先生方と情報を共有するように努めましょう。 家庭と塾・学校が連携することで、より効果的なサポートが可能になります。
子どもの「自分でやる力」を引き出す関わり方


親が一方的にサポートするのではなく、子どもの「自分でやる力」、つまり自律性を引き出すような関わり方を意識することが、サポートが少ない状況では特に重要になります。
「伴走し、見守る」意識で接する
分からない問題をすぐに親が教えるのではなく、まずは子ども自身に考えさせることが大切です。ヒントを与えたり、考え方を整理する手伝いをしたりしながら、子どもが自分で答えにたどり着けるよう「伴走」するイメージで関わりましょう。 時には、じっと見守ることも必要です。
小さな成功体験を作ってあげる
- 「難しい問題が解けた」
- 「計画通りに宿題が終わった」
- 「苦手な単元を克服できた」
など、どんなに小さなことでも、子どもが達成したことを見つけて具体的に褒めましょう。「できた!」という成功体験の積み重ねが、子どもの自信と「次も頑張ろう」という意欲に繋がります。
忙しくても「聞く時間」を意識的に作る
毎日長時間向き合うのが難しくても、「話を聞く時間」は意識的に作りましょう。勉強のことだけでなく、学校での出来事、友達とのこと、好きなことなど、子どもの話に共感しながら耳を傾けることが、親子の信頼関係を深めます。 この時間が、子どもの心の支えになります。



子供に限らず、人間は、話を聞いてもらうことで、大きな安心感を得られます。
忙しい保護者でもできる!学習の進め方のコツ


限られた時間の中で、子どもの学習を効果的にサポートするための具体的な工夫を5つご紹介します。取り入れやすいものから試してみてください。
すべて完璧にやろうとしない
中学受験塾の勉強量は膨大です。すべてを完璧にこなそうとすると、親子ともに疲弊してしまいます。 苦手な分野や重要な単元に絞る、基礎的な問題は確実に解くなど、優先順位をつけることも大切です。必要であれば、塾の先生に相談して量を調整してもらうのも一つの方法です。



塾の課題が難しすぎる場合の対処法についてこちらの動画で詳しく解説しています。
スケジュール管理は子ども主体で
親が一方的にスケジュールを決めるのではなく、まずは子ども自身に計画を立てさせてみましょう。親はアドバイザーとして、無理のない計画になっているか、優先順位は適切かなどを一緒に確認し、必要に応じて修正を手伝う、というスタンスが理想的です。 自分で立てた計画なら、責任感も生まれやすくなります。
スマホやアプリなどデジタルツールを賢く活用
学習管理アプリ、オンラインの解説動画、タイマーアプリなど、スマートフォンのアプリやWebサービスを上手に活用すれば、学習の効率化やモチベーション維持に役立ちます。 ただし、使いすぎには注意し、ルールを決めて利用することが大切です。
長時間学習を目的化しない
長時間だらだらと勉強するよりも、短時間で集中して取り組む方が効果的な場合があります。キッチンタイマーなどを使って勉強時間を区切り、「この時間は集中する」という意識を持たせるのがおすすめです。 休憩時間もしっかり確保し、メリハリをつけましょう。



スキマ時間を活用し、学習効率を上げる方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。
「分からない」を放置させない
分からない問題をそのままにしておくと、学習の遅れに繋がります。親に質問しづらい場合は、塾の先生に積極的に質問するよう促しましょう。家庭でも、「分からないことがあったらいつでも聞いてね」と伝え、子どもが気軽に質問できる雰囲気を作っておくことが大切です。
親自身のメンタルケアも大切


お子さんのサポートに一生懸命になるあまり、保護者自身が心身ともに疲れてしまっては元も子もありません。親が笑顔でいることが、子どもの安心感にも繋がります。
完璧な親を目指さない
「あれもこれもしてあげなければ」と自分を追い詰めていませんか?完璧な親である必要はありません。「できる範囲で精一杯やっている」と、頑張っている自分自身を認め、許してあげましょう。 時には手を抜くことも大切です。
他の家庭やSNSの情報と比較しすぎない
周りの家庭がどれだけ手厚くサポートしているか、SNSでキラキラした情報を見ると、つい自分の家庭と比較して落ち込んでしまうかもしれません。しかし、家庭の状況はそれぞれ違います。「よそはよそ、うちはうち」と割り切り、比較しすぎないようにしましょう。
頼れる人やサービスを上手に活用する
一人で抱え込まず、頼れる存在には積極的に頼りましょう。パートナー、祖父母、友人、ママ友・パパ友、あるいはベビーシッターや家事代行サービス、塾の個別サポートなど、利用できるものは上手に活用するのも賢い方法です。
親子で中学受験を乗り越えるためのおすすめ指南書
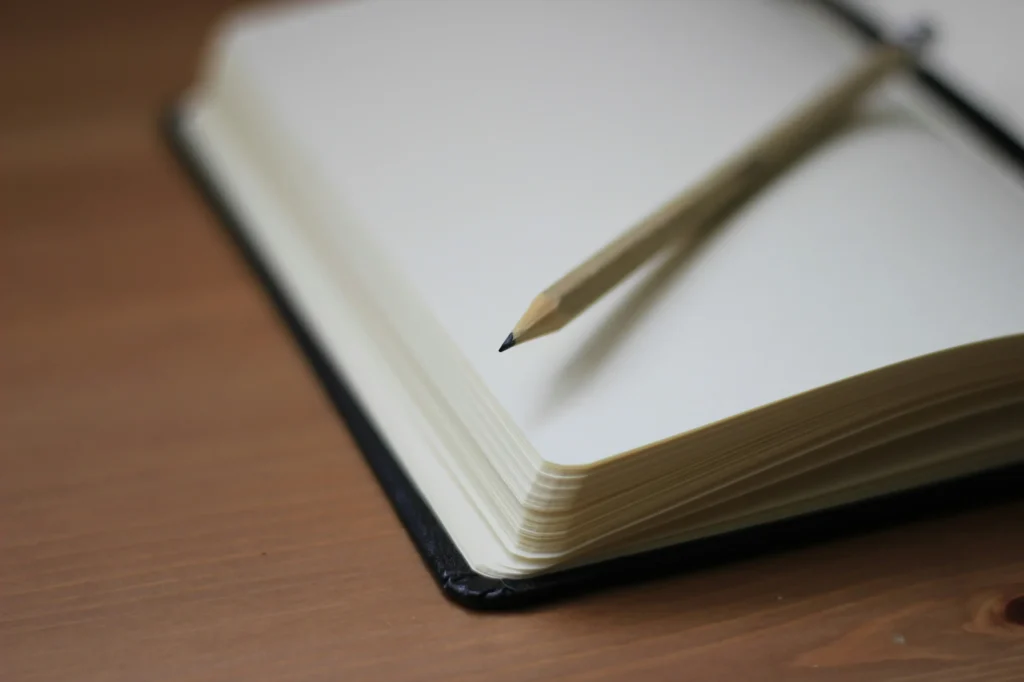
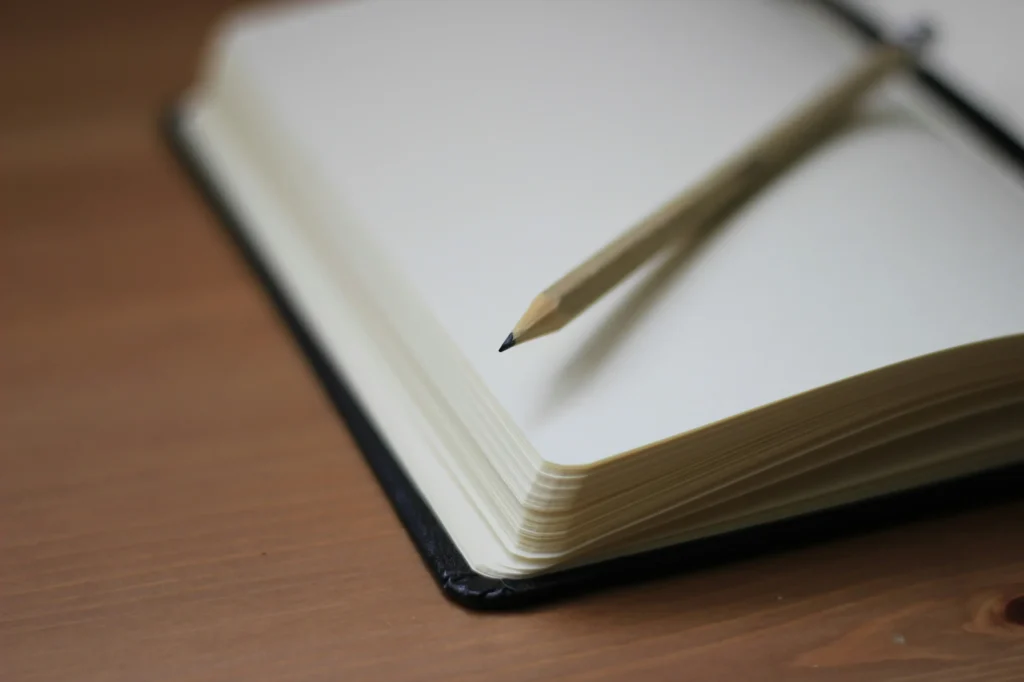
中学受験を初めて経験するご家庭にとって、大切なのは、先人の知恵です。親子で中学受験を乗り越えるために読んでおくべき指南書を、厳選してご紹介します。
親子で中学受験を乗り越えるために読んでおくべき指南書まとめ
- Amazonレビューの声
- 塾や学校が実名で生々しく書いてあるので、リアリティがあり、多くの教訓を得た。
- 親の心がまえと、塾の本音、子どもはまだ子どもだということ、家族のあり方を教えてくれる本
- 本当に首都圏関西圏で良く良くある事例なのだと肌で感じます。
- Amazonレビューの声
- フェイク学力、バブル偏差値、とても興味深い内容でした。
- 中学受験に何を求めているのか、この経験を通して子供に何を伝えたいのか、自分たちが1番大切にしたい核は何なのか、夫婦でシェアしたいと思いました。



受験指南本について100冊以上もっている私が厳選した2冊がこちらです。
まとめ


親のサポートが少ない状況での中学受験は、確かに大変な面もあります。しかし、工夫次第でより大きな成果を出すことは可能ですし、その経験は親子にとってかけがえのない財産となるはずです。
中学受験は親子が共に成長する貴重な機会
受験勉強を通して、
- 困難に立ち向かう力
- 計画性
- 忍耐力
- 論理的思考力
などを身につけます。親もまた、子どもへの関わり方を見つめ直し、子どもの成長を実感する中で、親として成長することができます。 結果だけでなく、そのプロセス自体が貴重な経験です。
お子さんの力を信じて伴走しましょう
周りと比較して焦ったり、不安になったりすることもあるかもしれません。しかし、一番大切なのは、お子さんの力を信じ、その子に合ったペースでサポートしていくことです。 親がどっしりと構え、温かく見守る姿勢が、子どもの安心感と頑張る力に繋がります。
親のサポートが少なくても、子どもは中学受験を乗り越えられますか?
はい、可能です。大切なのはサポートの「量」よりも「質」です。限られた時間でも、お子さんの話をじっくり聞いたり、頑張りを具体的に認めたりする質の高い関わりを意識しましょう。子どもの力を信じ、塾など外部のサポートも上手に活用することで、乗り越えることは十分に可能です。
共働きなどで忙しい親が、最低限やるべきサポートは何でしょうか?
まずはお子さんが安心できる「心の安全基地」となることです。精神的な支えは何より大切です。その上で、①集中できる学習環境の整備、②十分な睡眠やバランスの取れた食事といった基本的な生活リズムの管理、③塾や学校の先生とのコミュニケーション、の3点を意識すると良いでしょう。
子どもが自分から勉強する「自律性」を育むには、どう関われば良いですか?
親がすぐに答えを教えるのではなく、ヒントを与えたり考え方を整理したりして、お子さん自身が答えにたどり着けるよう「伴走」する姿勢が大切です。小さな「できた!」という成功体験を積み重ねられるよう、具体的に褒めて自信を育みましょう。お子さんの話をしっかり聞く時間を作ることも重要です。
親のサポートが少ない場合、中学受験でどのような問題が起こりやすいですか?
自分から勉強する習慣がつきにくい、塾の宿題や課題の管理が難しい、勉強へのモチベーションを維持しにくい、といった学習面での課題が考えられます。また、親が必要な情報を十分に集められなかったり、受験期のストレスから親子関係に影響が出たりする可能性もあります。
受験期は親も大変ですが、親自身のメンタルケアはどうすれば良いですか?
「完璧な親」を目指さず、できる範囲でサポートすれば良い、と自分を認めましょう。他の家庭と比較しすぎず、「うちはうち」と割り切ることも大切です。一人で抱え込まず、パートナーや祖父母、外部サービスなども頼り、意識的に休息やリフレッシュの時間を作りましょう。