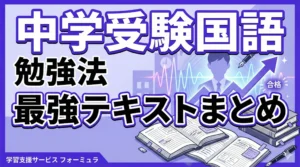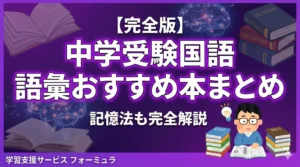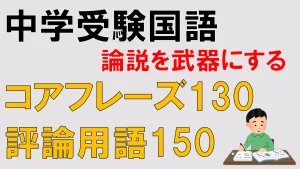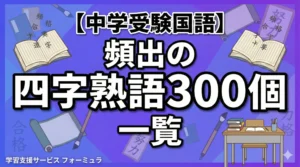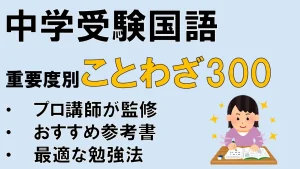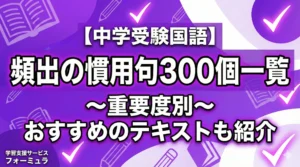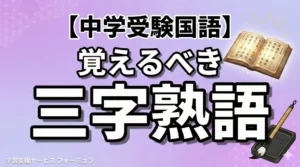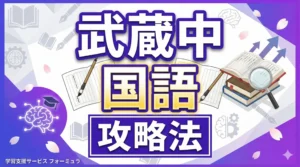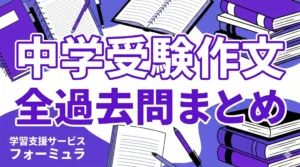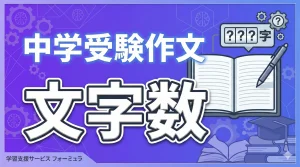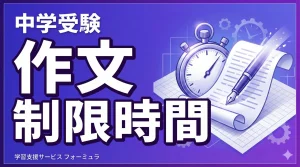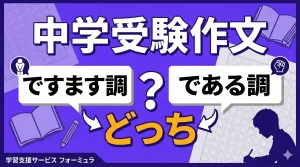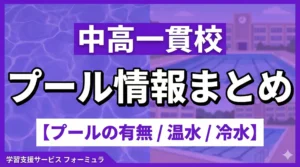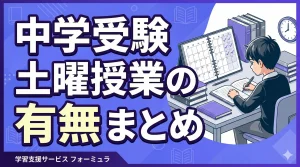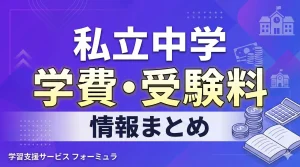この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
中学受験の国語、問題と設問どちらを先に読むべきか迷っていませんか?中学受験プロ講師の神泉忍が、それぞれのメリット・デメリット、文章タイプ別の読み方、お子さんに合った方法の見つけ方を分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 本文先読み・設問先読みのメリットとデメリット
- 物語文・説明文での効果的な読み方の違い
- お子さんに合った読み方の見つけ方とサポート方法
中学受験の国語、問題と設問どっちから読む?

多くの保護者が悩む「読む順番」
中学受験の国語の試験では、限られた時間の中で長い文章を読み、多くの設問に答えなければなりません。
- 「問題文(本文)を先にじっくり読むべきか」
- 「いや、設問(問い)から読んで効率よく進めるべきか」
というのは、多くの保護者の方やお子さん自身が一度は悩むポイントではないでしょうか。時間配分を間違えると解ききれなくなってしまいますし、読み方によっては正答率にも影響が出かねません。だからこそ、この「読む順番」は、国語の得点力を左右する重要な要素の一つといえるのです。
結論「絶対の正解はない」
まず最初にお伝えしたいのは、「問題文と設問、どちらを先に読むのが絶対に正しい」という唯一の答えはないということです。 お子さんの読むスピードや集中力、文章の得意不得意、そして問題そのものの性質によって、最適なアプローチは変わってきます。周りの意見や一般的な方法に惑わされず、お子さんに合ったやり方を見つけることが大切です。この記事では、そのための判断材料となる情報を提供していきますので、ぜひ参考にしてください。
お子さんに合う方法を見つけるのが大切
絶対的な正解がないからこそ、重要になるのが「お子さんに合った方法を見つける」という視点です。読むスピードが比較的速く、文章全体の流れを掴むのが得意なお子さんもいれば、先にポイントを絞ってから読む方が集中できるお子さんもいます。大切なのは、お子さん一人ひとりの個性や学習スタイルを理解し、最も力を発揮できる読み方を見つけ出すことです。
 塾長 神泉
塾長 神泉そのプロセス自体が、国語力向上にもつながっていくはずです。
「本文(問題文)から読む」メリット・デメリット
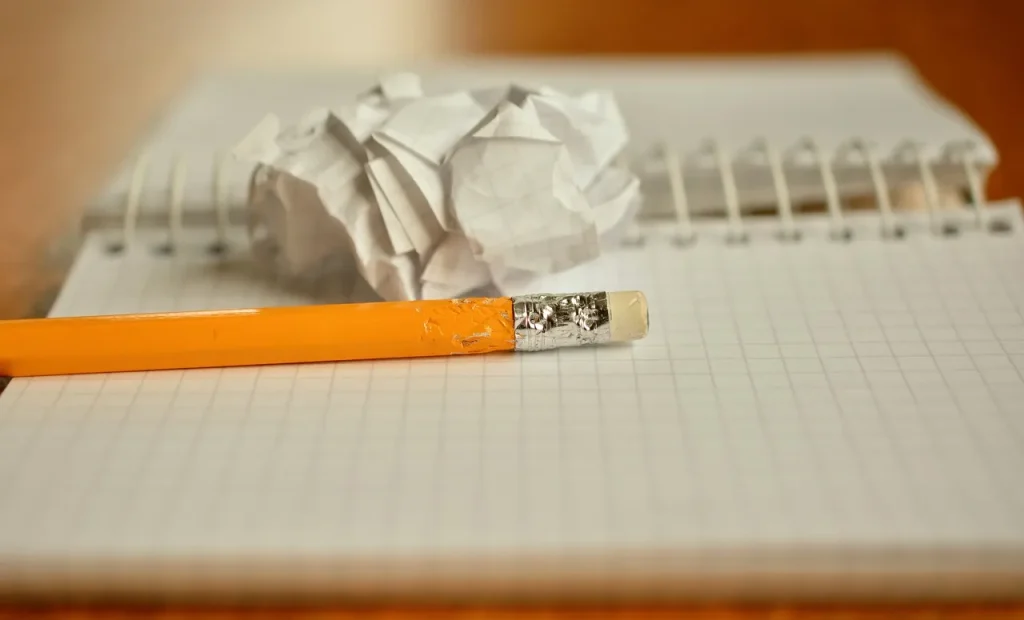
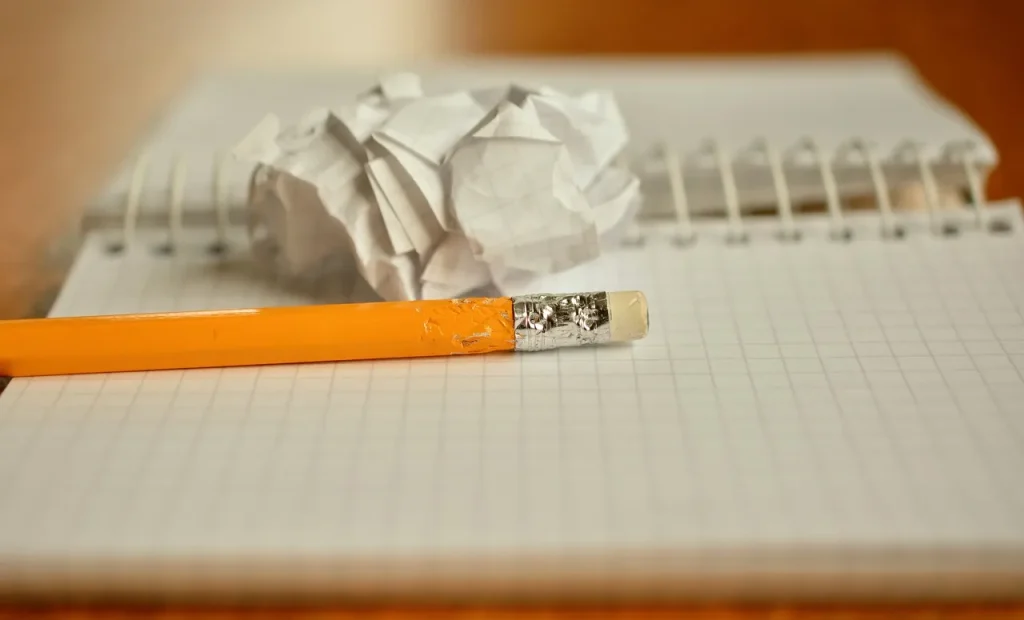
本文(問題文)先読みのまとめ
- メリット: 話の流れを掴める、全体像を理解できる
- デメリット: 時間がかかる可能性、設問ポイントの見逃し
- 注意点: 時間配分を意識する練習が必要
メリット①話の流れをしっかり掴める
本文を先に読むことの最大のメリットは、物語の展開や説明文の論理構成など、文章全体の流れや文脈をしっかりと把握できる点にあります。 特に登場人物の心情の変化や話の筋が重要な物語文においては、全体を読んで初めて理解できるニュアンスも多くあります。全体像を掴むことで、設問に対する深い理解につながりやすくなるでしょう。この方法は、文脈を重視するお子さんには安心感を与えるかもしれません。
メリット②全体像を理解してから設問へ
文章全体の構成やテーマを理解した上で設問に取り組むため、部分的な情報だけに注目して解答を導き出すといったミスを防ぎやすくなります。文脈を踏まえた上で解答を考えることで、特に「筆者の考えを説明しなさい」といった記述問題などで、より的確な解答を作成できる可能性が高まります。 表面的な理解にとどまらず、文章の本質に迫る読み方ができるのが、この方法の強みといえるでしょう。
デメリット①時間がかかり焦ることも
一方で、本文全体を丁寧に読むには、相応の時間がかかります。特に中学受験の国語は長文が出題されることも多く、制限時間が厳しい場合には、本文を読むだけで時間を使いすぎてしまい、設問を解く時間が足りなくなってしまう可能性があります。もし途中で内容が分からなくなり読み返す必要が出てくると、さらに時間をロスしてしまい、焦りの原因にもなりかねません。 時間配分には十分な注意が必要です。
デメリット②設問のポイントを見逃す可能性
本文を読んでいる段階では、具体的にどのような点が設問で問われるのかは分かりません。そのため、後で設問を読んだときに「どこに書いてあったっけ?」と、本文中から解答の根拠となる箇所を探し直す手間が発生する可能性があります。 重要な部分を意識せずに読み進めてしまうと、結果的に二度手間になってしまうこともあるのが、この方法のデメリットといえるでしょう。
「本文先読み」が向いているお子さんの特徴
「本文先読み」は、以下のような特徴を持つお子さんに比較的向いている方法と考えられます。
- 読むスピードが平均かそれ以上のお子さん
- 文章全体の流れや雰囲気を掴むことを重視するお子さん
- 物語文を読むのが比較的得意なお子さん
- 細部よりもまず全体像を把握したいタイプのお子さん
もちろん、これらはあくまで一般的な傾向であり、最終的にはお子さん自身が試してみて、しっくりくるかどうかで判断することが大切です。
先に「設問(問い)から読む」メリット・デメリット


設問先読みのまとめ
- メリット: 読むべき点が明確、時間短縮、設問意図を意識
- デメリット: 全体の流れを見失う可能性
- 注意点: 部分読みで終わらない工夫が必要
メリット①読むべきポイントが明確に
設問に先に目を通すことの最大のメリットは、本文を読む前に「何を探せばよいのか」「どこに注目すべきか」が明確になる点です。 まるで宝探しの地図を手に入れるように、解答に必要な情報を意識しながら本文を読み進めることができます。これにより、漠然と読むよりも効率的に、かつ目的意識を持って文章と向き合うことが可能になります。重要な情報を見逃しにくくなる効果も期待できるでしょう。
メリット②時間短縮につながりやすい
設問に関連する箇所を重点的に読むため、本文全体を隅から隅まで読む必要がなくなり、結果的に解答時間を短縮できる可能性が高まります。特に時間との戦いになることが多い入試本番においては、この「設問先読み」は有効な時間戦略となりえます。 限られた時間の中で、より多くの問題に確実に解答するための一つの手段として、試してみる価値はあるでしょう。
メリット③設問の意図を意識して読み進められる
先に設問を読むことで、「この文章で問われているのはこういうことだな」と、出題者の意図をある程度推測しながら本文を読むことができます。これにより、解答の方向性を見定めやすくなり、的外れな解答をしてしまうリスクを減らす効果が期待できます。 設問の要求に的確に応える解答を作成するためには、設問の意図を正確に読み取る力が不可欠であり、設問先読みはその助けとなります。
デメリット①本文全体の流れを見失いがち
設問に関連する部分的な情報に集中するあまり、文章全体の流れやテーマ、登場人物の心情の移り変わりといった、文脈全体を捉える視点が疎かになってしまう危険性があります。特に物語文のように、話全体の流れや登場人物の関係性を理解することが重要な文章では、部分的な読み方だけでは解答を誤ってしまう可能性があります。 木を見て森を見ず、の状態にならないよう注意が必要です。
「設問先読み」が向いているお子さんの特徴
「設問先読み」は、以下のような特徴を持つお子さんに比較的向いている方法と考えられます。
- 要点を素早く掴むのが得意なお子さん
- 限られた時間の中で効率よく問題を解きたいお子さん
- 説明文や論説文を読むのが比較的得意なお子さん
- 先にゴール(設問)を知ってから取り組みたいタイプのお子さん
こちらも本文先読みと同様、一般的な傾向にすぎません。お子さんの学習スタイルに合わせて検討することが重要です。
物語文の読み方
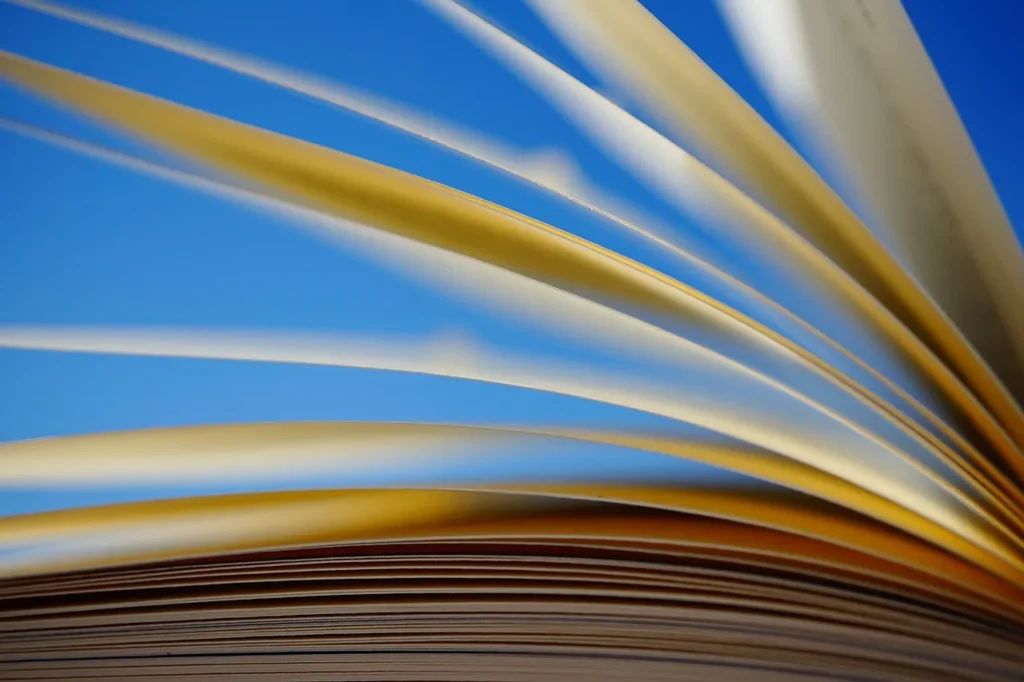
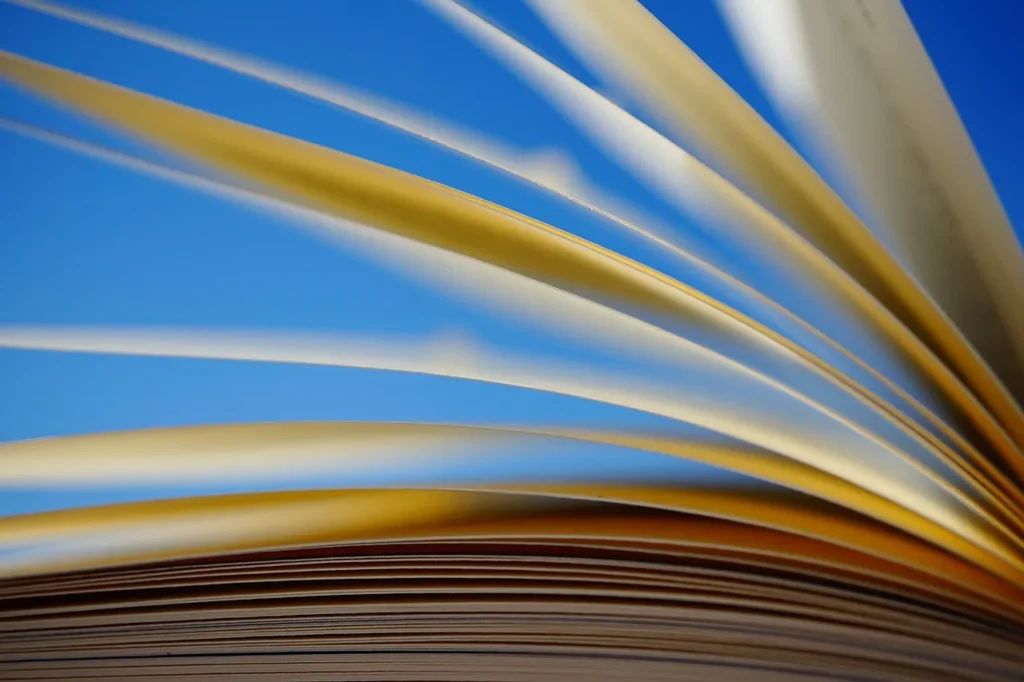
登場人物の心情理解が重要
物語文の問題では、登場人物が「なぜそう言ったのか」「その時どう感じていたのか」といった心情や、登場人物同士の関係性の変化を問われることが多くあります。これらの要素は、物語全体の流れや出来事の積み重ねの中で変化していくため、正確に読み取るには文脈理解が不可欠です。 また、何気ない描写が後の展開の伏線になっていることもあるため、場面の移り変わりにも注意深く目を向ける必要があります。
物語文は「本文先読み」が基本?
物語文の特性を考えると、基本的には「本文先読み」で、まず物語全体の流れや登場人物の関係性、雰囲気などを掴んでから設問に取り組む方が、深い理解に基づいた解答を導きやすいといえるでしょう。 先に設問を読むと、部分的な情報に引っ張られてしまい、登場人物の微妙な心情の変化や物語の結末を誤って解釈してしまうリスクがあります。焦らず、じっくりと物語の世界に入り込むことが大切です。
説明文・論説文の読み方


筆者の主張・要点を捉える
説明文や論説文では、「筆者はこの文章を通して何を伝えたいのか(主題・主張)」や「その主張を支える根拠は何か」「文章はどのような論理で構成されているか」を正確に把握することが求められます。そのためには、接続詞(しかし、だから、など)の働きに注意し、段落ごとの要旨や段落間の関係性を意識しながら読み進めることが重要になります。 キーワードを見つけることもポイントです。



論説・説明の必須となる接続語を一覧化した記事は【中学受験国語】説明文&論説文が得意になる用語150語になります。
説明文は「設問先読み」も有効な場合が多い
説明文や論説文の設問は、「傍線部の理由を説明しなさい」「指示語が指す内容を答えなさい」「筆者の主張と合致するものを選びなさい」など、特定の箇所やキーワード、文章の論理構造について問うものが多く見られます。そのため、「設問先読み」によって問われているポイントを把握し、本文中の該当箇所を探しながら読む方法が効率的な場合が多いといえます。 時間短縮の観点からも有効な戦略です。
保護者ができる!読み方定着のためのサポート


一緒に試して最適な方法を探る時間を作る
頭で考えるだけでなく、実際にお子さんと一緒に過去問や問題集を使って、両方の読み方を試してみる時間を作ることをお勧めします。「本文先読み」「設問先読み」の2パターンで解いてみて、どちらが解きやすかったか、時間はどれくらいかかったか、点数に違いはあったかなどを具体的に比較してみましょう。 客観的なデータと本人の感覚を合わせて判断することで、納得感のある方法が見つかりやすくなります。
時間を計って解く練習で時間感覚を養う
中学受験本番は時間との勝負です。普段の学習から、ストップウォッチなどを使って時間を計りながら問題を解く練習を取り入れましょう。これにより、お子さん自身が「この読み方だと大体これくらいの時間がかかるな」という時間感覚を掴むことができます。 また、時間制限がある中で、どちらの読み方がより自分のペースに合っているか、時間内に解き終えるためにどのような工夫が必要かを考える良い機会にもなります。



時間管理の大切さを説明した記事は【中学受験】おすすめの腕時計と日々の学習時間管理方法になります。
解き終わった後の振り返りを大切に
問題を解き終わったら、答え合わせをして点数を確認するだけでなく、
- 「なぜその順番で読んだのか」
- 「その読み方をして良かった点、やりにくかった点はどこか」
- 「次はどうすればもっと上手くできそうか」
といった点を、ぜひお子さんと一緒に話し合ってみてください。自分の解き方を客観的に振り返ることで、改善点が見つかり、より効果的な方法へと洗練させていくことができます。 この「振り返り」こそが、成長の鍵となります。
無理強いせず、お子さんの意見や感覚を尊重する
保護者の方が「こちらの読み方の方が効率的だ」と考えたとしても、それを一方的に押し付けるのは避けましょう。最終的に試験本番で問題を解くのはお子さん自身ですから、本人が「この方法が一番やりやすい」と納得していることが何よりも大切です。 いくつかの方法を試した上で、お子さんの意見や感覚を尊重し、「自分で選んだ」という主体性を大切にしてあげてください。その上で、試行錯誤を温かく見守り、応援する姿勢が重要です。
まとめ


この記事を通して繰り返しお伝えしてきたように、中学受験の国語において、「本文先読み」と「設問先読み」のどちらが絶対的に正しいということはありません。大切なのは、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、固定観念にとらわれずに柔軟に考えることです。 一般的な方法や周りの意見に流されるのではなく、お子さん自身の特性を見極める視点を持つことが重要です。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
有名中学校国語過去問に関する記事一覧
公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧
中高一貫校のデータに関する記事一覧
中学受験の国語、問題文と設問、どちらを先に読むのが正解ですか?
絶対的な正解はありません。お子さんの読むスピード、得意な文章タイプ、問題の性質によって最適な方法は異なります。一般的な方法に惑わされず、お子さんに合った方法を見つけることが最も大切です。この記事ではその判断材料を提供しています。
問題文(本文)を先に読むメリットとデメリットは何ですか?
メリットは、文章全体の流れや文脈を把握しやすく、深い理解につながることです。特に物語文に向いています。デメリットは、時間がかかる可能性があり、設問で問われる重要なポイントを見逃しやすい点です。時間配分には注意が必要です。
設問(問い)を先に読むメリットとデメリットは何ですか?
メリットは、読むべきポイントが明確になり、時間短縮につながりやすい点です。設問の意図を意識して効率的に読めます。特に説明文・論説文に向いています。デメリットは、文章全体の流れを見失いやすく、部分的な理解にとどまる可能性があることです。
物語文と説明文・論説文では、読み方を変えた方が良いですか?
はい、変えるのが効果的な場合があります。物語文は登場人物の心情や話の流れが重要なので、本文全体を先に読むのが基本とされています。一方、説明文・論説文は要点や論理構成が問われるため、設問を先に読んでポイントを絞る方法も有効です。
Q5.子どもに合った読み方を見つけるために、親は何ができますか?
まず、お子さんと一緒に両方の読み方を試してみるのがおすすめです。時間を計ったり、解き終わった後に感想や良かった点・悪かった点を話し合ったりする「振り返り」も大切です。無理強いせず、お子さんの意見や感覚を尊重し、試行錯誤をサポートしてあげてください。