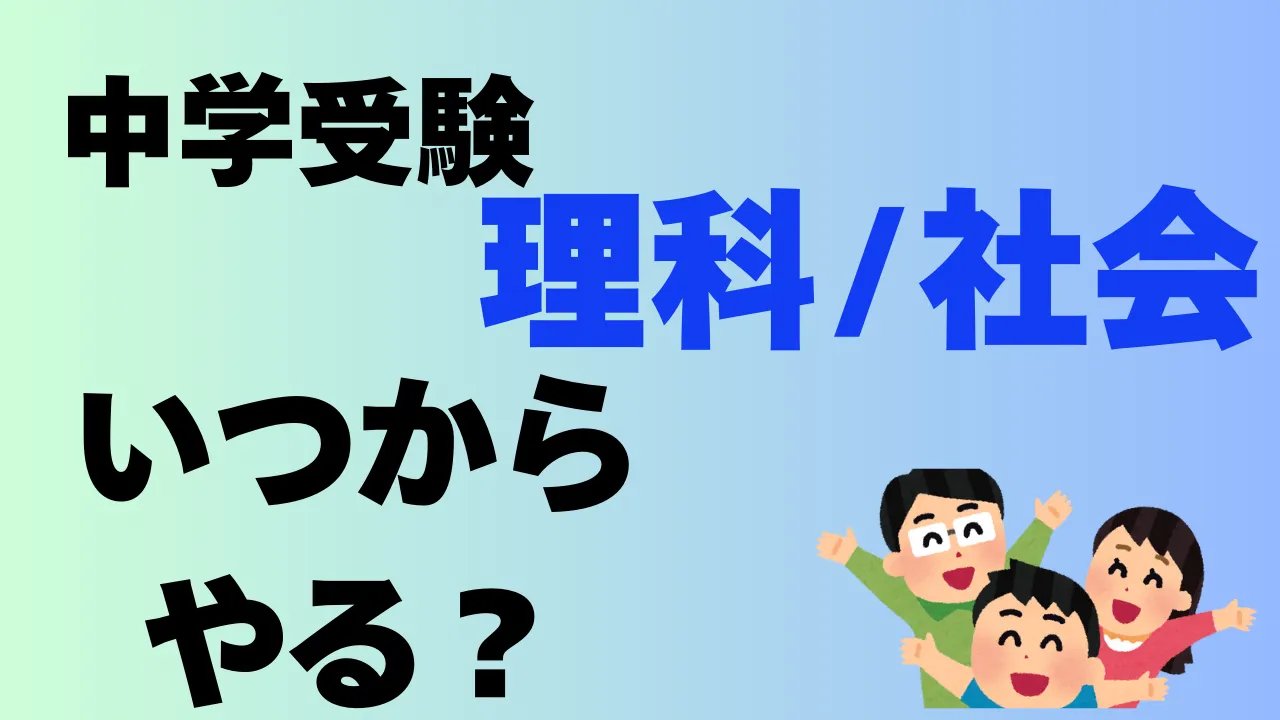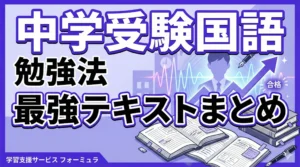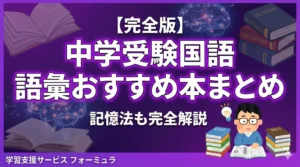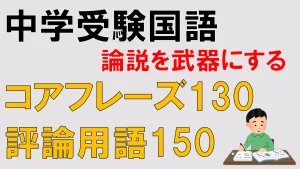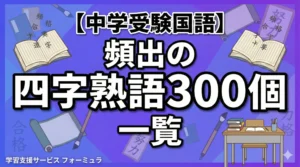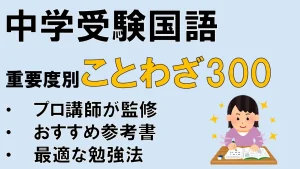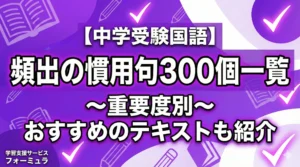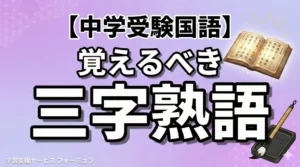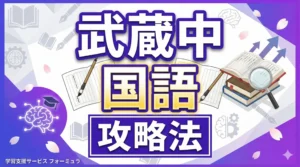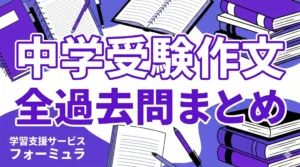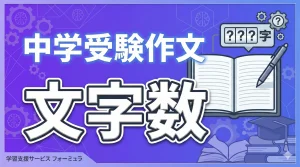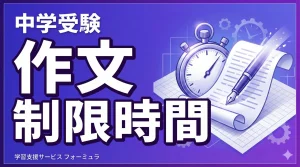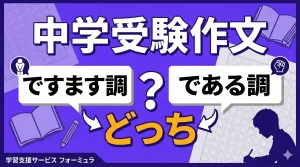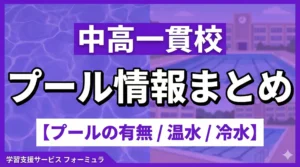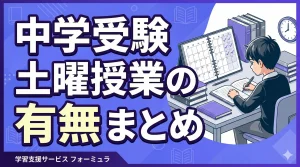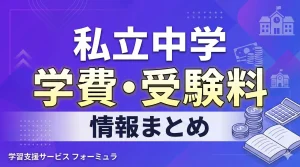この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
中学受験において、国語や算数と並んで重要な科目となる理科と社会。
- 「いつから本格的に勉強を始めればいいの?」
- 「算数や国語で手一杯で、理科・社会までなかなか…」
と悩む保護者の方は少なくありません。理科・社会は後回しにしても大丈夫なのでしょうか?
この記事では、中学受験における理科・社会の学習開始時期に関する疑問や不安にお答えします。中学受験プロ講師の神泉忍が、最適な開始時期の考え方から、後回しにした場合のリスク、学年別の効果的な学習法、そしてご家庭でできるサポートのコツまで、詳しく解説します。
この記事でわかること
- 中学受験の理科・社会の最適な学習開始時期の考え方
- 理科・社会の学習を後回しにするリスクと重要性
- 学年別の理科・社会の効果的な学習法と家庭でのサポート方法
中学受験の理科・社会「いつから?」保護者の悩み

中学受験の準備を進める中で、多くの保護者の方が理科・社会の学習開始時期について頭を悩ませています。算数や国語に比べて、どのように扱えばよいのか分かりにくいと感じる方もいるでしょう。ここでは、保護者の皆様が抱えがちな悩みについて見ていきます。
算数・国語で手一杯…
中学受験の勉強の中心は、やはり算数と国語になりがちです。特に算数は積み重ねが重要で、苦手意識を持つお子様も多いため、多くの時間を割くご家庭が多いでしょう。国語も、読解力や記述力を養うには時間がかかります。その結果、「理科や社会の勉強まで手が回らない」と感じるのは、多くの保護者に共通する悩みといえます。 まずは主要教科から、という考えは自然ですが、受験は総合力が問われることも忘れてはいけません。
「暗記科目だから後で」は正しい戦略?
理科や社会は、歴史の年号や出来事、生物の名前、地理の地名など、覚えるべきことが多い科目です。そのため、「暗記科目だから、入試直前に詰め込めば大丈夫」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、近年の中学入試では、単なる知識の暗記だけでなく、
- 知識を活用して考える力
- グラフ・資料を読み解く力
- 自分の言葉で説明する記述力
などが重視される傾向にあります。 これらの力は、付け焼き刃の学習ではなかなか身につきません。
周りの開始時期が気になる…焦りを感じていませんか
- 「〇〇さんのお子さんは、もう理科・社会の勉強を始めているらしい」
- 「塾の友達はみんな4年生から理社セットで受講しているみたい」
といった話を聞くと、「うちの子も早く始めないと!」と焦りを感じてしまうかもしれません。周りの状況が気になるのは当然ですが、大切なのは、他の家庭と比較することではなく、お子様の学習状況や性格、ご家庭の方針に合ったペースを見つけることです。 焦りは禁物です。
 塾長 神泉
塾長 神泉この記事では、その判断材料となる情報を提供していきます。
【結論】理科/社会は「小4から」取り組むのがおすすめ


理由①国語/算数が順調にいかない可能性がある
理科/社会は「小4から」取り組むべき理由の1つ目は、「国語/算数」が順調に進まない可能性があるためです。「理解/社会を直前期に回す」という戦略の前提は、「国語/算数」が順調に仕上がっているということです。しかし、難関中学志望レベルのお子さんも含めて、「国語/算数」が余裕で仕上がっているということはありません。算数に類稀な才能があるというケースもありますが、非常に少数です。
国語/算数が順調に仕上がっている前提で、理科/社会を後回しにしたにもかかわらず、国語/算数が仕上がっていなければ、より忙しい状況になってしまいます。
理由②勉強法が確立していない可能性がある
理科/社会は「小4から」取り組むべき理由の2つ目は、勉強法が確立していない可能性があるためです。理科/社会を最短で仕上げる期間として、「3ヶ月」と言われることがあります。この3ヶ月は、勉強法が確立していて、全く無駄のないリソースの使い方ができた場合に限ります。多くの受験生は、長期間勉強することで、自分の学習スタイルを身につけていくものです。いきなり、効率的な勉強ができないことを考えると、理科/社会に早期から触れ、時間をかけて、勉強法を確立していくことが望ましいでしょう。
理由③受験はバランスが大切
理科/社会は「小4から」取り組むべき理由の3つ目は、受験勉強は、バランスが大切であるためです。受験に求められるのは突出した能力ではなく、バランスよくできる能力です。4科目で「穴がない」状態を目指すことが求められます。また、理科/社会の学習は、国語や算数にも通じています。理科や社会でも計算が登場しますし、国語の文章では、社会的な知識が必要なものも多く出題されます。全科目にバランスよく触れることで、それぞれが体系的につながって理解が促進できるのです
理科/社会は「小4から」取り組むメリット
多くの進学塾では、小学4年生(あるいは小学3年生の2月)から理科・社会のカリキュラムが始まります。この時期から始める最大のメリットは、基礎からじっくりと学習を進められ、知識の土台をしっかりと築けることです。 比較的早い段階から4教科の学習リズムを作ることで、5年生、6年生になったときの負担感を軽減できます。一方で、低学年から勉強漬けになるのでは、という懸念を持つ方もいるかもしれません。
学年別!理科・社会の学習、どう進める?
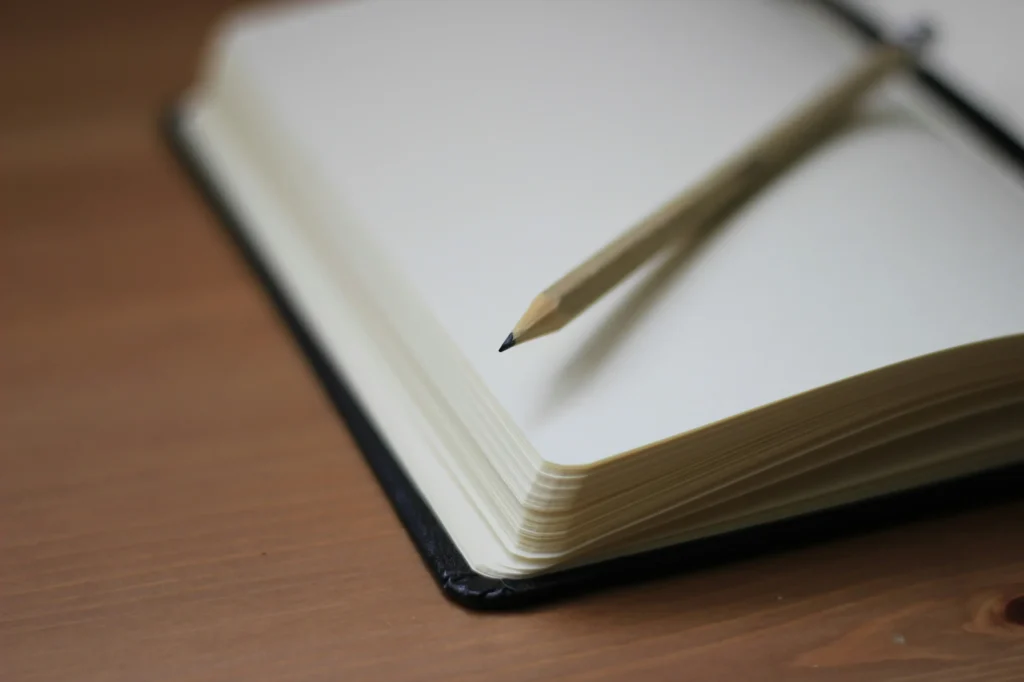
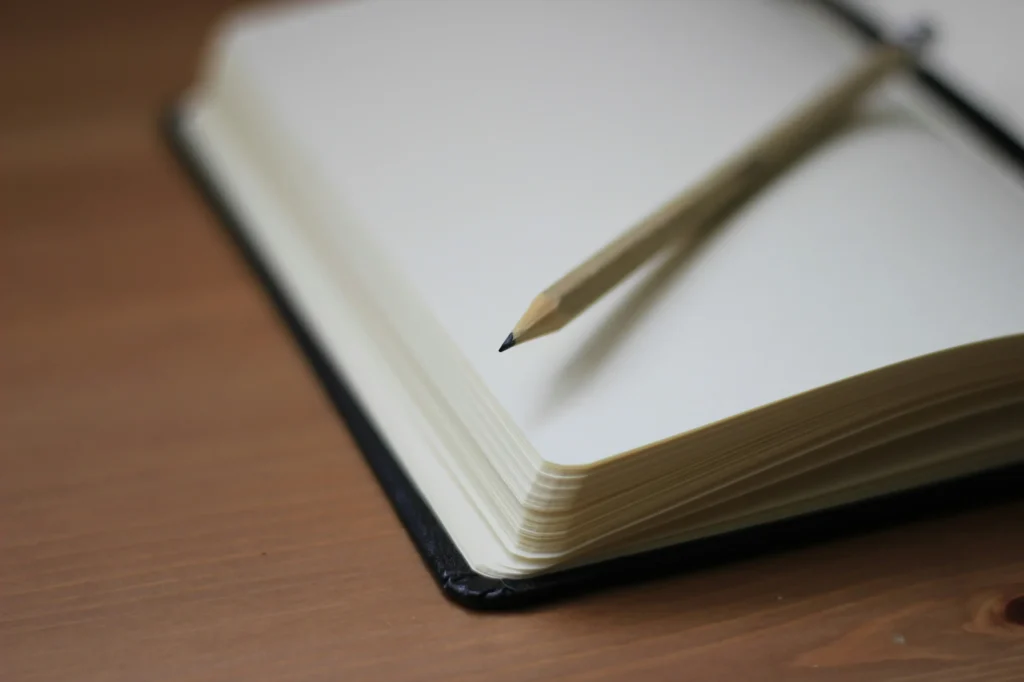
理科・社会の学習は、学年段階に応じて適切なアプローチがあります。低学年から6年生まで、それぞれの時期に合わせた学習の進め方のポイントを見ていきましょう。
【低学年】遊びや体験で興味を育てる
この時期は、本格的な勉強を始める前の「準備期間」と捉えましょう。図鑑を一緒に見たり、博物館や科学館、動物園、植物園などに出かけたり、キャンプや旅行で自然や文化に触れたりする体験を大切にします。大切なのは、お子様の「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心の芽を育むことです。 日常生活の中で、親子で会話しながら、身の回りの事象への興味関心を広げていきましょう。



「中学受験生にピッタリの図鑑はこれ!受験の傾向にそったおすすめ一覧!」では、中学受験生におすすめの図鑑を紹介しています。ぜひご覧ください。
【小4】基本用語とつながりの理解
多くの塾で理科・社会の授業が始まるこの時期は、まず基本的な用語の意味を正確に理解することが重要です。焦って先に進むのではなく、一つ一つの知識を丁寧にインプットし、それらがどのようにつながっているのかを意識しながら学習を進めましょう。 ノートの取り方を工夫したり、簡単な図や表でまとめたりする練習も始めるとよいでしょう。学習習慣を確立する時期でもあります。
【小5】知識の習得と整理・演習の開始
学習内容がより本格的になり、覚えるべき知識量も増えてきます。地理・歴史・公民、物理・化学・生物・地学といった各分野の学習が深まっていきます。インプットした知識を整理し、基本的な問題演習を通してアウトプットする練習を重ね、知識の定着を図りましょう。 定期的に復習を行い、苦手な単元や分野を早期に発見し、克服していくことが大切になります。
【小6】総復習と応用・実践力の総仕上げ
いよいよ受験学年です。これまでに学んだ膨大な知識を総復習し、知識の穴をなくすとともに、入試レベルの応用問題や過去問演習に本格的に取り組みます。志望校の出題傾向に合わせて、弱点を補強し、得点力を高めていくことが目標です。 時間配分を意識した演習や、記述問題対策なども含め、本番を見据えた実践的な学習を進めていきましょう。



6年生は総仕上げの時期。それまでに基礎が固まっているかが、合否を分けます。
理科・社会の学習サポートのコツ


塾に通っていても、家庭での学習サポートは欠かせません。特に理科・社会は、日常生活とのつながりを見つけやすい科目です。ここでは、保護者の方が家庭でできる学習サポートのコツをご紹介します。
日常生活と結びつけて興味を引き出す
日々のニュースや天気予報、食卓に並ぶ食材、旅行先での発見など、私たちの身の回りには理科・社会の学びのヒントがあふれています。
- 「この野菜はどこで作られたのかな?」
- 「今日のニュースに出ていた国はどこにあるんだろう?」
といった親子の会話を通して、学習内容と日常生活を結びつけ、興味関心を引き出しましょう。
図鑑や地図、ニュースを楽しく活用する
学習まんがや図鑑、地図帳、地球儀、子供向けの新聞やニュースなどを、リビングなどお子様が手に取りやすい場所に置いておくのも効果的です。無理に読ませるのではなく、自然に触れる機会を作ることを意識しましょう。 気になったことを一緒に調べたり、クイズ形式で問題を出し合ったりするのも、楽しく知識を深める良い方法です。
「なぜ?」を親子で楽しむ対話のすすめ
お子様が抱いた「なぜ?」「どうして?」という疑問は、学びの絶好のチャンスです。頭ごなしに否定したり、すぐに答えを教えたりするのではなく、「どうしてそう思うの?」「一緒に調べてみようか」と、考えるプロセスを共有し、探求する楽しさを体験させてあげましょう。 親子で一緒に学ぶ姿勢が、お子様の学習意欲を高めます。
【おすすめ】中学受験 理科/社会の学習指南本


中学受験の理科/社会をどのように攻略していけば良いか、お悩みの方は、「学習指南本」で情報を整理するのがおすすめです。いきなり学習を始めるのではなく、お子様と一緒に、全体像を整理してみましょう。親や先生が学習計画を理解していることも重要なのですが、お子様にも一定共有する中で進めた方が、スムーズに進みます。
中学受験 理科/社会の学習指南本まとめ
【中学受験 見るだけでわかる理科のツボ】
【中学受験 見るだけでわかる社会のツボ】
- Amazonレビューの声
- 中学受験の理科って何?という段階の人は手に取るとよい。
- 良く研究された分かりやすい内容です。



「【完全版】中学受験理科 目的別おすすめ問題集〜買っておけば間違いないテキストを一挙に紹介!」「【完全版】中学受験社会|基礎から難関まで対応できる厳選問題集」では、理科・社会のおすすめの問題集を徹底解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ


どの時期から始めるにしても、中学受験における理科・社会の重要性を早期に認識し、計画的に学習を進めていくことが合格への鍵となります。特に小学6年生になる前に、基礎的な知識をしっかりと固めておくことが、その後の応用力の伸びに大きく影響します。 行き当たりばったりではなく、長期的な視点を持って学習計画を立てましょう。
中学受験で理科・社会はいつから勉強を始めるのが最適ですか?
小学4年生から取り組むのがおすすめです。その理由は、国語/算数が必ずしも順調に進まない可能性があること、効率的な勉強法を確立する時間が必要なこと、そして受験はバランスが大切だからです。多くの進学塾でも小4から理科・社会のカリキュラムが始まります。
理科・社会を受験直前期まで後回しにするリスクはありますか?
はい、リスクがあります。近年の中学入試では単なる暗記だけでなく、知識を活用して考える力や資料を読み解く力、記述力が重視されます。これらは短期間では身につきにくいものです。また、国語や算数が思うように進まなかった場合、直前期にさらに忙しくなってしまう可能性もあります。
小学校低学年の段階で理科・社会の学習準備として何ができますか?
低学年は「準備期間」として、遊びや体験を通じて興味を育てることが大切です。図鑑を見たり、博物館や科学館に出かけたり、旅行で自然や文化に触れたりする体験を重視しましょう。お子様の「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心の芽を育み、身の回りの事象への興味関心を広げることが重要です。
家庭で理科・社会の学習をサポートするコツは何ですか?
日常生活と結びつけて興味を引き出すことがポイントです。ニュースや食卓の話題など身の回りのことを学習内容と関連づける会話をしましょう。図鑑や地図を手に取りやすい場所に置いておくこと、お子様の「なぜ?」という疑問を大切にして一緒に考えたり調べたりする対話も効果的です。親子で学ぶ姿勢がお子様の学習意欲を高めます。
小学校高学年(5・6年生)の理科・社会の学習はどう進めるべきですか?
小5では知識の習得と整理、基本的な問題演習を通したアウトプット練習が重要です。定期的な復習で苦手分野を早期発見・克服しましょう。小6では総復習と応用・実践力の総仕上げを行います。志望校の出題傾向に合わせた弱点補強、時間配分を意識した演習、記述問題対策など実践的な学習を進めることが目標となります。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ