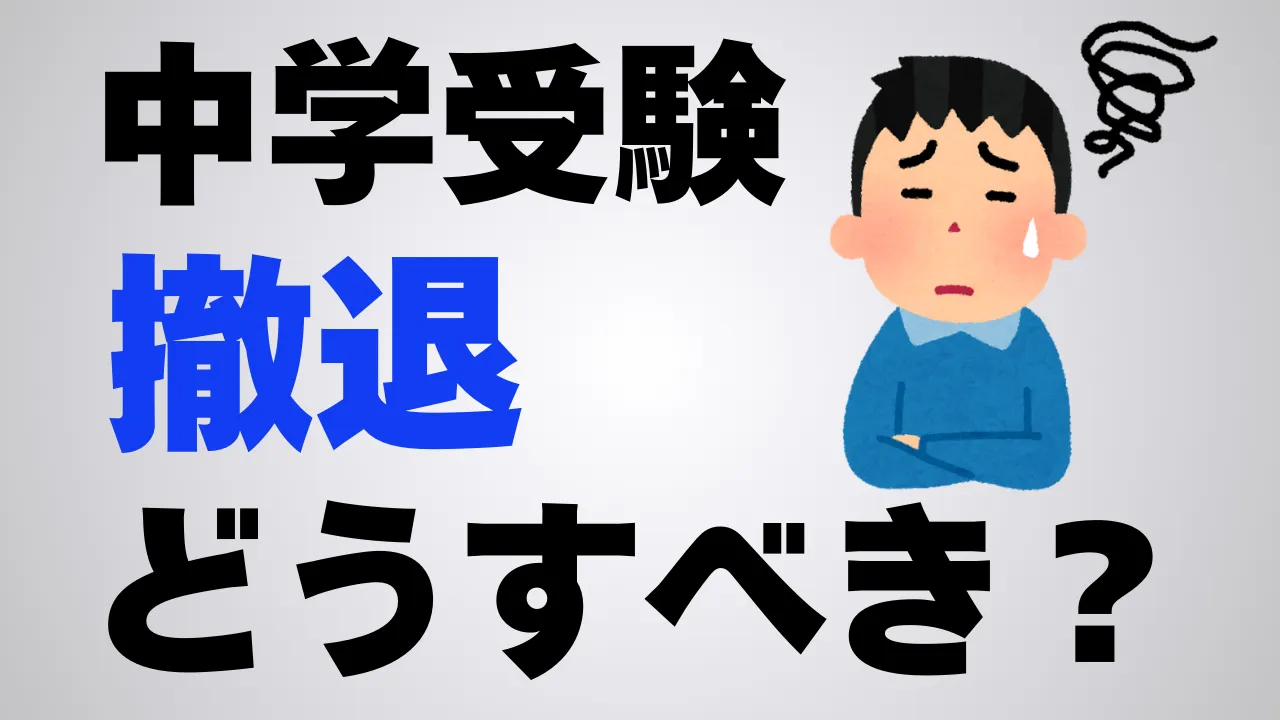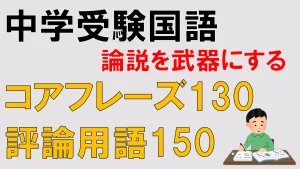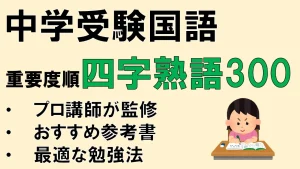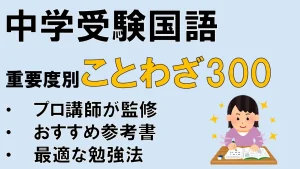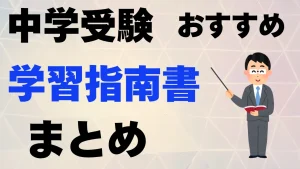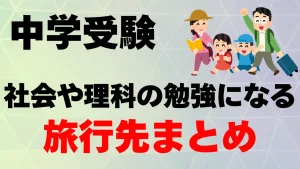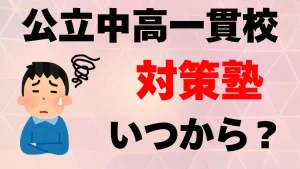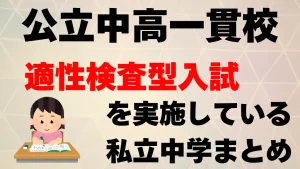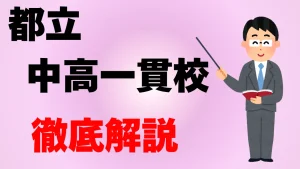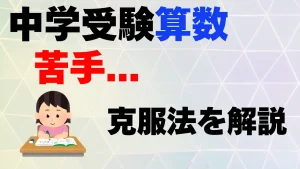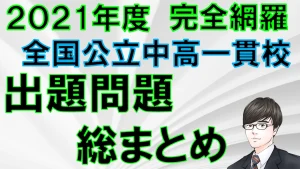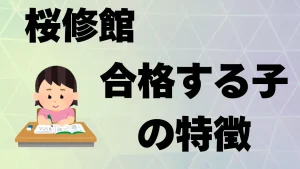この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
「もうこのまま続けていいのだろうか…」「撤退した方がいいのかもしれない…」中学受験に挑戦する親子の心に、そんな迷いが生じることは珍しくありません。 成績が思うように伸びない、お子さんのやる気が低下している、親子関係が悪化している—そんな状況に直面し、苦しい選択を迫られているご家庭も多いのではないでしょうか。
中学受験からの撤退は、これまで費やしてきた時間や労力、お子さんの努力を考えると、非常に重い決断です。しかし、時には立ち止まって別の道を選ぶことも、お子さんの将来のためには必要な判断かもしれません。
私は2013年から10年以上にわたり中学受験指導に携わり、2017年からはオンライン・オフライン両方の指導を行う私塾を開設してきました。これまで600人以上の受験生の指導やカウンセリングを通じて、様々な選択に悩む親子と向き合ってきました。
この記事では、撤退を考える際の判断基準やタイミング、撤退後のフォローについて具体的にお伝えします。 撤退のサインや判断ポイント、メリット・デメリット、そして撤退後の進路選択まで、親子が前向きに歩むための道筋を示します。
この記事を読むことで、「撤退」という選択が決して失敗ではなく、お子さんの個性や状況を考慮した大切な決断の一つであることを理解いただけるでしょう。最終的には、お子さんの心身の健康と将来の可能性を最大限に引き出す選択こそが最善の道なのです。
この記事でわかること
- 中学受験からの撤退を考えるサインと判断基準
- 撤退を決めた場合のメリット・デメリットと注意点
- 撤退後の学習フォローと前向きな進路選択の考え方
中学受験「撤退」が頭をよぎる…
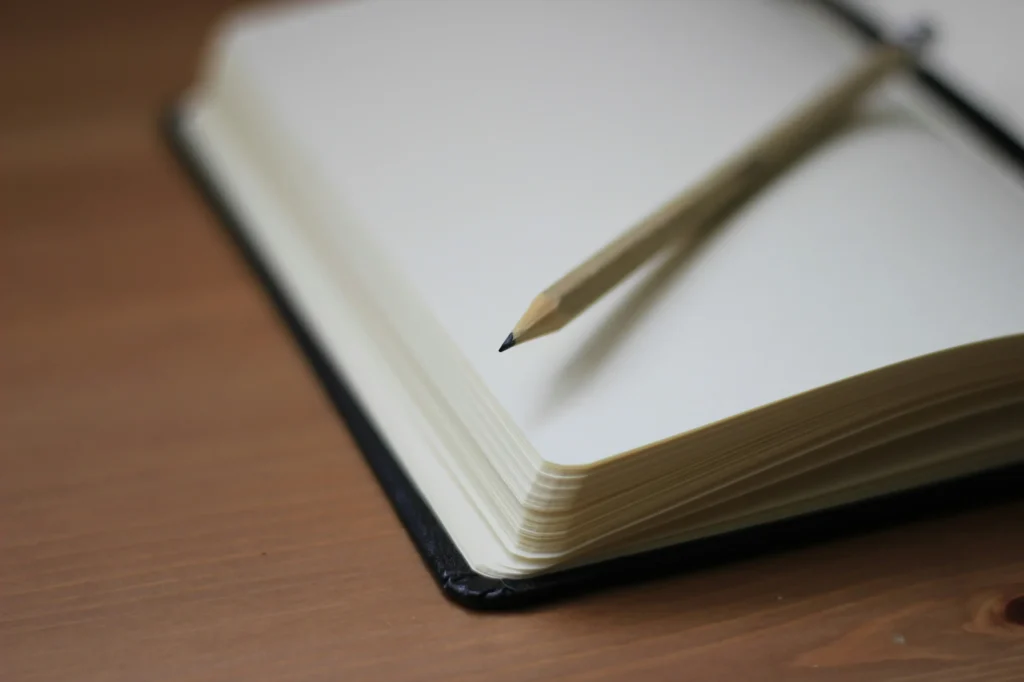
長い中学受験の道のりでは、順風満帆なことばかりではありません。時には立ち止まって、進むべき道を見直す必要が出てくることもあります。保護者の方が「撤退」という言葉を意識し始めるのは、どのような時なのでしょうか。いくつかの具体的なサインを見ていきましょう。
①成績が伸び悩んでいると感じるとき
一生懸命勉強しているにもかかわらず、模試の成績がなかなか上がらない、あるいは下がり続けてしまう。塾のクラスが維持できない、苦手科目が一向に克服できない…。そんな状況が続くと、「このまま続けても、合格は難しいのではないか」という不安が頭をもたげるかもしれません。ただし、成績の波は誰にでもあるため、一時的な不調だけで撤退を判断するのは早計です。 なぜ成績が伸び悩んでいるのか、その原因を探ることが大切になります。
②お子さんのやる気が見られないとき
以前は楽しそうに塾に通っていたのに、最近は行くのを嫌がるようになった。宿題になかなか取り組まない、あるいは答えを写すだけになっている。勉強中に集中できず、他のことばかり気にしてしまう…。お子さんから明らかなやる気の低下が見られると、保護者としては心配になります。中学受験は本人の意志なくして乗り越えることは難しいため、お子さんのモチベーションの変化は重要なサインといえるでしょう。
③親子関係が悪化していると感じるとき
「勉強しなさい!」とつい厳しく叱ってしまう回数が増えた。お子さんが反抗的な態度をとるようになった。受験のことで家庭内の雰囲気がピリピリしている…。中学受験が原因で、本来良好だったはずの親子関係に溝ができてしまうのは、とても悲しいことです。お子さんの将来を思うあまり、今の関係性を犠牲にしてしまっては本末転倒かもしれません。
④受験勉強による心身の負担が大きいとき
睡眠不足が続いている、食欲がない、頭痛や腹痛を訴えることが増えた、あるいは精神的に不安定になっている様子が見られる。それはお子さんだけでなく、サポートする保護者の方自身が疲れ切ってしまっている場合もあるでしょう。心身の健康は何よりも大切です。明らかな不調のサインが見られる場合は、無理を続けるべきではありません。
撤退を判断する前に確認したいこと

「もう限界かもしれない」と感じても、すぐに撤退を決断する前に、一度立ち止まって冷静に状況を見つめ直してみましょう。後悔しない判断をするために、確認しておきたいポイントがいくつかあります。
お子さんの本当の気持ちを探る
保護者の方が「撤退した方がいいのでは」と感じていても、お子さん自身はどう思っているでしょうか。「本当は続けたい」「友達と一緒に頑張りたい」という気持ちがあるかもしれません。逆に、「もうやめたい」と思っていても、言い出せずにいる可能性もあります。まずは、お子さんの気持ちを丁寧に聞き、本音で話し合う時間を持つことが大切です。 一方的に意見を押し付けるのではなく、お子さんの言葉に耳を傾けましょう。
成績不振の原因はどこにあるのか?
成績が上がらない原因は、必ずしもお子さんの能力だけの問題ではありません。勉強方法が合っていない、学習内容が難しすぎる、塾の授業についていけていない、特定の科目に大きな苦手意識があるなど、様々な要因が考えられます。原因を特定できれば、塾の先生に相談したり、学習方法を見直したりすることで、状況が改善する可能性もあります。
家庭学習の環境やサポート体制は見直せるか?
集中して勉強できるスペースはあるか、学習時間を確保できているか、保護者の声かけは適切か、丸付けやスケジュール管理の負担はどうか、塾との連携はうまくいっているか…。家庭学習を取り巻く環境やサポート体制を改めて見直してみましょう。すべてを完璧にする必要はありませんが、少しの工夫や見直しで、お子さんの学習効率が上がることもあります。
志望校へのこだわりは親子で一致しているか?
設定している志望校は、本当にお子さんの学力レベルや個性、希望に合っているでしょうか。保護者の期待だけで高い目標を設定してしまい、お子さんがプレッシャーを感じている可能性はありませんか。場合によっては、志望校のレベルを見直したり、目標を再設定したりすることも、状況を打開する一つの方法です。
撤退の判断ポイントとタイミング

撤退か続行か、最終的な判断を下すのは非常に難しいことです。どのような点を考慮し、どのタイミングで判断するのが適切なのでしょうか。いくつかのポイントを解説します。
判断のヒントまとめ
- お子さんの心身の健康状態は正常か
- 学習意欲は回復しそうか
- 成績不振への対策ができそうか
- 家庭環境やサポート体制は見直せるか
- 志望校はお子さんに合っているか
お子さんの心身の健康状態を最優先に
繰り返しになりますが、何よりも優先すべきはお子さんの心と体の健康です。 受験勉強が原因で、明らかな心身の不調(不眠、食欲不振、継続的な体調不良、うつ状態など)が見られる場合は、無理に受験勉強を続けるべきではありません。まずはゆっくり休養し、必要であれば医療機関やカウンセリングなど、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
学習意欲が回復する可能性はあるか?
一時的なスランプや疲れで学習意欲が低下しているのか、それとも根本的に中学受験への意欲を失ってしまっているのかを見極めることが大切です。塾の先生や、可能であれば第三者の意見も聞きながら、お子さんとしっかり話し合いましょう。学習計画の調整や、短期間の休息、小さな目標設定などで、再び前向きに取り組めるようになるか、改善の兆しが見られるかどうかが一つの判断材料になります。
学年別に見る撤退判断のタイミング

撤退を判断するタイミングは、学年によっても状況が異なります。
小学4年生
本格的な受験勉強が始まる時期であり、まだ軌道修正がしやすい段階です。もしお子さんが勉強に苦痛を感じているようなら、無理に進めるのではなく、一度立ち止まって考える良い機会かもしれません。
小学5年生
学習内容が難しくなり、中だるみしやすい時期でもあります。成績の変動も大きくなりがちです。ここで諦めずに乗り越えることで、大きく成長する可能性もありますが、負担が大きい場合は撤退も現実的な選択肢となります。
小学6年生
受験本番が近づき、プレッシャーも最大になります。夏休み以降の撤退は、精神的なダメージも大きく、高校受験への切り替えも時間的に厳しくなる可能性があります。ただし、限界を感じているなら、どの時期であってもお子さんの健康を最優先に考えるべきです。
最終判断はいつまでに?期限を設けることの重要性
撤退するかどうか悩み続けてしまうと、親子ともに精神的に疲弊してしまいます。「夏休み前まで」「〇月の模試の結果を見て」など、ある程度の期限を設けて判断することをおすすめします。期限を決めることで、それまでは全力で頑張るという覚悟ができたり、次のステップへ進むための心の準備ができたりする効果が期待できます。
中学受験撤退のメリット

中学受験からの撤退は、決してネガティブなことばかりではありません。メリットとデメリットを客観的に整理し、ご家庭にとってどちらが大きいかを考えてみましょう。
①時間的・精神的な余裕が生まれる
中学受験をやめると、これまで塾や勉強に費やしていた時間を、他の活動に使えるようになります。習い事を再開したり、家族で過ごす時間を増やしたり、友達と遊ぶ時間を持ったりすることで、お子さんの心にゆとりが生まれるでしょう。保護者の方も、塾の送迎や弁当作り、スケジュール管理といった負担から解放され、精神的なプレッシャーも軽減されるはずです。
②親子関係が改善する可能性
受験勉強を巡る口論や衝突がなくなり、家庭内の雰囲気が穏やかになることが期待できます。「勉強しなさい」という言葉から解放され、お子さんの良い面に目を向けられるようになるかもしれません。お子さん自身も、プレッシャーから解放されることで、本来の明るさを取り戻し、自己肯定感が高まるきっかけになることもあります。
中学受験撤退のデメリット

①高校受験への切り替えが必要になる
中学受験をしない場合、多くは地元の公立中学校へ進学し、高校受験を目指すことになります。高校受験は中学受験とは異なる準備が必要です。中学校の成績(内申点)が重要になること、受験科目や出題傾向が違うことなどを理解しておく必要があります。撤退を決めたら、早めに高校受験の情報収集と学習計画の立て直しを始めることが大切です。
②これまでの努力が無駄になったと感じることも
長期間にわたって頑張ってきた勉強や、費やした時間・お金が無駄になってしまったと感じ、親子ともに喪失感や後悔の念を抱くことがあるかもしれません。特に、一緒に頑張ってきた塾の友達が合格していく姿を見るのは、辛いと感じることもあるでしょう。しかし、中学受験を通して得た知識や学習習慣、そして困難に立ち向かった経験は、決して無駄にはなりません。その経験は必ず将来に活きてきます。
「撤退」を決めたら…親子で前向きに進むために
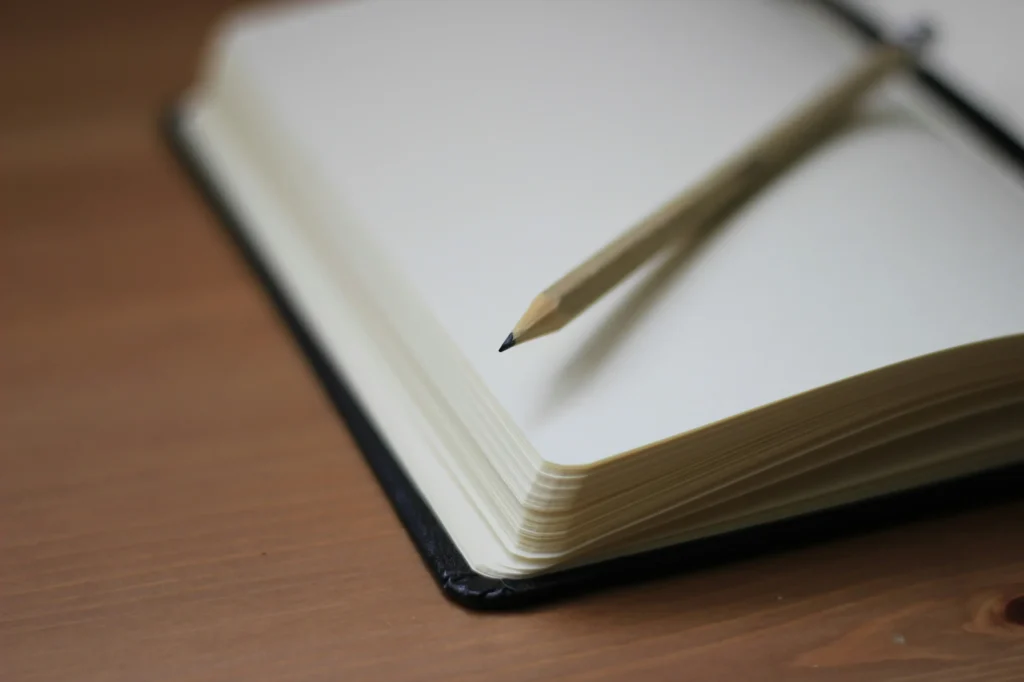
撤退という決断を下した後、親子でどのように向き合い、次のステップへ進んでいけばよいのでしょうか。大切な心構えと具体的な行動についてお伝えします。
お子さんへの伝え方
撤退の理由をお子さんの成績ややる気のせいにするような伝え方は絶対に避けましょう。「あなたのせいじゃないよ」「一緒に考えて、これからは違う道で頑張ろうと決めたんだよ」と、あくまで親子で話し合って決めた「選択」であることを伝えてください。まずは、お子さんの悔しさや悲しさ、不安な気持ちを否定せずに、しっかりと受け止めてあげることが大切です。
これまでの頑張りを認め、ねぎらう
結果がどうであれ、中学受験に向けて努力を続けてきたお子さんの頑張りは事実です。「〇〇を一生懸命頑張っていたね」「難しい問題にもチャレンジしていたね」など、具体的なプロセスを褒め、これまでの努力をしっかりと認め、ねぎらいの言葉をかけてあげてください。お子さんが自信を失わないように、「あなたはよく頑張った」というメッセージを伝えることが重要です。
塾への連絡
撤退を決めたら、できるだけ早く、正直に塾へ連絡しましょう。これまでお世話になった感謝の気持ちを伝えつつ、撤退する旨とその理由(家庭の判断、本人の意向など)を簡潔に伝えるのがよいでしょう。塾によっては引き止められる場合もありますが、家庭で決めたことであれば、その意思を明確に伝える姿勢も必要です。
撤退は「終わり」ではなく「新しいスタート」
中学受験からの撤退を、目標を達成できなかった「終わり」と捉えるのではなく、高校受験やその先の未来に向けた「新しいスタート」と捉えることが大切です。親子で気持ちを切り替え、次の目標に向かって前向きに進んでいくための第一歩としましょう。
撤退後の学習について
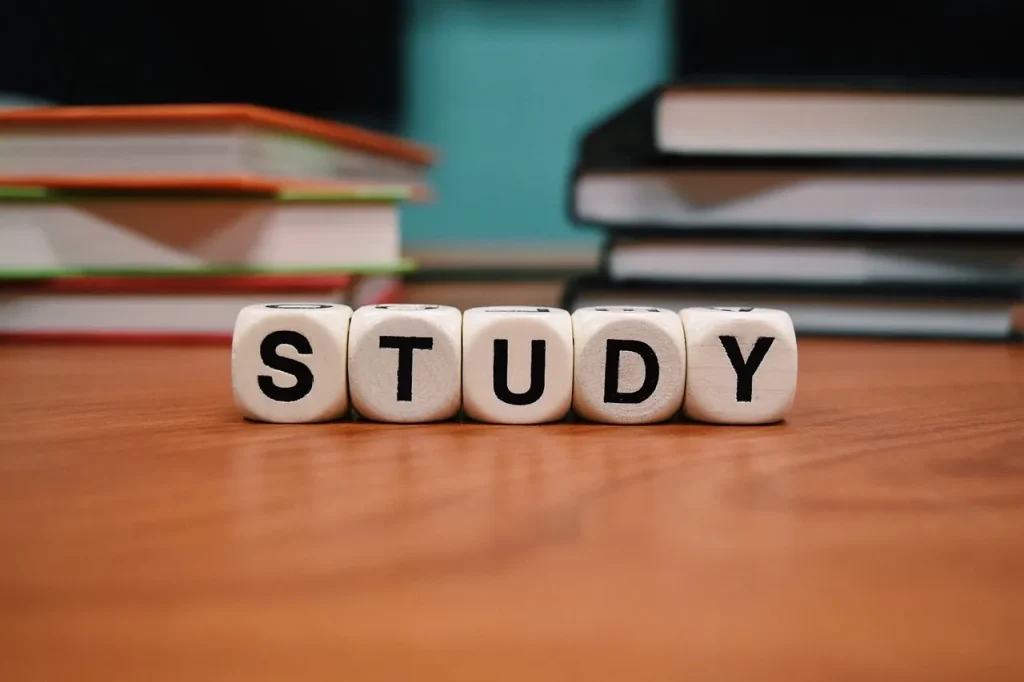
中学受験から撤退した後、学習面でどのようなフォローをしていくかが重要になります。高校受験に向けてスムーズに移行するためのポイントを見ていきましょう。
休息期間を設ける
長期間の受験勉強で、お子さんは心身ともに疲れている可能性があります。撤退直後は、無理に次の勉強を始めさせようとせず、まずはゆっくり休む期間を設けることも有効です。
趣味に没頭したり、好きなことをする時間を作ったりして、リフレッシュすることが、次のステップへのエネルギーになります。
中学校の授業についていくための基礎固めをしてみる
高校受験では、中学校での学習内容が基本となります。まずは、中学校の授業にしっかりついていけるように、小学校の学習内容(特に算数・国語)の復習や、中学校の予習など、基礎固めを意識しましょう。特に、英語と数学は積み重ねが重要な科目なので、早めに取り組むことが有利になります。
高校受験に向けた学習計画の立て方
高校受験は、中学3年間の成績(内申点)と学力検査の結果で合否が決まります。目標とする高校のレベルをある程度定め、内申点対策(定期テスト対策、提出物など)と、受験科目の学習計画を立てる必要があります。中学受験とは評価軸や対策が異なるため、情報収集を行い、早めに計画を立てることが重要です。
新しい学習スタイルを試してみる
集団塾のペースや雰囲気が合わなかったという経験から、撤退後の学習方法として、個別指導塾や家庭教師、オンライン学習教材などを検討するのも良いでしょう。お子さんの性格や学習ペースに合った、無理なく続けられるスタイルを見つけることが大切です。
高校受験のリアル/中学受験撤退組の選択肢

中学受験を撤退した場合、どのような進路選択が考えられるのでしょうか。高校受験を取り巻く状況について解説します。
公立高校という選択肢のメリット
多くの撤退組が選ぶのが、地元の公立中学校へ進学し、公立高校を目指す道です。公立高校には、多様なバックグラウンドを持つ生徒が集まる環境、地域に根差した活動、そして学費負担が比較的軽いといったメリットがあります。地域のトップレベルの公立高校を目指し、難関大学へ進学する生徒も少なくありません。
高校受験で私立高校を目指すのもあり
中学受験と比べると選択肢は減りますが、高校から募集を行っている私立高校も存在します。独自の教育方針や充実した設備を持つ学校もありますが、募集人数が少なかったり、難易度が高かったりする場合もあります。高校受験で私立を目指す場合は、早めに情報収集を行い、対策を立てることが必要です。
 塾長 神泉
塾長 神泉高校募集を廃止する私立も多いので、選択肢は限られますが、私の教え子でも高校から私立に入った受験生もいます。
中高一貫校でなくても大学進学は目指せる
中学受験の目的として、大学進学を有利に進めることを考えている方もいるかもしれません。しかし、必ずしも中高一貫校でなければ難関大学に進学できないわけではありません。高校受験を経て入学した高校でしっかりと努力を続ければ、希望する大学への道は十分に開かれています。
大切なのはお子さんに合った進路を選ぶこと
中学受験をするかしないか、どの高校を選ぶか。最終的に大切なのは、偏差値や評判だけでなく、お子さんの個性、興味、将来の目標に合った進路を選ぶことです。 親子でよく話し合い、納得のいく道を選択できることが理想です。
保護者自身の心のケアも忘れずに


中学受験からの撤退は、お子さんだけでなく、保護者の方にとっても大きな決断であり、精神的な負担がかかるものです。ご自身の心のケアも大切にしてください。
頑張ってきた自分自身も認めてあげよう
中学受験は、お子さんだけでなく、保護者の方にとっても大変な挑戦です。毎日の送迎、お弁当作り、学習サポート、精神的な支え…これまで本当に多くの時間とエネルギーを費やしてきたはずです。結果がどうであれ、お子さんと一緒に頑張ってきたご自身の努力を認め、ねぎらってあげてください。
周囲と比較せず、わが家の選択を信じる
他の家庭の成功体験や、SNSなどで目にする情報に心を乱されてしまうこともあるかもしれません。しかし、教育方針や子育ての形は家庭によって様々です。周囲と比較するのではなく、「わが家にとってはこれが最善の選択だった」と、自分たちの決断を信じることが大切です。



SNSは情報収集に使える反面、情報の波となり、判断を狂わせる可能性も高いです。
中学受験撤退は決して「失敗」ではない


中学受験からの撤退は、決して「失敗」や「負け」ではありません。それは、お子さんの個性や状況、そしてご家庭の状況を総合的に考えた上での、将来に向けた大切な「選択」の一つです。
撤退後のフォロー次第で可能性は広がる
大切なのは、撤退した後にどう過ごすかです。適切な学習フォローを行い、お子さんの興味や関心を広げる機会を作ることで、中学受験とは別の形で、お子さんの可能性を大きく伸ばしていくことができます。高校受験やその先の未来に向けて、新たな目標設定をすることが大切です。
撤退せずに続行する場合にすべきこと


中学受験からの撤退という選択肢を考えた末、「やはり、もう少し頑張ってみよう」と、受験勉強の続行を決断されたご家庭もあると思います。それはまた、親子にとって大きな覚悟と勇気のいる決断です。「受験を続行する」と決めたからには、ただこれまでと同じように頑張るのではなく、現状の課題を踏まえて、より良い方向へ進むための具体的なアクションを起こすことが重要になります。 その中心となるのが、「学習戦略の練り直し」です。
学習戦略を練り直そう!
なぜ今、学習戦略を見直す必要があるのでしょうか。それは、これまでと同じやり方を続けていては、また同じような壁にぶつかってしまう可能性があるからです。撤退を考えたということは、現在の学習方法や環境、目標設定などに、何らかの課題があったはずです。このタイミングで一度立ち止まり、戦略を練り直すことが、今後の学習をより効果的に進め、お子さんの負担を軽減し、そして合格可能性を高めるための重要な転換点となります。
学習戦略の見直しポイント3選


学習戦略を見直すといっても、どこから手をつければよいか迷うかもしれません。ここでは、特に重要な3つのポイントに絞って解説します。
①志望校戦略の見直し
まずは、目標設定の根幹である志望校について、改めて検討してみましょう。現在の成績状況や学習の進捗、そして何よりお子さんの意欲や適性を考慮した上で、設定している志望校のレベルは適切でしょうか。難易度が高すぎると、モチベーションの維持が難しくなることがあります。
場合によっては、第一志望校は変えずに併願校の組み合わせを見直したり、お子さんの得意科目を活かせる入試方式の学校を探したりするなど、柔軟な視点で戦略を再構築することが有効です。
②学習リソースの見直し
次に、お子さんが学習に利用している「リソース」、つまり「時間の使い方」を見直してみましょう。現在の学習スタイルを変えるにしても、「時間」に関しては増やすことはできません。
- 学校の授業
- 塾の授業
- 自習
の3つをこなしていく以上、そう簡単に時間を増やすことはできません。ですので、「そもそも塾の休日講習が必要なのか」「個別指導は必要なのか」「スキマ時間を活用できているか」といった形で、時間の使い方を見直さなければなりません。



ちなみに「時間の使い方」についてはこちらの記事で紹介しています。
③学習コンテンツの見直し
最後に、学習の「中身」、つまり「何を」「どのように」学ぶかを見直します。苦手科目は、どこでつまずいているのか原因を特定し、基礎まで遡って集中的に学習する必要があるかもしれません。得意科目は、さらに得点源とするために応用問題に取り組むなど、メリハリをつけることが大切です。また、過去問演習の進め方や、各科目の時間配分、日々の学習スケジュールの見直しなども重要です。
中学受験戦略を見直すにあたりおすすめの指南本
中学受験 大逆転の志望校選びと過去問対策 令和最新版
- Amazonレビューの声
- 各学校の校風マトリクスに国語算数の処理時間マトリクスなど、他の中学受験本とは全く異なる内容です。
- 学校選びから勉強法赤本の使い方などかなり細かく、理解しやすく書かれています
後悔しない中学受験100 親が知っておきたいこと、できること
- Amazonレビューの声
- 受験に関する情報を、ただ並べるのではなく「具体的に」「何を」「どう」するとよいかまで書かれています。
- 笑っちゃうエピソードもたくさんあって、子供も一緒に読んで笑い、親が言っても完全スルーな勉強法も、「ふむふむ」と納得してもらうことにも使えました。
中学受験 自走モードにするために親ができること
- Amazonレビューの声
- 言葉選びが絶妙で読みやすく、書かれてる内容を子供に説明するにも拝借しやすく非常に助かりました。
- 知りたいことというより、中学受験に関する本質が書いてある。



受験指南本について100冊以上もっている私が厳選した3冊がこちらです。
まとめ
中学受験からの撤退は決して失敗ではなく、お子さんの状況を考慮した重要な選択肢の一つです。撤退を考える際は、成績不振、モチベーション低下、親子関係の悪化、心身の負担などのサインに注目し、お子さんの気持ちを丁寧に聞くことが大切です。撤退後は適切な休息期間を設け、高校受験に向けた新たな学習計画を立てましょう。また続行を選んだ場合は、志望校や学習方法の見直しが必要です。どちらの道を選んでも、お子さんの健康と将来の可能性を最優先に考え、親子で前向きに進んでいくことが何より重要です。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
中学受験からの撤退を考え始めるのは、具体的にどのようなサインが見られたときですか?
お子さんの成績が長期的に伸び悩んでいる、学習へのやる気が著しく低下している、受験勉強が原因で親子関係が悪化している、お子さんや保護者自身に明らかな心身の不調(睡眠不足、食欲不振など)が見られる、といった状況が続く場合は、撤退を検討するサインかもしれません。
撤退するかどうかを判断する上で、最も大切にすべきことは何ですか?
何よりも、お子さんの心と体の健康状態を最優先に考えることです。成績や世間体よりも、お子さんが健やかに過ごせているかを第一に考慮してください。明らかな不調が見られる場合は、無理に受験勉強を続けるのではなく、休息や専門家のサポートも視野に入れることが重要です。
中学受験を撤退することのメリットとデメリットを教えてください
メリットとしては、親子ともに時間的・精神的なプレッシャーから解放され、関係性が改善する可能性がある点です。デメリットは、多くの場合、高校受験への切り替えが必要となり、その準備が求められる点、そして親子ともに喪失感や後悔を感じる可能性がある点です。
もし撤退を決めた場合、子どもにはどのように伝えるのが良いでしょうか?
お子さんを責めるような伝え方は避け、「あなたのせいではない」「一緒に考えて決めた選択だ」ということを明確に伝えましょう。これまでの努力を具体的に認め、ねぎらいの言葉をかけることが大切です。お子さんの悔しさや不安な気持ちに寄り添い、受け止めてあげてください。
撤退せずに中学受験を続けると決めた場合、まず何をすべきですか?
これまでと同じやり方ではなく、「学習戦略を練り直す」ことが重要です。具体的には、①現状に合わせた志望校戦略の見直し、②塾や教材などの学習リソース(時間配分含む)の最適化、③苦手克服や得意伸長など学習コンテンツ(学習内容・方法)の改善、の3点を見直しましょう。