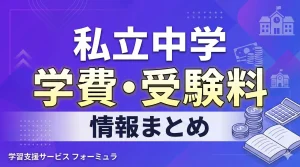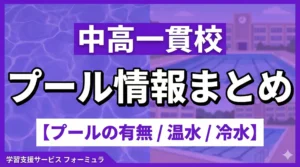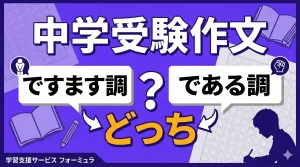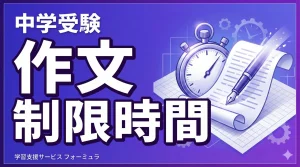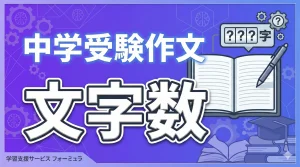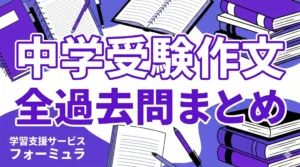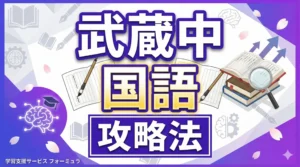この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
中学受検専門の作文添削塾を運営するプロ講師がテキストを厳選
2017年から中学受検専門の作文添削塾を運営しております
皆さん、こんにちは!中学受検専門の作文添削塾を運営している神泉忍です!中高一貫校の作文試験の合格を目指す受検生の皆さんの作文添削を日々行っております。

元々中学受験の国語指導を行ってきましたので、通常の国語の指導と作文の指導の共通点や違いなどを深く分析しながら授業の品質を高めてきました。2017年にオンライン添削中学受験専門の作文添削塾を立ち上げて全国の中高一貫校の作文添削を年間100人程度行ってきました。
 塾長 神泉
塾長 神泉オンライン添削で場所に縛られず全国の中高一貫校の作文試験を広く指導することができたのは非常に大きな財産です。
塾なしでも塾ありでも効果バツグンなテキストを一挙紹介!
全国の中高一貫校の作文試験について知り尽くした私が、今回「中高一貫校の作文試験対策の神テキスト」を一挙紹介させていただきます!テキストを何となく眺めたというレベルではなく、実際の生徒さんの使用感や合否結果を多くのデータと経験を元に厳選させていただきました。
まずは作文で求められている力を理解する
作文で求められている力を見誤ると全く点数が伸びない!
作文試験は「求められている力」を見誤ると致命的に点数が伸びない恐ろしい科目です。特に「発想力」「アイディア」を試す試験と誤認されている受検生や保護者様は多いです。公立中高一貫校の試験自体が積み上げ学習で対策できない性質が強く作文試験もその特徴を踏襲しているように見えるのですが、実態は異なります。


- 「基本的な文章が書けること」
- 「基本的な論理思考ができること」
- 「基本的な出題意図を満たすこと」
ができれば合格点を超えるようになっているのが中高一貫校の作文試験です。突飛な力を求められているわけではありませ。ん。求められる力は、基本的なトレーニングで獲得できるのでご安心ください。



作文で求められている力について掘り下げて解説したのがこちらの記事です。
採点要素は大きく3つ
作文試験の採点要素は大きく3つです。
作文試験の採点要素まとめ
- 構成
- 配点割合20%
- 設問に対する文字量の配分/論理構成/出題条件
- 配点割合20%
- 表現
- 配点割合20%
- 誤字脱字/文法的誤り/作文の作法
- 配点割合20%
- 内容
- 配点割合60%
- 出題意図を満たした内容か/論理的に説得力があるか
- 配点割合60%
このページでは各々の採点要素で最も重要な考え方を簡単にまとめて解説します!
【構成】〇〇を多く記述する
作文試験では、まず、「構成が適切か」が採点されています。構成の型はいくつかありますが、どの型にも共通しているのは、「理由説明」パートが全体の8割を占めるということです。作文試験では、自分の意見は端的に短く述べましょう。そして、意見自体はさほど点数に影響しません。意見それ自体よりも、その意見を支える根拠部分に文字数多く割かれているかを採点されています。


【表現】作文の文体をしっかりと習得しよう
作文試験では、当然ながら「表現」項目も採点対象となっています。
- 原稿用紙の使い方
- 誤字脱字
- 書き言葉で文章が書けているか
といった要素で採点されており、小説家のような素晴らしい表現を求められているわけではありません。表現の採点は
良いところがあって加点というよりも悪い所がなく減点がないという状態を目指しましょう。小学生の皆さんが習得に時間を要するのが「書き言葉」です。「話し言葉」をそのまま文章化してしまう受検生が多いです。
以下の表現に注意して作文練習を進めてみてください。
中学受験作文で気を付けるべき表現まとめ
- 使ってはいけない口語表現「やっぱり」
- 正しい表現「やはり」
- 使ってはいけない口語表現「全然」
- 正しい表現「全く」
- 使ってはいけない口語表現「全部」
- 正しい表現「すべて」
- 使ってはいけない口語表現「一番」
- 正しい表現「最も」
- 使ってはいけない口語表現「絶対に」
- 正しい表現「必ず」
- 使ってはいけない口語表現「たぶん」
- 正しい表現「おそらく」
- 使ってはいけない口語表現「とっても/とても/すごく」
- 正しい表現「非常に/大変」
- 使ってはいけない口語表現「ちょっと」
- 正しい表現「少し」
- 使ってはいけない口語表現「いっぱい/たくさん」
- 正しい表現「多くの」
- 使ってはいけない口語表現「もっと」
- 正しい表現「さらに」
- 使ってはいけない口語表現「だんだん」
- 正しい表現「次第に」
- 使ってはいけない口語表現「どんどん」
- 正しい表現「急速に」
- 使ってはいけない口語表現「やっと」
- 正しい表現「ようやく」
- 使ってはいけない口語表現「いつも」
- 正しい表現「常に」
- 使ってはいけない口語表現「ちゃんと」
- 正しい表現「きちんと/正しく」
- 使ってはいけない口語表現「だいたい」
- 正しい表現「およそ」
- 使ってはいけない口語表現「どうして/なんで」
- 正しい表現「なぜ」
- 使ってはいけない口語表現「どんな」
- 正しい表現「どのような」
- 使ってはいけない口語表現「どっち」
- 正しい表現「どちら/いずれ」
- 使ってはいけない口語表現「~けど」
- 正しい表現「~が」
- 使ってはいけない口語表現「~から」
- 正しい表現「~ため」
- 使ってはいけない口語表現「~たら」
- 正しい表現「~ば」
- 使ってはいけない口語表現「~んです」
- 正しい表現「~のだ/~です」
大人からすると当然の注意事項ですが、長文を書き慣れていない小学生にとっては「書き言葉」はなじみがありません。作文の練習を始めたての頃は、「話し言葉」を多用してしまう受検生が多いですが、根気強く1つずつ修正していきましょう。


また、適切に「漢字」を使いこなせるということも習得に時間を要します。「中高一貫校の作文試験」では小学校六年生までの範囲の漢字をマスターしておきましょう。中高一貫校を受検する場合、漢字の学習については先取りで早めにマスターするのが吉です。
学校の学習進度に合わせると小六の卒業時期と同時に漢字の学習が終わるようにスケジューリングされており、そのスケジュールでは小六までの漢字を作文で適切に扱えるレベルまでは到達しません。そこで漢字については「中学受験生」の学習進度を参考にすると良いでしょう。理想は、小五までに小六の漢字学習を修了することです。私は、中学受験国語の指導も行っておりますが、漢字の習得については「漢検」を活用して、先取り学習するのがおすすめです。



こちらの記事で漢字学習の方法について徹底解説しております。
【内容】「論理思考×出題意図のくみ取り」で高得点を狙おう
最後の採点要素は「作文の中身」、つまり「内容」です。「合格点をとれる内容」を安定して考え出せるようにすること」が最も作文対策で時間がかかり、かつ、採点の点数としても最も、ウエイトが大きいです。100点満点で言えば、60点が「内容」についての配点で占めると考えて良いでしょう。


「合格点をとれる内容」とは具体的にどんな内容なのか?「誰にも思いつかないようなアイディア」「独自性が強く読み手を魅了するネタ」が書ければそれに越したことはありませんが、現実的に難しいですし、求められてもおりません。
冒頭にも記述しましたが「基本的な論理思考」「出題意図のくみ取り」が出来ていればOKです。
論理思考については「言い換え」「対比」「因果関係」という3つの軸をアイディア出しや資料の読み取りで発揮することが求められます。
特に「対比」を使って考えることは、強く求められます。後に紹介する「ふくしま式」のロジカルシンキングを実践できるようにトレーニングしていきましょう。もう一つの重要な考え方が「出題意図のくみ取り」です。最も誤解が多い論点がここです。設問の指示として「自由に書きなさい」「あなたの考えを整理しなさい」記載があっても、それは半分は本音、半分建前です。本当に自由に考えて良いのであればどの作文も「内容」面では満点評価となるはずでしょう。しかし、実際は異なります。その理由は「出題意図のくみ取り」が出来ているかどうかを試されているのです。出題者がどういったことを意図して問題を作っているかを分析し、求められている内容を書き上げるその過程で自分の独自性を少しブレンドするというイメージです。あくまで「基本的な文章」を書けるかどうかを試されているので、「内容」については既定路線に従う必要があります。既定路線に従いつつ、自分の体験談といった独自性を織り交ぜればOKです。



こちらの記事で合格点をとれる内容の仕上げ方について徹底解説しております。
~おすすめテキストまとめ~
勉強法全体のチューニングを行う
中高一貫校の受検対策は、作文だけではありませんので、全体最適が大切になります。こちらのテキストで学習戦略全体のチューニングを行いましょう!
作文の練習におすすめのテキストはこちら!
作文試験では、作文の問題以上に「添削」が大切になります。最短の学習ルートは、「銀本」×「添削」のかけあわせになります。
銀本がおすすめの理由
- 100校以上の実際の過去問で演習ができる
- 難易度が簡単な問題から難しい問題がそろっており、初心者から受検生まで幅広いレベルに対応可能
作文は問題以上に添削が大事
作文対策で、「いきなり過去問をやって大丈夫?」と思われた方もいるかと思います。
結論、「大丈夫」です。作文対策は、問題そのもの以上に「添削」が重要です。銀本を一人で取り組むのではなく、添削込みで取り組むのが最短の勉強法になります。銀本には、全国100校以上の中高一貫校の問題が掲載されています。難易度が簡単な過去問もあれば、難しい過去問もあります。通常のテキストを買って、簡単な問題からレベルアップしていくのと同様の演習を積むことができます。



私の添削塾では、10回程度で合格レベルまで到達できるように問題を選んで添削メニューを作っています。
「受検まで時間がある」という方はこちら!
現在、小学六年生で「受検まで」一年を切っているという方は、「過去問演習×添削」で学習をすすめていくのがおすすめです。一方で、小学校五年生以下の場合は、受検まで余裕があります。いきなり作文に挑むのではなく、「論理的思考」をトレーニングしていきましょう。
ロジカルシンキングを鍛えるためのおすすめテキストはこちら
- ロジカルシンキングの基本である「言い換え」「対比」「因果関係」を学ぶことができる
- 作文の課題文整理&論理構成に必要な基本をマスターできる
公立中高一貫校作文試験で求められる「表現力」を鍛えるにあたっては、ふくしま式の「一文力」がおすすめです。は、ロジカルシンキングを徹底した文章力を養成できます。
ふくしま式の「一文力」がおすすめな理由
- 文章全体を論理的に仕上げる素地を鍛えられる
- 論理的な短文を書き上げるところからステップバイステップでトレーニングできる
一般的な作文の作法を学ぶためには、「公立中高一貫校対策 作文問題 書き方編」でトレーニングしていきましょう。ふくしま式の一文力は、短文に特化しています。こちらのテキストは、より公立中高一貫校の作文試験を意識した内容になっています。原稿用紙の使い方や文法上の留意事項など、試験で求められる知識は一通り習得可能です。
「細かいミスをなくしたい!」場合はサブテキストで補おう
「文章の作法が身につかなくて、所々減点される・・・」原稿用紙の使い方や文法のミス、誤字脱字など、が直らない場合、このテキストがおすすめです。小学校低学年の子にも分かるようにイラスト付きで解説されているので、作文が苦手な受検生におすすめです。
「字が汚くて減点される・・・」というお悩みも良く頂きます。丁寧に書くという意味では、意識の程度の問題という風にまとめてしまうこともできるのですが、長年の指導の経験から字が汚いという小学生は、そもそも「綺麗な字」の書き方を知らないことが多いです。マス目のバランス感覚や綺麗な字の特徴などを知識として知っておくことで、「綺麗な字がそもそも分からない」という状態から抜け出せます。習字なども「綺麗な字とはそもそもこれ!」という具合に情報としてインプットするところから始まりますからね。こちらのテキストで綺麗な字の特徴を着実におさえていきましょう。
テキストを与えるだけはNG!
「できたつもり」にならず何度も復習する
受検勉強の過程で最も恐れるべき敵は「できたつもり」です。本番では短時間で知識や技術を自由自在に発揮する必要があります。このレベル二到達するためには、「何となく知っている」「テキストを読めば思い出せる」「ゆっくりやれば解ける」という油断を徹底的に排除していかねばなりません。みな取り組んでいる問題集は同じです。しかし結果は大きく異なります。丁寧に、かつ粘り強く自分の知識と技術の定着を図った受検生に勝利の女神は微笑むのです。


塾や家庭教師をうまく利用する
公立中高一貫校の作文試験では、塾や家庭教師をうまく使いましょう。作文の書き方や誤字脱字といった採点要素は、属人性が低く、大人であれば誰でも採点可能です。しかし、「どの程度の内容であれば合格可能か」といった要素は、プロに添削をお願いするとよいでしょう。
全国の中高一貫校の作文試験に対応した専門の作文添削塾はこちら
私は、中高一貫校専門の作文添削塾を運営しております。気になる方はチェックしてみてください。
- 電話相談無料
- 初回割引添削あり
- 学習プランも無料で設計
しております。オンライン添削なので、場所時間関係なく、全国どなたでも対応可能です。
公立中高一貫校の作文過去問データ(すべての学校の問題を一覧化しています)
東京都公立中高一貫校の作文過去問模範解答データ(各学校各年度の作文模範解答を無料公開しています)