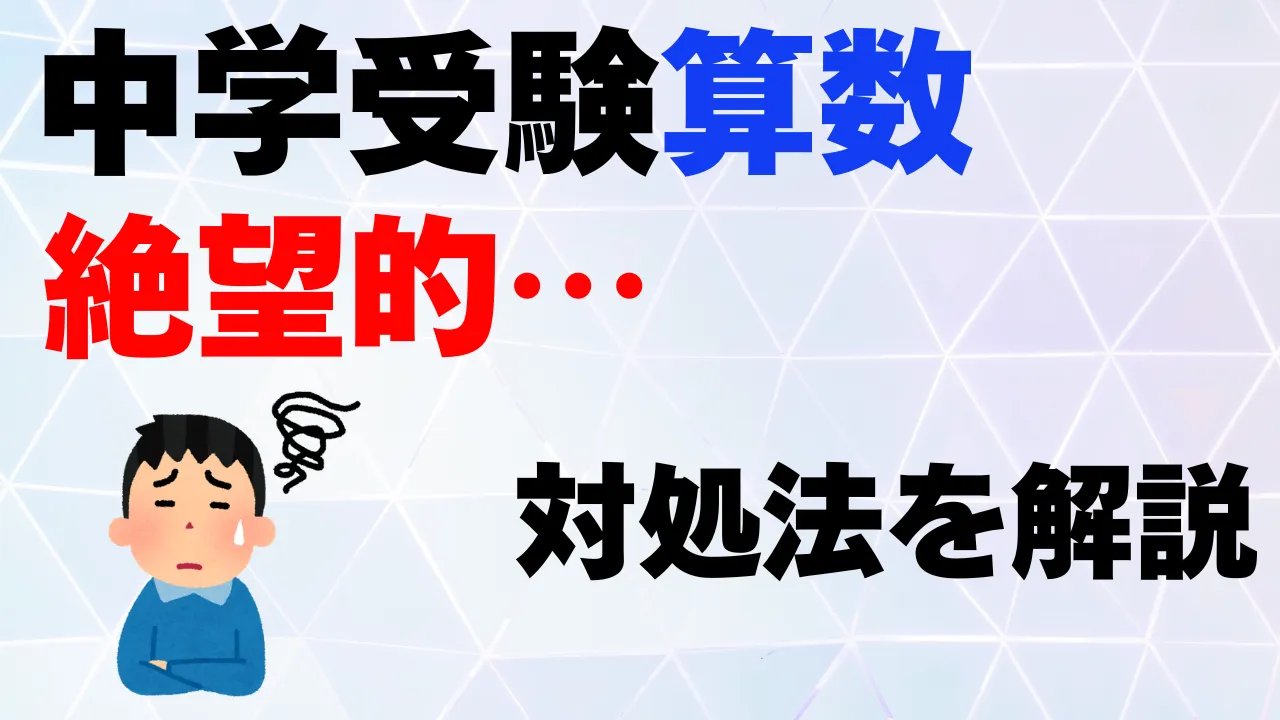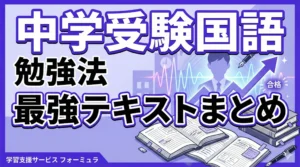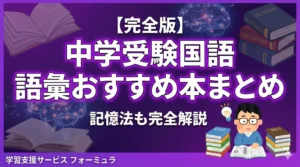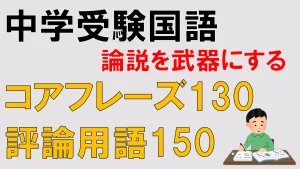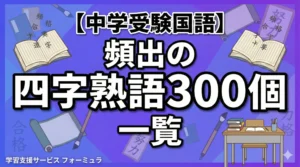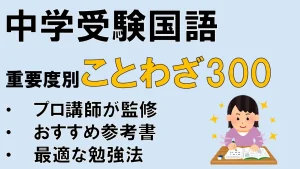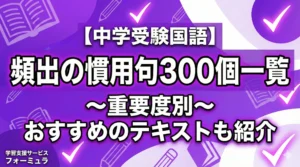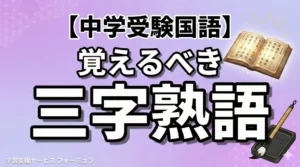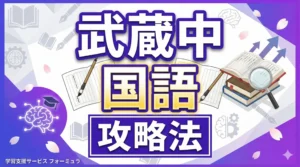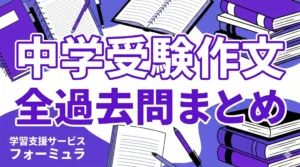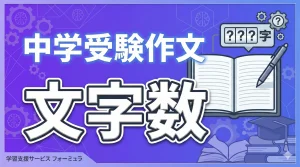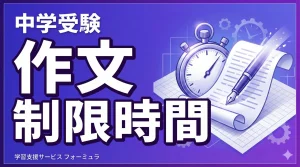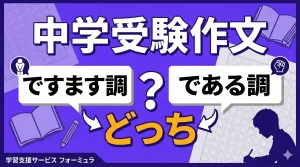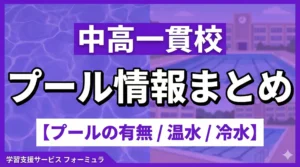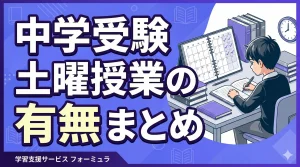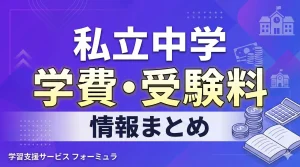この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
「算数の点数がまったく上がらない…」「問題の解き方を教えても次の日には忘れている…」 中学受験の算数に頭を抱える保護者の方は多いのではないでしょうか。何をしても成績が伸びず、対策法がわからないと悩まれていることでしょう。
しかし、絶望的に見える状況でも諦める必要はありません。算数が苦手な子どもの多くは基礎固めが不十分なだけで、適切な対策を講じれば成績向上は可能です。
私は2013年から10年以上中学受験指導に携わり、600人以上の受験生を指導してきました。その経験から、算数苦手克服の効果的な方法を確立しています。
この記事では、算数が苦手な原因と具体的解決策、短期間で基礎力を上げる学習法、親ができるサポート方法、単元別のおすすめテキストを解説します。
ここで紹介する対策を実践すれば、「何から手をつければいいのか」という不安から解放され、お子さんの算数力向上に確かな道筋が見えるでしょう。「難しいことをやる」のではなく「基本的なことを確実に」やることが、算数逆転の鍵なのです。
この記事でわかること
- 算数が「絶望的」に見える根本原因と_具体的な解決策
- 短期間で算数の基礎力を上げる効果的な学習法と、親ができるサポート方法
中学受験で算数が絶望的に見える原因

算数が絶望的に見える原因まとめ
- 算数ができない原因は、大きく分けて「概念理解」「計算力」「図式化能力」「時間管理」の4つに分類できる
- 多くの保護者が「うちの子は難しい問題が解けない」と悩む一方で、基本的な計算ミスや文章題の読解ミスが実は大きな原因になっている
- 算数が「絶望的」と感じる子どもの90%以上は、実は基礎固めが不十分なだけで、適切な対策を取ればかなりの確率で成績を向上させることができる
- 「難しいことをやる」のではなく、「基本的なことを確実に」やる
算数の成績が伸び悩む原因は子どもによって様々ですが、多くの場合いくつかの典型的なパターンに分類できます。原因を正確に把握することで、効果的な対策を講じることができます。まずは、なぜお子さんの算数が「絶望的」に見えるのか、その根本原因を探りましょう。
【算数が苦手な理由①】「基礎固め」の定義を誤解している
「基礎をしっかり固めましょう」とよく言われますが、この「基礎」の定義を誤解している場合が多いです。基礎固めとは単に簡単な問題を解くことではなく、算数の概念を正確に理解し、自在に活用できるレベルまで到達することを意味します。
例えば、割合の単元を例にとると、「割合=部分÷全体」という公式を覚えるだけでは不十分です。「AはBの何%」「AをB%増やすと」「AをB%引くと」などの表現を見たとき、即座に式に変換できるようになるまで練習する必要があります。
 塾長 神泉
塾長 神泉この「真の基礎固め」ができていないケースが非常に多く見られます。
【算数が苦手な理由②】計算力の不足が全ての根本原因
多くの保護者が見落としがちなのが、基本的な計算力の重要性です。計算に時間がかかりすぎる、ケアレスミスが多いなどの問題は、他の全ての学習を阻害する根本的な原因となります。
計算に自信がないと、複雑な問題に取り組む際に「この計算、合ってるかな?」と不安になり、思考が中断されます。また、計算に時間をとられすぎて問題を解き切れないこともあります。小学4年生の段階で四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)が迅速・正確にできることは、その後の算数学習の土台となります。
【算数が苦手な理由③】文章題の図式化ができていない
文章題を解く際、問題文から必要な情報を抽出し、図や表に整理する「図式化」の能力は非常に重要です。文章題を図式化できない子どもは、いくら計算力があっても問題を正しく解くことができません。
例えば「AさんとBさんが反対方向から歩き始め…」という問題を見たとき、自動的に数直線を描いて状況を整理できる子どもと、文章をただ眺めて何をしていいかわからない子どもとでは、解答への道筋が大きく異なります。



図式化能力は訓練によって身につけることができる技術ですが、多くの受験生はその方法を知らないままでいます。
【算数が苦手な理由④】問題の読解力が追いついていない
算数の問題を解く上で、問題文を正確に理解する読解力は欠かせません。「問われていることは何か」「与えられている条件は何か」を正確に把握できないと、いくら計算が得意でも正解にたどり着けません。
特に中学受験の算数では、複雑な条件が含まれる長文問題が多く出題されます。これらの問題では、文章を読み解く力と数学的な思考力の両方が試されます。国語の読解力に比べ、算数特有の「数量関係を読み取る力」が不足している受験生は少なくありません。
【算数が苦手な理由⑤】単元間のつながりが理解できていない
算数の各単元は互いに密接に関連していますが、多くの子どもはそのつながりを理解できていません。各単元を独立した「島」として捉えるのではなく、関連性を理解することで応用問題に対応する力が身につきます。
例えば、「割合」と「比」は本質的に同じ概念ですが、別々に学習することでつながりを見失い、応用問題で活用できないケースがあります。同様に、「面積」と「体積」の関係、「速さ」と「割合」の共通点など、単元間の横断的理解が不足していると、複合問題に対応できなくなります。
【算数が苦手な理由⑥】時間配分の誤りによる悪循環
テストや模試での時間配分の誤りも、成績不振の大きな原因です。難問に時間をかけすぎて基本問題を解く時間が足りなくなり、得点できるはずの問題で点を落とす悪循環に陥っている子どもが多くいます。
特に、計算に時間がかかる子どもは、全体の解答時間の大半を基本的な計算に費やしてしまい、肝心の思考力を問う問題に手が回らないことがあります。また、問題の難易度を見極める力がないと、解けない問題に固執して時間を無駄にしてしまいます。これらの時間配分の問題は、適切な訓練で改善することができます。
算数の基礎力を短期間で上げる具体策


算数の基礎力を短期間で向上させるためには、効率的かつ効果的なアプローチが必要です。ここでは、すぐに実践できる具体的な方法を紹介します。これらの方法は、限られた時間の中で最大限の効果を発揮します。
算数の基礎力を上げる6つの方法まとめ
- 毎日10分間の計算ドリルで計算スピードと正確性を向上させる
- 基本問題を繰り返し解き、完全に理解して定着させる
- すべての文章題で図や表を使って整理する習慣をつける
- よく出題されるパターンを認識し、解法を身につける
- 類題演習で理解度を確認し、応用力を高める
- 間違えた問題を記録・分析する「エラーノート」を作成する
まずは計算スピードを上げる訓練
算数の成績向上において、計算スピードの向上は最も即効性のある対策です。毎日10分間の計算ドリルを継続することで、1〜2ヶ月という短期間で計算スピードと正確性を劇的に向上させることが可能です。
具体的には、以下のトレーニング方法が効果的です。
- 時間を計りながら計算ドリルに挑戦する
- 前回より速く解けることを目標にする
- 間違えた問題は必ず復習する
- 四則演算だけでなく、分数・小数の計算も含める
計算力向上のコツは「量」と「速さ」です。短時間で多くの問題を解く訓練を続けることで、自然と計算の正確性とスピードが身につきます。スマホのタイマー機能を使って「3分間でどれだけ解けるか」という目標を立てると、子どもも挑戦しやすくなります。
基本問題を徹底的に反復する
どれだけ複雑な応用問題も、基本問題の組み合わせで成り立っています。基本問題を徹底的に反復し、解法を完全に理解して定着させることが、応用問題を解くための最短ルートです。
効果的な基本問題の反復学習法は以下の通りです。
- 各単元の基本パターンを3〜5題選ぶ
- 同じ問題を3日連続で解く
- 完全に定着するまで、1週間後、1ヶ月後にも再度解く
- 解き方を声に出して説明できるようにする
基本問題の反復では、単に答えを出すだけでなく、「なぜそういう解き方をするのか」という理解を深めることが重要です。お子さんに解法を説明してもらう時間を作ると、理解度を確認できると同時に、説明することで知識が定着します。
図や表で整理する習慣をつける
文章題を解く際の最大のコツは、問題の状況を図や表に整理することです。すべての文章題で図式化する習慣をつけることで、問題の構造を把握する力が飛躍的に向上します。
図式化の訓練には以下の方法が効果的です。
- どんな簡単な問題でも必ず図や表を書く
- 問題を読みながら、出てくる数字や関係性をメモする
- 特に「速さ」「割合」「場合の数」の問題では必ず図式化する
- 図を描いた後、何を求めるべきかを明確にする
慣れないうちは時間がかかりますが、継続することで自然と図式化のスピードが上がります。また、図式化することで問題の見落としが減り、間違いも少なくなります。最初は親が一緒に取り組み、徐々に子ども自身ができるように促すとよいでしょう。
パターン認識力を鍛える方法
中学受験の算数には、繰り返し出題されるパターンがあります。これらのパターンを認識し、解法を知っておくことで、見たことのない問題でも対応できる力がつきます。
パターン認識力を鍛えるためには
- 過去問や問題集を「型」に注目して分類する
- 同じパターンの問題をまとめて解く
- 「この問題はあのパターンだ」と認識する習慣をつける
- パターンごとに解法を暗記する
例えば、「植木算」「旅人算」「通過算」などの速さの問題や、「食塩水」「混み具合」などの割合の問題は、それぞれ特有のパターンがあります。これらのパターンを意識的に学ぶことで、問題を見た瞬間に「この解き方だ」と判断できるようになります。
類題演習で定着を確かめる
基本問題が理解できたら、次は少し形を変えた類題に取り組むことで定着度を確認します。類題演習は、単なる暗記ではなく、応用力を試すために重要なステップです。
効果的な類題演習の進め方は
- 基本問題を完全に理解する
- 数値や条件が少し変わった類題に挑戦する
- つまずいたら基本に戻り、違いを確認する
- 徐々に難易度を上げていく
類題演習でつまずいた場合は、基本問題と何が違うのか、どこで混乱したのかを分析することが大切です。つまずきの原因が明確になれば、そこを重点的に復習することで効率よく学習を進められます。
間違えた問題を活用する方法
間違えた問題は、実は最高の学習教材です。間違いから学ぶことで、同じミスを繰り返さない力が身につきます。間違えた問題を活用する「エラーノート」の作成が非常に効果的です。
エラーノートの作り方と活用法
- 間違えた問題とその解答を記録する
- なぜ間違えたのかを分析して書き添える
- 正しい解き方を詳細に記録する
- 定期的にエラーノートを見直し、同じミスを防ぐ
特に重要なのは「なぜ間違えたのか」の分析です。計算ミスなのか、問題の読み間違いなのか、解法の誤りなのかを明確にすることで、効果的な対策ができます。エラーノートは受験直前期の総復習にも非常に役立ちます。
算数が苦手な子の親がすべきサポート


算数が苦手なお子さんを持つ親として、どのようにサポートすればよいのでしょうか。適切なサポートがあれば、お子さんの成績は必ず向上します。ここでは、家庭でできる効果的なサポート方法を紹介します。
子どもの「できない理由」を冷静に分析
お子さんが算数ができない理由を感情的にならずに分析することが重要です。「やる気がない」「頭が悪い」という短絡的な判断ではなく、具体的なつまずきのポイントを特定することが、効果的なサポートの第一歩です。以下の5つの観点でお子様の算数について分析してください。
- 基本的な計算は正確かつ素早くできるか
- 文章題を正確に読み取れているか
- 図や表を使って問題を整理できるか
- 基本的な概念(分数、割合など)を理解しているか
- 時間配分は適切か
例えば、お子さんが文章題で間違えるパターンを観察し、「速さの単位変換がわかっていない」「割合の問題で全体と部分を混同している」といった具体的な原因を突き止めることで、ピンポイントな対策が可能になります。
家庭での勉強環境の整え方
集中して学習できる環境づくりは、効率的な学習のために不可欠です。静かで整理整頓された学習スペースと、規則正しい学習時間の確保が、算数の成績向上に大きく貢献します。学習環境については以下の5つを守りましょう。
- 集中できる静かなスペースを確保する
- 学習に必要な道具(筆記用具、ノート、教材)を整理する
- スマホやゲームなどの誘惑を排除する
- 適切な照明と室温を維持する
- 毎日同じ時間に学習する習慣をつける
また、物理的な環境だけでなく、精神的な環境も重要です。プレッシャーをかけすぎず、かといって放任しすぎず、適度な緊張感のある家庭の雰囲気を作ることが大切です。親が「算数は難しい」という態度を見せると、子どもにもその感覚が伝わるため注意が必要です。
学習スケジュールの立て方
限られた時間を効率的に使うためには、計画的な学習スケジュールが欠かせません。長期的な計画と日々の具体的なスケジュールの両方を、お子さんの特性に合わせて立てることが効果的です。以下の5つの観点で学習スケジュールを立ててください。
- 受験までの長期計画をカレンダーに落とし込む
- 1週間単位の学習計画を立てる
- 得意科目と苦手科目のバランスを考慮する
- 1日の学習時間を細かく区切り、メリハリをつける
- 復習の時間を必ず確保する
特に算数の学習では、新しい内容を学ぶ時間と基礎的な計算練習の時間をバランスよく配分することが重要です。また、塾での学習内容を家庭で確実に定着させるための復習時間を確保することも忘れないでください。
子どものモチベーション維持法
算数が苦手な子どもは、しばしばモチベーションの低下に悩まされます。小さな成功体験を積み重ね、達成感を味わわせることが、モチベーション維持の鍵です。
- 難易度を適切に設定し、達成感を味わわせる
- 小さな進歩を見逃さず、具体的に褒める
- 競争ではなく、自分との比較を重視する
- 学習の成果を可視化する(グラフ化など)
- 適度な休息と楽しみを取り入れる
特に効果的なのは、「できるようになった」という実感を持たせることです。例えば、「先週はこの問題が解けなかったけど、今日は解けたね」と具体的な成長を示すことで、お子さんの自信につながります。
NGな言葉かけとよい言葉かけ
親の言葉かけは、子どものやる気と自信に大きく影響します。否定的な言葉は子どもの意欲を削ぎ、肯定的で具体的な言葉かけは学習意欲を高めます。
NGな言葉かけ例
- 「どうしてこんな簡単な問題ができないの?」
- 「いつまでたっても上達しないね」
- 「○○君はできているのに」
よい言葉かけ例
- 「この部分はよく理解できているね」
- 「前回よりも計算のスピードが上がっているよ」
- 「難しい問題に挑戦する姿勢がすばらしい」
ポイントは、結果だけでなく過程も評価すること、他の子と比較せず個人の成長に注目すること、そして具体的に褒めることです。「頑張れ」という抽象的な言葉より「この単元をマスターしよう」という具体的な目標設定の方が効果的です。
親自身のメンタル管理の重要性
中学受験は子どもだけでなく親にとってもストレスの多いプロセスです。親自身のメンタルが安定していることが、子どもを効果的にサポートするための前提条件です。
- 完璧を求めすぎない
- 長期的な視点で成長を見守る
- 同じ立場の親と情報交換し、悩みを共有する
- 子どもの受験と自分の人生を分けて考える
- 適度なリフレッシュの時間を確保する
特に注意したいのは、親の不安やイライラが子どもに伝わることです。親が焦れば子どもも焦り、冷静な判断ができなくなります。「今はうまくいかなくても、適切な努力を続ければ必ず伸びる」という信念を持ち、穏やかな気持ちでサポートすることが大切です。



算数が苦手な子どもの場合、基礎力の向上には時間がかかります。1週間や2週間で劇的な変化を期待するのではなく、1ヶ月、3ヶ月という単位で成長を見守ることが大切です。
【中学受験算数】ジャンル別おすすめテキスト


算数の成績を効果的に向上させるには、適切な学習法と教材選びが重要です。ここでは、単元別のアプローチ方法や各種教材の特徴、効果的な活用法などを紹介します。
計算力トレーニングのおすすめ教材
計算力向上には、目的に合った教材選びと効果的な活用が欠かせません。スピードと正確性を同時に鍛えられる教材を選び、継続的に取り組むことが計算力向上の鍵です。
計算力トレーニングのおすすめ教材まとめ
図形問題攻略のおすすめ教材
図形問題は多くの子どもが苦手とする分野ですが、適切なアプローチと教材で効率的に攻略できます。実際に図を描き、操作することを通じて図形感覚を養うことが重要です。
図形問題トレーニングのおすすめ教材まとめ
- Amazonレビュー
- このテキストを習熟すると、図形のパターンは、このくらいで対応出来ることがわかる
- 中堅から難関と呼ばれている学校で出題されている問題も対応できる
文章題攻略のおすすめ教材
文章題を解くためには、問題文を正確に理解し、適切な解法を選ぶ思考力が必要です。問題文の読み解き方と情報の整理法を学ぶことで、文章題への苦手意識を克服できます。
図形問題トレーニングのおすすめ教材まとめ
- Amazonレビュー
- 文章問題の解き方を体系的にトレーニングできます
文章題を解くためのステップ:
- 問題を読み、何を求めるのかを明確にする
- 与えられた条件を図や表に整理する
- 必要な式を立てる
- 計算し、答えを導く
- 答えの妥当性を確認する
文章題用の教材を選ぶ際は、解説が詳しく、図式化の方法も示されているものが望ましいです。また、同じパターンの問題が複数収録されている教材を選ぶと、パターン認識力が鍛えられます。文章題の学習では、解答を見る前に自分で考える時間を十分に取ることが大切です。
一行問題のおすすめ教材
一行問題がしっかり解ける受験生なら、「この二つの解き方を組み合わせれば解けるぞ」などと解法が思いつきやすくなりますし、計算が速くて正確なのでミスも少なくなるのです。
一行問題のおすすめ教材
- Amazonレビュー
- 合計1000問の一行問題が掲載されている
- 一行問題は比較的、高い配点なので、偏差値アップにも効果的
- 一行問題をひたすらやることで基礎力も向上する



難しすぎる教材は挫折感を生み、簡単すぎる教材は成長につながりません。理想的なのは、8割程度の問題が自力で解ける難易度の教材です。
算数の苦手意識を克服するメンタルケア


算数への苦手意識は、実力以上に成績を下げる要因になります。ここでは、算数に対するネガティブな感情を克服し、前向きな気持ちで学習に取り組むためのメンタルケア方法を紹介します。
算数の苦手意識を克服する5つのメンタルケアまとめ
- 「算数ができない」という固定観念から「練習中」という成長志向への転換
- 適切な難易度の課題に取り組み、小さな成功体験を積み重ねる
- 具体的で達成可能な目標設定で持続的なモチベーションを維持する
- 得意教科での学習スキルや自信を算数学習にも応用する
- 深呼吸やイメージトレーニングで緊張を緩和し、集中力を高める
「できない自分」から抜け出す方法
多くの子どもが「算数ができない」という自己イメージに縛られています。この固定的な思考から「まだできるようになっていない」という成長思考への転換が、算数の成績向上への第一歩です。
自己イメージを変えるための具体的な方法
- 「私は算数が苦手」ではなく「今は練習中」と言い換える
- 小さな成功体験を積み重ね、自信を構築する
- 「できない」部分よりも「できる」部分に注目する
- 失敗を学びの機会と捉える姿勢を身につける
特に重要なのは、算数の能力は生まれつきのものではなく、訓練によって伸ばせるという「成長マインドセット」を養うことです。親が「私も算数は苦手だったの」というような言葉を避け、「練習すれば必ずできるようになる」というメッセージを伝え続けることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねる
自信を構築するには、成功体験の積み重ねが不可欠です。適切な難易度の課題に取り組み、少しずつ成功体験を重ねることで、算数への自信と前向きな姿勢が育まれます。
効果的な成功体験の作り方
- 確実に解ける問題から始める
- 少しずつ難易度を上げていく
- 成功したら具体的に褒める
- 成長の記録を視覚化する(グラフや記録ノードなど)
ポイントは、子ども自身が「できた!」と実感できる体験を意図的に作ることです。例えば、計算問題なら最初は5問、次は10問と徐々に量を増やしたり、時間を計って「前回より速く解けた」という成功体験を積み重ねたりすることが効果的です。
リラックス法と集中力アップの技術
緊張やストレスは、算数の実力発揮を妨げる大きな要因です。効果的なリラックス法と集中力を高める技術を身につけることで、学習効率と本番での実力発揮力が向上します。
リラックスと集中力アップのテクニック
- 深呼吸:4秒かけて息を吸い、6秒かけて吐く
- 目標の可視化:テスト前に成功している自分をイメージする
- 適度な休憩:25分勉強したら5分休憩する「ポモドーロ・テクニック」
- 体を動かす:短時間の運動で脳の血流を改善する
特にテスト前の緊張緩和には、「今自分にできる最善を尽くす」という考え方が効果的です。完璧を求めるのではなく、「今の自分にできることをやる」という心構えが、余計な不安やプレッシャーを軽減します。また、睡眠や食事などの基本的な生活習慣の管理も、集中力維持には欠かせません。
まとめ


中学受験で算数が「絶望的」に見える原因は「概念理解」「計算力」「図式化能力」「時間管理」の4つに分類されます。多くの場合、基礎固めが不十分なだけで、適切な対策で成績向上は可能です。
基礎力向上のための具体策として、①毎日10分間の計算ドリル、②基本問題の徹底反復、③文章題の図表整理習慣、④パターン認識力強化、⑤類題演習、⑥「エラーノート」活用を推奨します。
親のサポートとしては、子どもの「できない理由」を冷静に分析し、適切な学習環境とスケジュールを整え、肯定的な言葉かけでモチベーションを維持しましょう。
算数苦手克服のメンタルケアとして、「できない」という固定観念から「練習中」という成長思考への転換、小さな成功体験の積み重ね、リラックス法と集中力アップの技術習得が効果的です。正しい教材選びと継続的な取り組みで、算数の成績は向上します。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
有名中学校国語過去問に関する記事一覧
公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧
中高一貫校のデータに関する記事一覧
中学受験の算数が「絶望的」に見える根本原因は何ですか?
主な原因は「基礎固め」の定義の誤解、計算力の不足、文章題の図式化能力の欠如、問題読解力の不足、単元間のつながりが理解できていないこと、時間配分の誤りなどがあります。特に多くの場合、基本的な計算ミスや文章題の読解ミスが大きな原因となっています。適切な対策を講じれば、成績向上が期待できます。
算数の基礎力を短期間で向上させるための具体的な方法は何ですか?
毎日10分間の計算ドリルで計算スピードと正確性を向上させる、基本問題を繰り返し解いて完全に理解する、文章題では必ず図や表を使って整理する習慣をつける、よく出題されるパターンを認識して解法を身につける、類題演習で理解度を確認する、間違えた問題を記録・分析する「エラーノート」を作成するなどの方法が効果的です。
算数が苦手な子どもの親としてどのようなサポートが効果的ですか?
子どもの「できない理由」を冷静に分析する、集中できる学習環境を整える、長期的・短期的な学習スケジュールを立てる、小さな成功体験を積み重ねてモチベーションを維持する、否定的な言葉かけを避け肯定的で具体的な言葉かけをする、親自身のメンタル管理を大切にするなどが効果的です。特に結果だけでなく過程も評価し、個人の成長に注目することが重要です。
算数の苦手意識を克服するためのメンタルケア方法にはどのようなものがありますか?
「算数ができない」という固定観念から「練習中」という成長志向へ転換する、適切な難易度の課題に取り組み小さな成功体験を積み重ねる、具体的で達成可能な目標設定でモチベーションを維持する、得意教科での学習スキルを算数学習に応用する、深呼吸やイメージトレーニングで緊張を緩和し集中力を高めるなどの方法があります。
受験直前期にやるべきことと避けるべきことは何ですか?
やるべきことは、過去問を時間を計って解く、間違えやすい問題タイプを重点的に復習する、計算スピードの最終調整をする、時間配分の訓練を繰り返すことです。避けるべきことは、新しい単元や難しい分野に手を出す、解けない問題に固執する、模試の結果に一喜一憂する、睡眠時間を削って勉強することです。「得点できる問題で確実に点を取る」という意識が重要です。