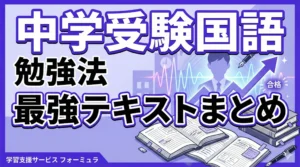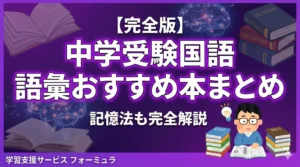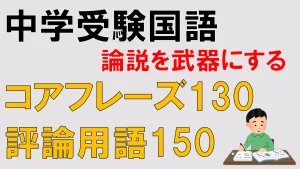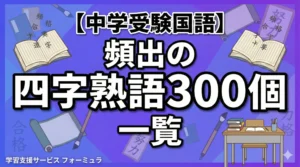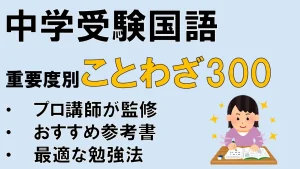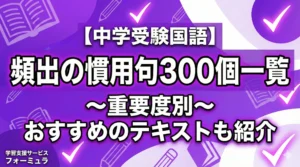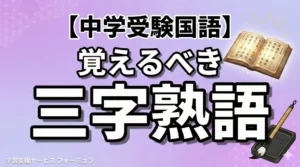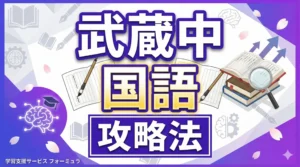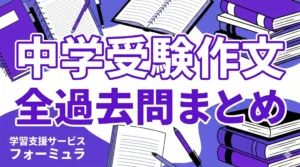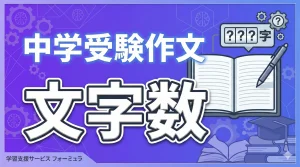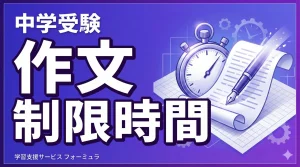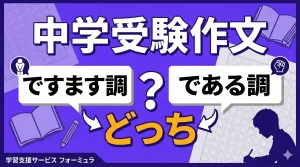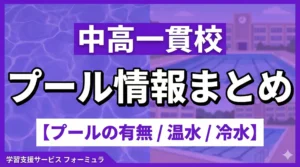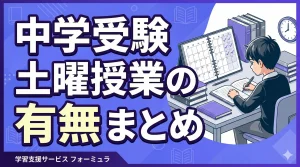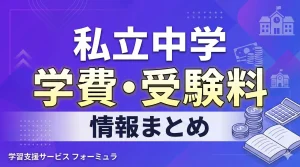この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
渋幕の国語はどのように対策すべき?プロ講師が傾向と対策を解説
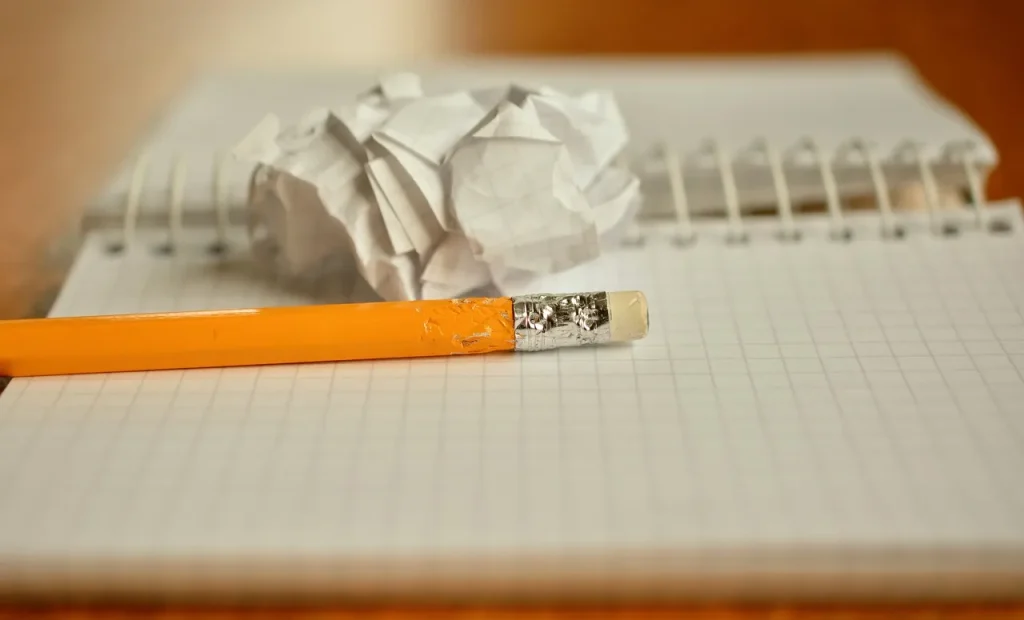
渋谷教育学園幕張中学校(以下、渋幕)の入試において、国語は合否を左右する重要な科目です。特に、その難易度の高さと独特な出題傾向から、適切な対策をせずに臨むと高得点を狙うことは困難でしょう。渋幕の国語で合格点を勝ち取るためには、一般的な中学受験対策だけでは不十分であり、より高度な読解力と知識が求められます。 本記事では、渋幕の国語の傾向と具体的な対策方法について、プロの視点から詳しく解説していきます。
渋幕の国語特徴
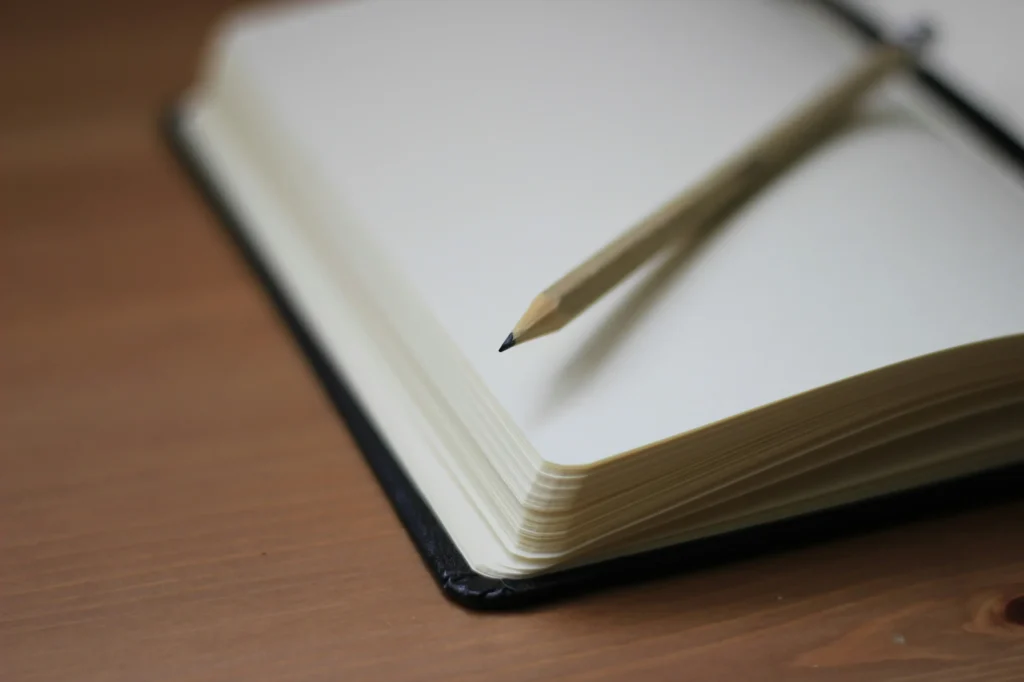
高校現代文レベルの難易度の文章が出題される
渋幕の国語では、高校現代文レベルの文章が出題されることが大きな特徴です。 抽象度の高い論説文や、心情描写が複雑な文学作品が頻繁に登場します。これらの文章は、一般的な中学受験対策で用いられる教材ではあまり見られないテーマや語彙を含んでいます。日頃から様々なジャンルの文章に触れ、未知の言葉や概念に対しても臆することなく読み進める訓練が必要になります。
特に小説は特徴的で高尚な文学作品が出題される傾向にある
渋幕の国語における小説の出題は、その選定に特徴があります。一般的な中学受験でよく見られる児童文学や、分かりやすい筋書きの作品とは異なり、高尚な文学作品や、人間の内面を深く掘り下げたテーマの作品が出題される傾向が強いです。 例えば、芥川龍之介や太宰治といった近代文学の大家の作品から出題されることも少なくありません。これらの作品は、登場人物の心理が複雑に描かれていたり、社会背景や思想が深く関わっていたりするため、読解には高い国語力と教養が求められます。単に物語の流れを追うだけでなく、作者の意図や登場人物の心情の機微を読み取る力が合否を分けます。
漢字や語彙関連の問題は中学受験の難易度を大きく逸脱することはない
漢字や語彙に関する問題は、他の難関中学と比べても極端に難しいというわけではありません。漢字の書き取り問題は小学校学習指導要領の範囲内から出題されることが多く、日頃の学習でしっかりと基礎を固めていれば対応できるでしょう。一方で、漢字の読み問題については、小学校指導要領外からの出題も見られます。しかし、これは日常生活で新聞や書籍などを通じて文章に触れる機会が多いお子様であれば、自然と読めるようになる程度の難易度です。漢字や語彙力を高めるためには、単語帳を丸暗記するよりも、文章読解の中で出会った言葉の意味や使い方をその都度確認し、知識を定着させる学習方法が効果的です。
文学作品に関する知識問題の出題がある
渋幕の国語では、文学作品そのものに関する知識を問われる問題が出題されることがあります。これは、特定の作家や作品のタイトル、登場人物、あるいは作品が書かれた時代背景などについて問われるものです。一般的な読解力だけでは対応できないため、事前に文学史に関する基礎的な知識を身につけておく必要があります。過去には芥川龍之介の作品に関連する知識問題が出題されたこともあり、中学受験の国語としては珍しい傾向と言えるでしょう。 対策としては、主要な文学作品や著名な作家について、ある程度の知識を習得しておくことが有効です。
【渋幕国語】基本の対策まとめ(論説と小説共通の対策)

わからない言葉を一日最低10回は辞書で探すクセをつける
語彙力は国語の読解において不可欠な要素です。特に渋幕の国語では、高校レベルの文章が出題されるため、日頃から未知の言葉に触れる機会が多くなります。わからない言葉に出会ったら、その都度辞書で意味を調べる習慣をつけることが重要です。 一日に最低10回は辞書を引くという具体的な目標を設定することで、語彙の定着を促すことができます。単に意味を調べるだけでなく、例文や類義語、対義語なども確認することで、より深い理解に繋がり、表現力も向上するでしょう。
出会った漢字は辞書やテキストでその都度意味や読みを調べる
漢字は、文章を正確に読み解く上で非常に重要な要素です。渋幕の国語では、小学校指導要領外の漢字の読みも出題される可能性があるため、日頃から漢字学習を怠らないようにしましょう。問題演習や読書中に知らない漢字や読み方が曖昧な漢字に出会ったら、その場で辞書やテキストで意味と読みを確認する習慣をつけることが大切です。 調べた漢字は、ノートにまとめるなどして、定期的に復習することで知識の定着を図ります。漢字の知識が増えることで、文章全体の理解度も向上し、読解のスピードアップにも繋がります。
小学校指導要領の漢字はひらがなで書かないようにする
小学校学習指導要領で定められている漢字は、日常生活はもちろんのこと、中学受験においても正確に使いこなすことが求められます。特に文章を書く際には、小学校指導要領内で習う漢字をひらがなで書く癖がついていると、本番の記述問題で減点対象となる可能性があります。 日頃から漢字を使って書くことを意識させ、正確な漢字の知識を身につけさせましょう。保護者の方も、お子様が書いた文章をチェックする際に、適切な漢字が使われているかを確認し、必要に応じて指導することが重要です。
言い換え・対比・因果関係を構造的に見抜く能力を磨く
文章読解において、筆者の主張を正確に理解するためには、論理的なつながりを捉える能力が不可欠です。「言い換え」「対比」「因果関係」といった論理構造を瞬時に見抜く力が求められます。 例えば、「AはBである、つまりCである」といった言い換えの関係、「AではなくBである」といった対比の関係、「AだからBである」といった因果関係などです。これらの関係性を意識して文章を読む訓練を積むことで、筆者の論理展開を構造的に理解できるようになり、設問の意図を正確に把握する力が向上します。
文章の全体整理をすることを日ごろから行う
複雑な文章や長文を読解する際には、文章全体を構造的に捉える能力が非常に重要です。日頃から文章を読む際に、筆者の主張、具体例、結論などを意識しながら、文章全体の構成を整理する訓練を行いましょう。 例えば、段落ごとに要点をまとめる、キーワードを抽出する、文章の構造を図式化するといった方法が有効です。これにより、文章の全体像を把握しやすくなり、設問に対する解答の根拠を見つけやすくなります。また、記述問題においては、文章全体を理解した上で要約する力が求められるため、この訓練は非常に役立ちます。
選択肢問題・記述問題の解き方を学び、その解法を使って普段の演習を行う
渋幕の国語では、選択肢問題と記述問題がバランス良く出題されます。それぞれの問題形式には、効率的かつ正確に解答するための「解き方」が存在します。例えば、選択肢問題では、誤りの選択肢がなぜ誤っているのかを明確にする訓練、記述問題では、設問の意図を正確に読み取り、限られた字数の中で必要な要素を盛り込む訓練が必要です。 解き方を学んだら、それを普段の演習で意識的に適用することで、本番での得点力向上に繋がります。漫然と問題を解くだけでなく、解法のプロセスを意識して取り組むことが重要です。
選択肢問題は正解の選択肢、誤りの選択肢ともに理由を明確に答える訓練をする
選択肢問題では、単に正解を選ぶだけでなく、なぜその選択肢が正解なのか、そしてなぜ他の選択肢が誤りなのかを明確に説明できる力が求められます。特に誤りの選択肢については、その誤りの根拠を本文中から探し出し、論理的に説明する訓練を積むことが重要です。 この訓練を通じて、文章の深い理解と、選択肢を吟味する力が養われます。また、曖昧な理解で正解を選んでしまうことを防ぎ、確実な得点に繋げることができるでしょう。
記述問題は文字数の多寡に合わせて記述量を調整して答える訓練を積む
記述問題では、限られた文字数の中で、設問の要求事項を的確に盛り込み、論理的に記述する力が求められます。渋幕の記述問題は、文字数指定が多様であり、短いものから長いものまで様々です。日頃から、設問の文字数に応じて、どの程度の情報を盛り込むべきか、どの程度具体的に記述すべきかを調整する訓練を積むことが重要です。
 塾長 神泉
塾長 神泉例えば、40字であれば要点を簡潔に、100字であれば具体例を交えながら説明するなど、文字数感覚を養うことで、本番で慌てずに対応できるようになります。
【渋幕国語】論理的文章の対策まとめ


日ごろの問題演習で出会った文章のテーマ理解を深める(国語の勉強というよりは教養を深める意識で様々な方面から知識や情報を収集する)
渋幕の論理的文章では、多岐にわたるテーマから出題されます。哲学、科学、社会問題、芸術など、中学受験ではあまり触れないような専門的な内容も含まれることがあります。単に文章の内容を理解するだけでなく、そのテーマに対する背景知識や教養を深めることが、より深い読解に繋がります。 問題演習で出会ったテーマについては、関連する書籍を読んだり、インターネットで調べたりして、多角的に情報を収集する習慣をつけさせましょう。これは国語の勉強という枠を超え、お子様の知的好奇心を刺激し、将来にわたる学習の基盤を築くことにも繋がります。
論説文のテーマ学習ができるテキストで頻出のテーマは事前に理解しておく
渋幕の論理的文章では、特定のテーマが繰り返し出題される傾向があります。例えば、「情報化社会」「グローバル化」「AIと人間」といったテーマは、現代社会において頻繁に議論されるものです。これらの頻出テーマについては、事前に専門のテキストを用いて学習し、基本的な知識や概念を理解しておくことが非常に有効です。 可能であれば、高校現代文の論説文対策で用いられるような、より専門性の高いテキストにも目を通し、幅広い知識を身につけることをお勧めします。テーマに関する知識があれば、文章の理解度が格段に向上し、速読力も高まるでしょう。
筆者の論理関係を、構造的に図式化して読み解く
論理的文章を正確に理解するためには、筆者の主張とそれを支える論理の流れを構造的に把握する能力が不可欠です。文章を読む際に、筆者の主張、根拠、具体例、結論などを意識しながら、それらの関係性を図や線で結ぶなどして可視化する訓練を積むと良いでしょう。 例えば、筆者の主張をA、その理由をB、具体例をCとして、A←B←Cのように関係性を図で示すことで、文章全体の論理構造が一目でわかるようになります。この訓練により、複雑な論理展開も整理して理解できるようになり、設問に対する的確な解答に繋がります。
テーマ理解と論理構造把握が瞬時にできるように習熟度を高めていく
渋幕の国語は、制限時間内に難解な文章を読み解き、正確に解答する力が求められます。そのためには、論理的文章の「テーマ理解」と「論理構造把握」を瞬時に行うことができるレベルまで習熟度を高める必要があります。 日頃の演習では、時間を意識しながら、文章全体のテーマや筆者の主張、論理展開を素早く捉える訓練を繰り返しましょう。最初は時間がかかっても、継続することで徐々にスピードが向上し、本番で余裕を持って問題に取り組めるようになります。
【渋幕国語】文学的文章の対策まとめ


日ごろの問題演習で出会った文章のテーマや心理描写、時代背景などを調べる
渋幕の文学的文章は、高尚な作品が多く、そのテーマや登場人物の心理描写、作品が書かれた時代背景などが複雑に絡み合っています。単に物語を追うだけでなく、作品が持つ深いテーマや、登場人物の心情の機微、さらにはその作品が生まれた社会や歴史的背景にも目を向けることが重要です。 問題演習で出会った作品については、作者や時代背景、作品の解釈などをインターネットや関連書籍で調べるなど、国語の勉強という枠を超えて教養を深める意識で情報を収集しましょう。これにより、作品への理解度が深まり、より的確な心情把握やテーマ理解に繋がります。
芥川龍之介をはじめとした短編文学作品を一週間に一つ読み、テーマや時代背景について調べる
渋幕の国語では、特に近代文学の作品が出題される傾向があります。芥川龍之介の作品は、その代表例であり、登場人物の心理描写が深く、示唆に富んだ内容が多いです。 対策として、一週間に一つ、芥川龍之介などの著名な作家の短編文学作品を読み、その作品のテーマや時代背景、作者の意図などについて調べることをお勧めします。これにより、文学作品の読解に慣れるだけでなく、文学史的な知識や教養も自然と身につけることができます。読んだ作品について親子で話し合うのも良いでしょう。



芥川作品は基本的に短編でテーマが明確なので比較的読みやすいです。また、芥川作品は、渋幕の文学史問題でも繰り返し出題されています。
日ごろの小説の演習では、時間制限を厳しく設けて、時間がない中で文章を読み解く訓練をする
渋幕の国語は、制限時間内に多くの文章を読み解かなければならないため、速読力と正確な読解力が求められます。特に小説の読解においては、物語の流れや登場人物の心情を素早く掴むことが重要です。 日頃の演習では、時間制限を厳しく設けて、時間がない中で文章を読み解く訓練を積むことをお勧めします。これにより、本番での時間配分感覚が養われ、焦らずに問題に取り組めるようになります。また、速く読むだけでなく、内容を正確に理解する質も意識して取り組むことが大切です。
フェリス女学院中学校の国語の過去問を使って文学作品の読解に慣れる
渋幕と傾向が似ている学校の過去問を解くことは、効果的な対策の一つです。フェリス女学院中学校の国語は、渋幕と同様に文学的文章の出題が多く、心情把握やテーマ理解を問う問題が特徴的です。 フェリス女学院の過去問を解くことで、渋幕の文学的文章の読解に必要な力を総合的に養うことができます。特に、高尚な文学作品の読解に慣れるためには、非常に有効な演習となるでしょう。単に問題を解くだけでなく、解説を熟読し、なぜその解答になるのかを深く理解するよう努めることが重要です。
代表的な文学作品の作者やテーマを理解しておく
渋幕の国語では、特定の文学作品に関する知識問題が出題されることがあります。これは、読解力とは別に、文学作品そのものについての知識が問われることを意味します。対策として、日本文学史における代表的な文学作品とその作者、そして作品の主要なテーマについて、基本的な知識を身につけておくことが重要です。 例えば、夏目漱石や森鴎外、川端康成など、中学受験レベルでも触れる可能性のある作家や作品について、概要を把握しておくと良いでしょう。これにより、知識問題に加えて、文学作品の読解の際に、より深い理解に繋がることもあります。
渋幕に受かる子の特徴は?


なんでも自分で調べる習慣がある
渋幕に合格するお子様は、単に与えられた課題をこなすだけでなく、自ら疑問を持ち、それを解決するために積極的に調べる習慣を持っています。 例えば、知らない言葉に出会ったらすぐに辞書を引く、興味を持ったテーマがあれば関連書籍やインターネットでさらに深く調べるなど、知的好奇心に基づいて行動します。この「自分で調べる」という能動的な学習姿勢は、高度な読解力と幅広い知識を身につける上で不可欠であり、渋幕が求める自律的な学習者像と合致します。
仮説を設けて改善を繰り返す習慣がある
渋幕に合格するお子様は、問題解決において、「仮説を立てて検証し、改善を繰り返す」という思考プロセスを自然と実践しています。 例えば、記述問題でうまく解答できなかった場合、なぜできなかったのか、どうすればより良い解答が書けるのかを分析し、次の演習に活かします。これは、単に正解を覚えるだけでなく、問題の本質を理解し、より効率的な学習方法を見つける力に繋がります。このような試行錯誤の経験が、難解な問題にも粘り強く取り組む力を育みます。
論理的に考える力がある
渋幕の入試問題、特に国語では、論理的な思考力が問われる問題が多く出題されます。合格するお子様は、物事を感情的に捉えるのではなく、筋道を立てて論理的に考える力に長けています。 例えば、文章の主張と根拠を明確に区別したり、複雑な因果関係を整理したりすることができます。日頃から、なぜそうなるのか、その根拠は何か、という問いを立てながら学習することで、論理的思考力を養うことができます。これは、国語だけでなく、他の教科の学習においても非常に重要な能力と言えるでしょう。
渋幕国語対策使えるおすすめテキストまとめ



ここからは、渋幕国語専用のおすすめテキストをまとめてご紹介します。漢字や語彙、基本的な読解テクニックを鍛える一般的な国語対策のおすすめテキストは、「【完全版】中学受験国語〜合格までの勉強法と最強テキストまとめ〜」で紹介しています。
論理的文章を攻略するテキスト
合格する国語の授業 説明文・論説文 得点アップよく出るテーマ編
評論文キーワード 頻出270語
文学的文章を攻略するテキスト
合格する国語の授業 物語文 得点アップよく出る感情語&パターン編
小学生なら知っておきたい教養366
フェリス女学院中学校 過去問(最新版)
出題文一覧
令和03年度(2021年度)第一回試験
大問1論説「具象以前(湯川秀樹)」
大問2小説「極楽(菊池寛)」
令和03年度(2021年度)第二回試験
大問1論説「人生は苦である、でも死んではいけない(岸見一郎)」
大問2小説「薔薇盗人(上林暁)」
令和02年度(2020年度)第一回試験
大問1論説「山本七平-空気の研究(大澤真幸)」
大問2小説「豊穣の海(三島由紀夫)」
令和02年度(2020年度)第二回試験
大問1論説「科学と非科学 その正体を探る(中屋敷均)」
大問2小説「ネッシーはいることにする(長薗安浩)」
令和01年度(2019年度)第一回試験
大問1論説「天災と国防(寺田寅彦)」
大問2小説「おらおらでひとりいぐも(若竹千佐子)」
令和01年度(2019年度)第二回試験
大問1論説「原っぱと遊園地(青木敦)」
大問2小説「Masato(岩城けい)」
平成30年度(2018年度)第一回試験
大問1論説「養老孟司の幸福論(養老孟司)」
大問2小説「死後(芥川龍之介)」
平成30年度(2018年度)第二回試験
大問1論説「街場の共同体論(内田樹)」
大問2小説「犀鳥(遠藤周作)」
出題された知識問題一覧
令和03年度(2021年度)第一回試験
漢字書き:画期的 収める
漢字読み:費やす(ツイヤス)
令和03年度(2021年度)第二回試験
漢字書き:真に受ける 進展 自己 内在
漢字読み:殊に(コトニ) 強ち(アナガチ) 提げる(サゲル)
令和02年度(2020年度)第一回試験
漢字書き:採用 有無を言わせぬ
漢字読み:戒める(イマシメル) 権化(ゴンゲ) 興じて(キョウジテ) 火照る(ホテル)
令和02年度(2020年度)第二回試験
漢字書き:考案 安易 相場 日除け 劇的
漢字読み:秘匿(ヒトク)
令和01年度(2019年度)第一回試験
書き:宣伝 月謝 冷蔵庫
読み:稀有(ケウ) 怠る(オコタル) 独楽(ドクラク)
令和01年度(2019年度)第二回試験
書き:分化 配置 検証 運営 窓際 一目置く
読み:縁(フチ)
平成30年度(2018年度)第一回試験
書き:操縦 阻む 寸断
読み:床(トコ) 卑しい(イヤシイ) 露(ツユ)
平成30年度(2018年度)第二回試験
書き:希釈 縮減 再稼働 面倒 湖水
読み:度々(タビタビ)
まとめ


渋幕の国語は、中学受験の中でも特に難易度が高く、一般的な対策だけでは合格は難しいです。高校現代文レベルの文章読解力、高尚な文学作品への理解、そして論理的な思考力が求められます。 しかし、適切な対策と日々の継続的な学習によって、十分攻略可能な科目です。本記事で紹介した対策方法を参考に、お子様に合った学習計画を立て、着実に実践していくことが重要です。
渋幕の国語はなぜ難しいと言われているのですか?
渋幕の国語は、高校現代文レベルの抽象度の高い論説文や、心情描写が複雑な高尚な文学作品が出題されるため、一般的な中学受験対策だけでは対応が難しいからです。読解力だけでなく、深い教養も求められます。
渋幕の国語で高得点を取るために、特にどのような対策が必要ですか?
未知の言葉を辞書で調べる習慣をつけ、漢字学習も徹底することが重要です。また、文章の言い換え・対比・因果関係を構造的に見抜く力や、文章全体を整理する能力を磨くことが求められます。
渋幕の国語の記述問題対策で重要なことは何ですか?
記述問題は配点が大きく合否を分けるため、早期からの対策が不可欠です。設問の意図を正確に読み取り、限られた文字数で論理的に記述する練習を積むこと、また、文字数に合わせて記述量を調整する訓練が重要です。
渋幕の国語の文学史対策はどの程度行うべきですか?
文学史に関する知識問題は出題されますが、配点は3~5点と低めです。代表的な文学作品の作者やテーマを理解する程度に留め、文学史に時間をかけすぎないよう、記述問題の対策に注力することをおすすめします。
渋幕に合格するお子様にはどのような共通点がありますか?
渋幕に合格するお子様は、なんでも自分で調べる習慣があり、仮説を立てて改善を繰り返す思考力、そして物事を感情的にではなく論理的に考える力を持っています。自律的な学習姿勢が特徴です。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ