中学受験の面接対策本のおすすめは?

この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
面接対策のコツと合わせて徹底解説
中学受験において、学力試験の準備に多くの時間を費やしますが、面接対策も合否を左右する重要な要素です。近年、面接を課す学校が増加傾向にあり、単に知識を問うだけでなく、受験生の人柄や潜在能力、学校への適応性などを総合的に評価する場となっています。面接は、お子様が学校の教育方針や校風にどれだけ合致しているかを示す絶好の機会であり、また、お子様の個性や魅力を直接アピールできる貴重な場でもあります。面接対策を怠ると、せっかくの学力が評価されない可能性もあるため、早期からの準備が不可欠です。このセクションでは、面接の基本的な考え方から、効果的な対策のコツまでを詳しく解説していきます。
対策にかけられる時間別にやるべきことも紹介します
中学受験の面接対策は、お子様やご家庭の状況によってかけられる時間が異なります。例えば、受験直前で時間がない場合と、数ヶ月前から余裕を持って準備できる場合とでは、取るべきアプローチが変わってきます。時間が限られている場合は、頻出の質問への回答を簡潔にまとめるなど、効率を重視した対策が必要です。一方、時間がある場合は、模擬面接を繰り返し行い、応答力や表現力を高めるなど、より深く踏み込んだ準備が可能です。お子様の性格や面接への慣れ具合も考慮し、最適な対策プランを立てることが重要です。このセクションでは、対策にかけられる時間別に、具体的に何をすべきか、どのような点に重点を置くべきかを詳細に解説し、効果的な学習計画をサポートします。
中学受験の面接では何を見られている?

自然なコミュニケーションができるかどうか
中学受験の面接において、面接官が最も重視する点の一つは、お子様が自然なコミュニケーションを取れるかどうかです。事前に準備された完璧な模範解答を話すことよりも、面接官の質問意図を正確に理解し、自分の言葉で適切に返答できるかどうかが評価の対象となります。不自然な暗記や棒読みの受け答えは、お子様の個性や人間性を伝える妨げになる可能性があります。面接官は、お子様が緊張しながらも、相手の目を見て、はっきりと自分の意見を述べられるか、また、質問に対して柔軟に対応できるかを見ています。日頃から家族や友人との会話を通じて、自分の考えを言葉にする練習を積むことが、自然なコミュニケーション能力を養う上で非常に重要です。
校風や文化とミスマッチがないか
学校の面接では、お子様がその学校の校風や文化に適合しているかどうかが厳しく見られます。各学校には独自の教育理念や特色があり、面接官は、お子様の性格や価値観が、学校が求める生徒像と合致しているかを確認したいと考えています。
例えば、自由な校風の学校であれば自主性や探究心、伝統を重んじる学校であれば規律や協調性が重視される傾向があります。学校のウェブサイトやパンフレット、説明会などを通じて、事前にしっかりと情報収集を行い、お子様のどのような点がその学校の魅力や教育方針に貢献できるかを具体的にアピールできるように準備することが重要です。ミスマッチがあると判断されれば、学力が高くても不合格となる可能性もあります。
課題に対して事前準備がしっかりとできているか
中学受験の面接では、与えられた課題に対して、お子様がどれだけ真剣に事前準備をして臨んでいるかが見られています。これは、単に質問への回答を暗記しているかどうかだけでなく、面接という場に対するお子様の姿勢や責任感を測る指標でもあります。例えば、学校への志望理由や自己PRなど、事前に考えておくべき質問に対して、どれだけ具体的に、そして論理的に自分の言葉で表現できるかが問われます。また、面接中に想定外の質問が出た場合でも、慌てずに落ち着いて考える時間をもらったり、誠実に「わかりません」と伝えたりする対応も、準備の証と見なされることがあります。十分な準備は、お子様の自信にも繋がり、面接全体を通して落ち着いた態度で臨むことができるでしょう。
アピールポイントを間違えると逆効果になってしまうのが面接の怖いところ

中学受験の面接では、お子様のアピールポイントを適切に伝えることが非常に重要ですが、そのアピール方法を誤ると逆効果になることがあります。
例えば、過度な自己主張や自慢話は、協調性がないと受け取られたり、傲慢な印象を与えてしまったりする可能性があります。また、お子様らしからぬ大人びた言葉遣いや、丸暗記したような模範解答は、お子様の個性を覆い隠し、不自然な印象を与えることもあります。面接官は、お子様の真の姿や潜在能力を見極めようとしています。そのため、背伸びをしたり、偽ったりするのではなく、お子様のありのままの魅力や長所を、具体的なエピソードを交えながら、正直に、そして謙虚な姿勢で伝えることが大切です。アピールポイントを明確にしつつも、相手に良い印象を与える表現方法を練習しておくことが成功の鍵となります。
 塾長 神泉
塾長 神泉基本的なことをおろそかにして、崇高な受け答えや理想的な回答を目指すご家庭がありますが、対策としてはズレていると言わざるを得ません。あくまで基本的なことに意識をむけましょう。
受験面接でよくある誤解


事前に準備したことをすべて話さなければいけないと思っている
中学受験の面接において、多くの受験生や保護者が抱きがちな誤解の一つに、「事前に準備したことをすべて話さなければならない」という考えがあります。しかし、これは大きな間違いであり、台本を読み上げるような受け答えは、面接官に不自然な印象を与え、お子様の個性や人間性を伝える妨げになってしまいます。面接は、あくまで面接官とのコミュニケーションの場であり、一方的に話す場ではありません。質問の意図を正確に理解し、それに対して適切に、そして自分の言葉で答えることが求められます。準備した内容に固執しすぎると、質問のニュアンスを読み違えたり、話が長くなりすぎたりする可能性もあります。準備はあくまで自信を持って臨むための土台であり、本番では柔軟に対応する姿勢が重要です。
面接では聞かれたことにすべて答えられなければならないと思っている
中学受験の面接でよくある誤解の一つに、「面接官の質問にはすべて完璧に答えなければならない」という思い込みがあります。しかし、すべての質問に完璧に答えることよりも、正直で誠実な姿勢を見せることの方がはるかに重要です。もし、お子様が質問の内容を理解できなかったり、答えに詰まってしまったりした場合は、無理にでたらめな回答をするよりも、「少し考える時間をいただいてもよろしいでしょうか」と伝えたり、「すみません、今の質問の意味がよくわかりません」と正直に伝えたりする方が、むしろ良い印象を与えることがあります。大切なのは、質問に対するお子様の思考プロセスや、困難な状況にどう向き合うかという人間性です。わからないことを素直に認める勇気も、面接では評価されるポイントとなります。
立派な回答をしなければならないと思っている
中学受験の面接において、「立派な回答をしなければならない」と思い込むことは、よくある誤解の一つです。しかし、面接官が求めているのは、大人顔負けの完璧な模範解答ではなく、小学生らしい素直な気持ちや、お子様自身の言葉で語られる個性です。
例えば、将来の夢について質問された際に、壮大な社会貢献のビジョンを語るよりも、「〇〇の仕事に興味があって、そのために今、××を頑張っています」といった具体的な体験に基づいた話の方が、お子様の興味や意欲が伝わりやすく、好印象を与えることがあります。背伸びをして難しい言葉を使ったり、本心ではないことを言ったりするのではなく、ありのままのお子様の考えや気持ちを、わかりやすい言葉で伝えることが大切です。
自分の本音をすべて話してOKと思っている
中学受験の面接において、「自分の本音をすべて話してしまっても大丈夫だ」と考えてしまうのは、よくある誤解の一つです。面接はあくまで合否を判断する場であり、お子様の正直な気持ちを全てぶつける場所ではありません。
例えば、学校への不満や、特定の教師に対する個人的な意見など、面接官が聞きたい内容とはかけ離れた本音を話してしまうと、マイナス評価に繋がる可能性があります。大切なのは、学校への敬意を示しつつ、お子様自身の良い面や、学校で学びたいという意欲を伝えることです。時には、伝え方によっては誤解を招く可能性のある本音は、別の表現に置き換えたり、敢えて話さなかったりする選択も必要になります。面接の場にふさわしい内容と表現を選ぶことが重要です。
面接に準備をして臨むのはズルいことと思っている
中学受験の面接において、「面接に準備をして臨むのはずるいことだ」という誤解を抱く方がいます。しかし、これは大きな間違いであり、面接前の準備は、お子様の意欲や真剣さを示す重要なプロセスです。むしろ、何の準備もせずにぶっつけ本番で臨むことの方が、学校への敬意が欠けていると見なされる可能性があります。面接準備は、お子様自身の考えを整理し、伝えたいことを明確にするための大切な時間です。模擬面接を通じて、受け答えの練習をしたり、自身の考えを深めたりすることは、お子様が自信を持って本番に臨むための土台となります。適切な準備をすることは、お子様の実力を最大限に発揮し、面接官に良い印象を与えるための不可欠な要素であると理解しましょう。



自分の素を評価され面接を突破できる人は、大人含めてほとんどいません。社会的な立ち振る舞いや受け答えをできるようにすることは事前の対策として当然のことです。
受験面接で好評価を獲得するポイント


面接官との受け答えができているかを最重視する
中学受験の面接で好評価を獲得するためには、面接官との「受け答え」ができているかを最重視することが重要です。これは、面接が一方的に準備した内容を話す場ではなく、面接官との双方向のコミュニケーションの場であることを意味します。面接官が質問の意図を汲み取り、それに対して的確に、そして自分の言葉で答える能力が求められます。例えば、質問されたこととは関係のない、準備した自己紹介を延々と話すような行為は、コミュニケーション能力が低いと判断される可能性があります。面接官の目を見て、相槌を打ちながら話を聞き、質問の意図を正確に捉え、簡潔かつ明確に返答することで、良好なコミュニケーションが築け、お子様の真の魅力が伝わるでしょう。
「知らない・わからない」質問に対しては、素直にそう答えるか考える時間が欲しいと伝えるようにする
中学受験の面接において、知らない質問や答えに詰まる質問が出た場合、焦って適当なことを言ってしまうのは避けるべきです。好評価を獲得するポイントは、「知らない・わからない」ということを素直に認めたり、「少し考える時間をいただけますか」と伝えたりすることです。これは、お子様の正直さや誠実さを示すだけでなく、困難な状況にどう向き合うかという姿勢を表します。無理に知ったかぶりをしたり、嘘をついたりすると、面接官には見抜かれてしまい、かえってマイナス評価に繋がる可能性があります。わからないことを正直に伝える勇気と、その後の対応が、お子様の人間性を測る上で重要な要素となります。



わからないことをごまかすのはコミュニケーションとしては不適切ですよね。あくまで試されているのはコミュニケーション力です。
学校HPや説明会の内容を入念にチェックしておく
中学受験の面接で好評価を獲得するためには、志望校の学校HPや説明会の内容を入念にチェックし、その情報を自身の言葉で語れるようにしておくことが非常に重要です。面接官は、お子様がどれだけその学校に興味を持ち、深く理解しているかを知りたいと思っています。例えば、「貴校の〇〇という教育理念に共感し、特に説明会で伺った××の取り組みに感銘を受けました」のように、具体的に学校の特徴や魅力を挙げ、それに対するお子様自身の考えや抱負を述べられると、熱意が伝わりやすくなります。単に情報を知っているだけでなく、それがお子様にとってどのような意味を持つのか、どう活かしたいのかを明確にすることが、面接官に響くアピールに繋がります。
受験校の校風や文化とミスマッチがないことを実体験をもとに語れるようにする
中学受験の面接で好評価を得るためには、受験校の校風や文化と、お子様の性格や価値観にミスマッチがないことを実体験をもとに具体的に語れるように準備することが極めて重要です。例えば、自由な校風の学校であれば、お子様が自主的に取り組んだことや、探究心を刺激された経験などを話せるようにします。また、伝統を重んじる学校であれば、協調性や規律を重んじるお子様の姿勢を示すエピソードを準備するなどが考えられます。単に「御校の校風に合っていると思います」と述べるだけでは説得力に欠けます。具体的な経験談を交えることで、お子様の個性がその学校でどのように花開くかを面接官に想像させることができ、入学後の活躍を期待してもらうことに繋がります。
小学生らしい回答を実体験をもとに語れるようにする
中学受験の面接では、背伸びをして大人びた回答をするよりも、小学生らしい素直な視点や感情を実体験に基づいて語れるようにすることが、好評価に繋がるポイントです。例えば、頑張ったことや楽しかったことについて質問された際に、抽象的な表現ではなく、「友達と協力して運動会の練習をした時に、意見がぶつかったけれど、最後はみんなで力を合わせて成功させられたのが一番嬉しかったです」といった具体的なエピソードを交えることで、お子様の個性や成長が伝わりやすくなります。面接官は、お子様のありのままの姿や、日々の生活の中で何を学び、何を感じているのかを知りたいと考えています。無理に難しい言葉を使わず、お子様自身の言葉で、心に残った出来事を話せるように準備しましょう。



異様に大人びた回答は、評価を低くしてしまう可能性が高いです。
事前準備をしっかりし、ぶっつけ本番の状態を避ける
中学受験の面接で好評価を獲得するためには、徹底した事前準備を行い、ぶっつけ本番の状態で臨むことを避けることが非常に重要です。面接は、お子様の人柄や思考力を測る重要な場であり、準備不足は自信のなさや意欲の欠如と見なされてしまう可能性があります。学校の教育理念や校風、カリキュラムについて深く理解し、志望理由や自己PR、長所・短所など、頻出の質問に対する回答を事前に考え、模擬面接を繰り返すことで、本番で落ち着いて、かつ的確に答えることができるようになります。また、面接時の態度や言葉遣い、入退室の仕方なども練習しておくことで、より良い印象を与えることができます。十分な準備は、お子様の自信にも繋がり、面接の成功に大きく貢献するでしょう。
受験面接の事前準備について


10個~20個の質問を事前に用意し模擬面接をする
中学受験の面接対策として、事前に10個から20個程度の質問を用意し、お子様と模擬面接を繰り返すことが非常に効果的です。これにより、様々な質問パターンに対応できる応用力と、自分の言葉で考える力を養うことができます。質問の内容は、志望理由、自己PR、長所・短所といった定番のものから、小学校生活での思い出、最近のニュース、入学後の抱負など、多岐にわたるように工夫しましょう。模擬面接では、単に回答内容をチェックするだけでなく、声の大きさ、視線、姿勢、言葉遣いなど、非言語コミュニケーションの部分も意識して練習することが重要です。繰り返し練習することで、本番での緊張を軽減し、自信を持って臨めるようになるでしょう。
本番の1~2か月前から週1~2回ほどの頻度で準備すればOK
中学受験の面接準備は、本番の1~2か月前から週に1~2回ほどの頻度で取り組むのが効果的です。あまりに早期から詰め込みすぎると、お子様が飽きてしまったり、暗記に偏ってしまったりする可能性があります。また、直前になって慌てて準備するのでは、十分な対策ができません。この期間であれば、お子様の記憶にも残りやすく、かつ、無理なく継続して練習に取り組むことができます。各回の模擬面接で得られたフィードバックを元に、次回の練習で改善点に意識を向けることで、着実にスキルアップを図ることが可能です。無理のないペースで継続的に練習することで、面接本番で最高のパフォーマンスを発揮できる準備が整います。
変に難しい質問をするのではなく、基本的な質問にしっかり答えられるように準備する
中学受験の面接準備においては、変にひねくれたり、難しい質問ばかりを想定するのではなく、まずは基本的な質問にしっかりと答えられるように準備することが最も重要です。面接官は、お子様が学校生活を送る上で必要な基本的なコミュニケーション能力や、思考力を測りたいと考えています。志望理由、自己PR、長所・短所、小学校での思い出、入学後の抱負など、頻出の質問に対する回答を、お子様自身の言葉で具体的に、そして分かりやすく説明できるように練習しましょう。これらの基本的な質問に自信を持って答えられるようになれば、応用的な質問にも落ち着いて対応できる基礎力が養われます。土台を固めることが、面接成功への近道となります。



この記事で紹介している「基本レベル」の質問を繰り返し練習するだけで十分合格可能でしょう。
質問の受け答え以上に、退室の仕方、お辞儀、態度などを練習した方がいい場合もある
中学受験の面接準備において、質問の受け答えにばかり意識が向きがちですが、入退室の仕方、お辞儀、姿勢、視線などの「態度」を練習することも非常に重要です。これらの非言語コミュニケーションは、お子様の印象を大きく左右する要素であり、面接官は質問内容だけでなく、お子様全体の振る舞いから、人間性や礼儀正しさ、真剣さなどを総合的に評価しています。
例えば、ドアの開閉、お辞儀の角度、着席時の姿勢、質問を聞く時の相槌、退室の際の挨拶など、細部にわたる練習をすることで、より洗練された印象を与えることができます。質問の回答が多少詰まっても、堂々とした態度や礼儀正しい振る舞いは、お子様への好意的な評価に繋がる可能性が高いです。



受け答え以上に、ふるまいの練習の方が大変かもしれません…。心配な場合は、長期的にトレーニングしていきましょう。
知人や家庭教師などに依頼して親以外の大人と面接練習する
中学受験の面接準備として、知人や家庭教師など、親以外の大人に依頼して模擬面接を行うことは非常に有効です。普段から接している親御様との練習では、お子様が緊張感を持ちにくかったり、甘えが出てしまったりすることがあります。しかし、親以外の大人を面接官と想定することで、より本番に近い状況で練習することができ、お子様は適度な緊張感を持って臨めます。また、第三者からの客観的なフィードバックは、親御様からは気づきにくいお子様の癖や改善点を発見する良い機会となります。これにより、より実践的な練習を積むことができ、面接本番で落ち着いてパフォーマンスを発揮するための自信を養うことができるでしょう。
基本レベル【中学受験の面接質問集】10選と回答のポイント


基本情報(名前・受験番号・通っている学校)
中学受験の面接で最も基本的な質問は、お子様自身の基本情報に関するものです。
- 「お名前と受験番号を教えてください」
- 「現在通っている小学校はどこですか」
といった内容が問われます。これらの質問は、面接の冒頭で緊張をほぐす目的もありますが、お子様がきちんと指示を理解し、はっきりと答えることができるかを見るためのものです。お子様には、大きな声で、相手の目を見て、はっきりと答えるように練習させましょう。特に受験番号は、緊張で忘れてしまう可能性もあるため、事前にしっかりと頭に入れておくか、すぐに確認できる場所にメモを用意しておくことも有効です。基本的な質問にスムーズに答えることで、面接の出だしを良い印象でスタートさせることができます。
自己PR
中学受験の面接における自己PRは、お子様の個性や長所、そしてそれが学校生活でどのように活かせるかをアピールする重要な機会です。
- 「あなたの良いところを教えてください」
- 「自分はどんな人だと思いますか」
といった質問が想定されます。お子様には、単に長所を羅列するだけでなく、具体的なエピソードを交えながら語るように指導しましょう。
例えば、「私は粘り強く物事に取り組むことができます。先日、算数の難しい問題に直面した時も、すぐに諦めずに何時間も考え続け、最終的に自力で解くことができました。」のように、具体的な経験を通して自分の強みを示すことで、説得力が増します。また、その長所が志望校の教育理念や校風とどのように結びつくかを意識して話すことも有効です。
志望理由
中学受験の面接において、志望理由の質問は合否を左右する重要な要素です。
- 「なぜ本校を志望しましたか」
- 「本校のどこに魅力を感じますか」
といった形で問われます。お子様には、単なる憧れや通学のしやすさといった理由だけでなく、その学校独自の教育内容、校風、特定の活動、先生方の教え方など、具体的な魅力を挙げ、それらが自分自身の学びや成長にどう繋がるのかを具体的に話せるように準備させましょう。
例えば、「貴校の探求学習のプログラムに大変魅力を感じています。私は幼い頃から自然科学に興味があり、貴校の〇〇先生の研究室で、より深く学びたいと考えています」のように、具体的な情報を盛り込むことで、熱意が伝わりやすくなります。
長所・短所
中学受験の面接では、お子様の長所と短所について質問されることがあります。
- 「あなたの長所と短所を教えてください」
といった形で問われます。長所を語る際は、単に羅列するのではなく、具体的なエピソードを交えて、それがどのように発揮されたかを説明しましょう。
例えば、「私の長所は、誰とでもすぐに仲良くなれることです。小学校の遠足で新しい班になった時も、すぐにみんなと打ち解け、協力して活動できました。」のように、具体例を挙げることで説得力が増します。短所については、正直に認めるだけでなく、それを克服するためにどのような努力をしているのか、あるいは今後どのように改善していきたいかを具体的に述べることが重要です。短所を客観的に認識し、前向きに取り組む姿勢を示すことが評価に繋がります。
小学校生活で力をいれていること
中学受験の面接において、「小学校生活で力を入れていることは何ですか」という質問は、お子様の興味関心や自主性、継続力を見るためのものです。勉強以外にも、部活動、委員会活動、習い事、趣味など、お子様が情熱を傾けていることについて具体的に話せるように準備しましょう。単に「サッカーを頑張っています」と答えるだけでなく、「サッカー部でチームのキャプテンとして、仲間と協力することの大切さを学びました」のように、活動を通して何を学び、どのように成長したかを具体的に述べることが重要です。また、その活動が志望校でどのように活かせるか、あるいは入学後も続けたいと考えているかなどを付け加えることで、面接官へのアピール度が高まります。
小学校での委員会活動での役割や活動内容
中学受験の面接では、お子様のリーダーシップや協調性、責任感を見るために、小学校での委員会活動について質問されることがあります。
- 「小学校でどのような委員会活動をしていましたか?」
- 「その中でどのような役割を担い、どのような活動をしましたか?」
といった質問が想定されます。お子様には、所属していた委員会名とその活動内容を具体的に説明させましょう。
さらに、その中で自分がどのような役割を担い、どのような貢献をしたのか、あるいはどのような困難に直面し、それをどう乗り越えたのかを具体的に話せるように準備させることが重要です。
例えば、「図書委員会で本の整理を担当し、みんなが読みやすいように工夫しました」のように、具体的な行動を示すことで、お子様の主体性や責任感が伝わります。
今まで最も悔しいと感じたこと
中学受験の面接で「今まで最も悔しいと感じたことは何ですか」という質問は、お子様が挫折や困難にどのように向き合い、そこから何を学んだかを見るためのものです。単に悔しかった出来事を話すだけでなく、その経験を通してどのように成長したのか、次へとどう活かそうと考えているのかを具体的に述べることが重要です。
例えば、「運動会でリレーの選手に選ばれず悔しかったですが、その悔しさをバネに、毎日自主練習をして次の機会に備えることを決めました」のように、悔しさの感情だけでなく、その後の前向きな行動や学びを伝えることで、お子様の精神的な強さや成長意欲をアピールできます。困難を乗り越える力は、学校生活を送る上で非常に大切な資質であると評価されます。
今まで最もうれしかったこと
中学受験の面接で「今まで最もうれしかったことは何ですか」という質問は、お子様の喜びの源や価値観、感受性を見るためのものです。単に嬉しかった出来事を話すだけでなく、なぜそれが嬉しかったのか、その経験を通して何を感じ、どのような気持ちになったのかを具体的に語れるように準備しましょう。
例えば、「クラスで一番苦手だった算数のテストで、初めて100点を取れた時が一番嬉しかったです。毎日苦手な問題と向き合い、諦めずに頑張ってきて良かったと思いました。」のように、努力が実を結んだ喜びや、周りの人との関わりの中で生まれた感動など、お子様らしいエピソードを話すことで、人間性が伝わります。具体的な感情や学びを交えることで、より印象的な回答となるでしょう。
中学校生活で頑張りたいこと
中学受験の面接で「中学校生活で頑張りたいことは何ですか」という質問は、お子様の学習意欲や、入学後の具体的な目標を見るためのものです。漠然とした回答ではなく、志望校の特色やカリキュラムと結びつけながら、具体的に何を頑張りたいかを話せるように準備しましょう。
例えば、「貴校の理科の実験が充実していると伺ったので、色々な実験に挑戦し、科学の面白さを深く学びたいです」のように、具体的な活動内容や学習分野を挙げることで、お子様の意欲と学校への理解度が伝わります。また、勉強だけでなく、部活動や生徒会活動、ボランティア活動など、多岐にわたる分野で頑張りたいことを話すことで、バランスの取れた人物像をアピールすることも可能です。
中学校生活で心配していること
中学受験の面接で「中学校生活で心配していることは何ですか」という質問は、お子様が自分のことを客観的に見つめ、課題意識を持っているかを見るためのものです。素直に心配事を伝える一方で、それをどう乗り越えていきたいか、あるいはどう工夫していきたいかを具体的に述べることが重要です。
例えば、「新しい環境に慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、積極的に新しい友達を作って、早く学校に馴染めるように努力したいです」のように、心配事を認識しつつも、前向きな姿勢を示すことで、お子様の適応能力や成長意欲をアピールできます。また、学校側が提供しているサポート体制などを事前に調べておき、それを活用したい旨を伝えるのも良いでしょう。



時間がない場合は、この10個のみを対策するだけでも十分効果があるでしょう。
応用レベル【中学受験の面接質問集】13選と回答のポイント


最近の気になるニュースとそれに対する考え
中学受験の面接で「最近の気になるニュースとそれに対する考え」という質問は、お子様の社会への関心や、物事を多角的に捉え、自分の意見を持つ能力を見るためのものです。単にニュースの内容を述べるだけでなく、それに対してお子様がどのように感じ、何を考えたのか、自分にできることは何かといった視点で話せるように準備しましょう。
例えば、「最近、地球温暖化のニュースが気になっています。私たちの生活が環境に与える影響を考え、自分にできることからゴミの分別や節電に取り組みたいです」のように、自分事として捉え、行動に繋げようとする姿勢を示すと良いでしょう。時事問題に対するお子様なりの意見や倫理観をアピールする機会にもなります。
中学校、高校生活を通して何を成し遂げたいのか具体的に
中学受験の面接で「中学校、高校生活を通して何を成し遂げたいのか具体的に」という質問は、お子様の将来への展望や、目標設定能力を見るためのものです。漠然とした夢ではなく、志望校の教育環境や自身の興味・関心と結びつけながら、より具体的な目標を話せるように準備しましょう。
例えば、「貴校の語学教育が充実していると伺っているので、高校卒業までに英語を流暢に話せるようになり、将来は国際的な舞台で活躍できる人になりたいです」のように、具体的なスキルや分野を挙げ、そのためにどのような努力をしたいかを述べると良いでしょう。長期的な視点で目標を持ち、それに向かって努力する意欲を示すことで、面接官に強い印象を与えることができます。
将来の目標
中学受験の面接で「将来の目標」について質問されることは、お子様の夢やキャリアに対する意識、そしてそれを実現するための意欲を見るためのものです。単に職業名を挙げるだけでなく、なぜその職業に興味を持ったのか、どのような人になりたいのか、そのために今から何を頑張りたいのかといった、具体的な理由やビジョンを話せるように準備しましょう。
例えば、「将来は医師になり、困っている人を助けたいです。そのためには、今から理科や算数をしっかり学び、人の命を救うために必要な知識を身につけたいと考えています」のように、夢の背景にある思いや、そこに至るまでの道筋を具体的に語ることで、面接官にお子様の真剣な気持ちが伝わります。
あなたにとって「リーダーシップ」とは何ですか?また、それを発揮した経験はありますか?
中学受験の面接で「あなたにとって『リーダーシップ』とは何ですか?また、それを発揮した経験はありますか?」という質問は、お子様のリーダーとしての資質や、チームの中での役割を理解する能力を見るためのものです。「リーダーシップ」という言葉の定義をお子様なりに考え、それを具体的な経験と結びつけて話せるように準備しましょう。
例えば、「私にとってリーダーシップとは、みんなの意見を聞き、まとめることです。小学校のグループ学習で、意見が分かれた時に、みんなの話を丁寧に聞き、最終的に良い方向に導くことができました」のように、具体的なエピソードを通して、お子様がどのようにリーダーシップを発揮したかを説明することで、説得力が増します。
友達と意見がぶつかったとき、あなたはどう対応しますか?
中学受験の面接で「友達と意見がぶつかったとき、あなたはどう対応しますか?」という質問は、お子様の協調性や、問題解決能力、コミュニケーションスキルを見るためのものです。単に「話し合います」と答えるだけでなく、具体的な状況を想定し、どのように歩み寄ろうとするのか、どのように相手の意見を尊重するのかといったプロセスを話せるように準備しましょう。
例えば、「まずはお互いの意見をしっかり聞き、なぜそう考えるのかを理解しようとします。そして、共通の目標を達成するために、お互いが納得できる compromise(妥協点)を見つけられるように話し合います」のように、具体的な行動を示すことで、お子様のコミュニケーション能力や、課題解決への前向きな姿勢をアピールできます。
苦手なことにどう向き合っていますか?実際の例を教えてください。
中学受験の面接で「苦手なことにどう向き合っていますか?実際の例を教えてください。」という質問は、お子様の課題克服能力や、自己分析力、そして努力する姿勢を見るためのものです。単に苦手なことを挙げるだけでなく、それに対してどのように考え、どのような努力をしてきたのかを具体的に話せるように準備しましょう。
例えば、「私は計算が苦手でしたが、毎日寝る前に10分間、計算ドリルを解く練習を続けました。最初は大変でしたが、少しずつ速く正確にできるようになり、今では苦手意識がなくなりました」のように、具体的な行動とその結果を述べることで、お子様の粘り強さや成長意欲が伝わります。苦手なことを克服しようとする前向きな姿勢を示すことが重要です。
あなたがこれまでに読んだ本の中で、最も心に残っているものとその理由を教えてください。
中学受験の面接で「あなたがこれまでに読んだ本の中で、最も心に残っているものとその理由を教えてください。」という質問は、お子様の読書習慣や、思考力、感受性を見るためのものです。単に本のタイトルを挙げるだけでなく、なぜその本が心に残ったのか、どんな点が印象的だったのか、その本から何を学んだのかといったことを具体的に話せるように準備しましょう。
例えば、「宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』が心に残っています。主人公のジョバンニとカムパネルラの友情や、生きることの意味について考えさせられ、何度も読み返しました」のように、本のテーマやお子様自身の感想を交えながら語ることで、読書から得た学びや感性が伝わります。
自分とは違う考えの人とどのように関わっていきたいですか?
中学受験の面接で「自分とは違う考えの人とどのように関わっていきたいですか?」という質問は、お子様の多様性への理解や、協調性、コミュニケーション能力を見るためのものです。単に「話し合います」と答えるだけでなく、異なる意見を持つ相手を尊重し、どのように関係を築いていきたいかを具体的に話せるように準備しましょう。
例えば、「自分とは違う考えの人と出会うことは、新しい発見に繋がり、自分の視野を広げる良い機会だと考えています。相手の意見を頭ごなしに否定せず、まずはしっかりと耳を傾け、お互いの考えを理解し合えるように努力したいです」のように、具体的な姿勢を示すことで、お子様の柔軟性や、他者との良好な関係構築への意欲をアピールできます。
これまでの人生で一番大切な決断は何でしたか?理由も教えてください。
中学受験の面接で「これまでの人生で一番大切な決断は何でしたか?理由も教えてください。」という質問は、お子様の意思決定能力や、価値観、そしてその決断から何を学んだかを見るためのものです。お子様にとって「大切」と感じた決断であれば、どんな小さなことであっても構いません。
例えば、「習い事を始めるかやめるか悩んだ時、最終的に自分で決めて継続することを選んだことです。なぜなら、その決断を通して、自分で決めたことには責任を持って取り組むことの大切さを学んだからです」のように、決断に至るまでのプロセスや、その後の学びを具体的に話せるように準備しましょう。お子様自身の成長に繋がったエピソードを語ることで、自己肯定感や自主性をアピールできます。
社会の課題の中で、あなたが特に関心を持っていることは何ですか?
中学受験の面接で「社会の課題の中で、あなたが特に関心を持っていることは何ですか?」という質問は、お子様の社会への関心や、問題意識、そしてそれに対するお子様なりの考えを見るためのものです。具体的な社会問題を一つ選び、なぜその問題に関心があるのか、その問題に対して自分には何ができると考えているのかを話せるように準備しましょう。
例えば、「私は環境問題に関心があります。特に、私たちの出すゴミが海を汚染しているというニュースを見て、日常生活でゴミを減らす工夫をしたり、リサイクルに協力したりすることの大切さを実感しました」のように、具体的な問題に対するお子様自身の考察や、行動への意識を伝えることで、社会貢献への意欲や、主体的な思考力をアピールできます。
あなたの家族の中で尊敬している人とその理由を教えてください。
中学受験の面接で「あなたの家族の中で尊敬している人とその理由を教えてください。」という質問は、お子様の人間関係や、価値観、そして他者を尊重する気持ちを見るためのものです。単に「お父さん」や「お母さん」と答えるだけでなく、具体的にどのような行動や考え方を尊敬しているのか、その理由をエピソードを交えて話せるように準備しましょう。
例えば、「私は母を尊敬しています。いつも笑顔で、どんなに大変な時でも家族のために頑張っている姿を見て、私も人のために努力できる人になりたいと思っています」のように、具体的な行動から感じた尊敬の念を伝えることで、お子様の感受性や、家族への感謝の気持ちが伝わります。
もし1日だけ大人になれるとしたら、何をしてみたいですか?
中学受験の面接で「もし1日だけ大人になれるとしたら、何をしてみたいですか?」という質問は、お子様の想像力や、将来への夢、そして大人に対するイメージを見るためのものです。現実離れした内容ではなく、お子様らしい純粋な発想と、それがなぜしてみたいのかという理由を具体的に話せるように準備しましょう。
例えば、「もし1日だけ大人になれるとしたら、世界中の誰もが困らないような発明をしてみたいです。特に、病気で苦しんでいる人を助ける薬を作りたいと考えています」のように、お子様らしい夢や、社会貢献への意識を伝えることで、面接官に良い印象を与えることができます。
自分の性格や考え方を一言で表すとしたら、どんな言葉になりますか?
中学受験の面接で「自分の性格や考え方を一言で表すとしたら、どんな言葉になりますか?」という質問は、お子様の自己認識能力や、表現力を見るためのものです。お子様自身が納得できる言葉を選び、その言葉を選んだ理由を具体的に話せるように準備しましょう。
例えば、「私を一言で表すなら「努力家」です。なぜなら、一度決めたことは最後まで諦めずに努力し続けることができるからです。逆上がりが苦手だった時も、毎日練習を続けて、できるようになりました」のように、選んだ言葉の裏付けとなる具体的なエピソードを話すことで、説得力が増します。お子様自身の言葉で、ありのままの自分を表現することが大切です。



応用レベルの質問は、一つ一つを完璧にするというよりも、話の引き出しを広げることを目的として様々な角度から質問を投げてみることに意識をおきましょう。
中学受験の面接を突破するためのおすすめ本
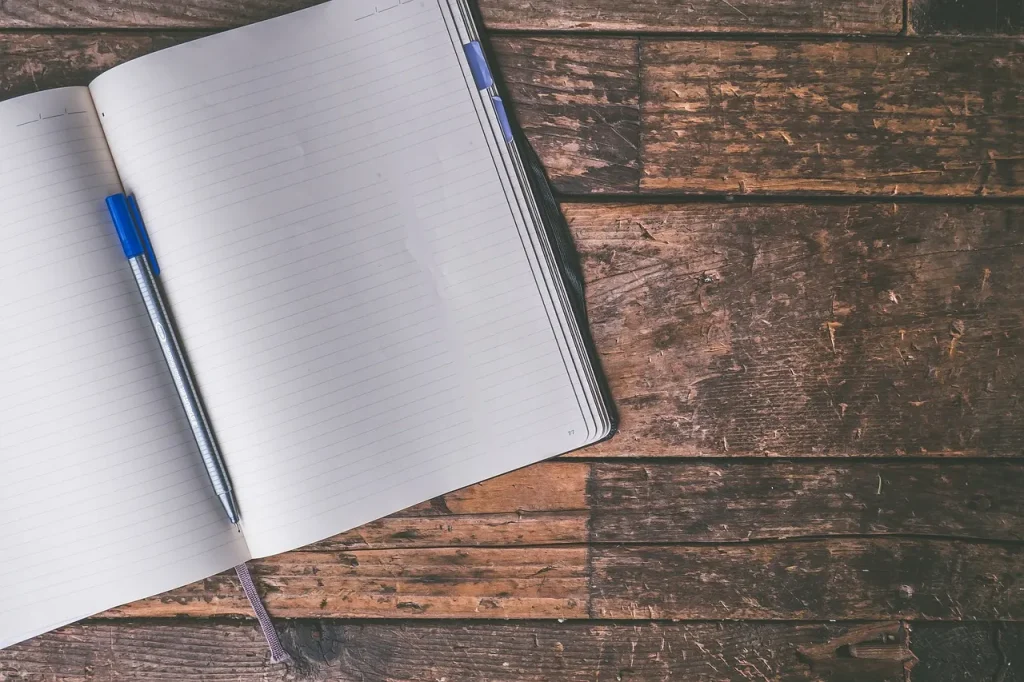
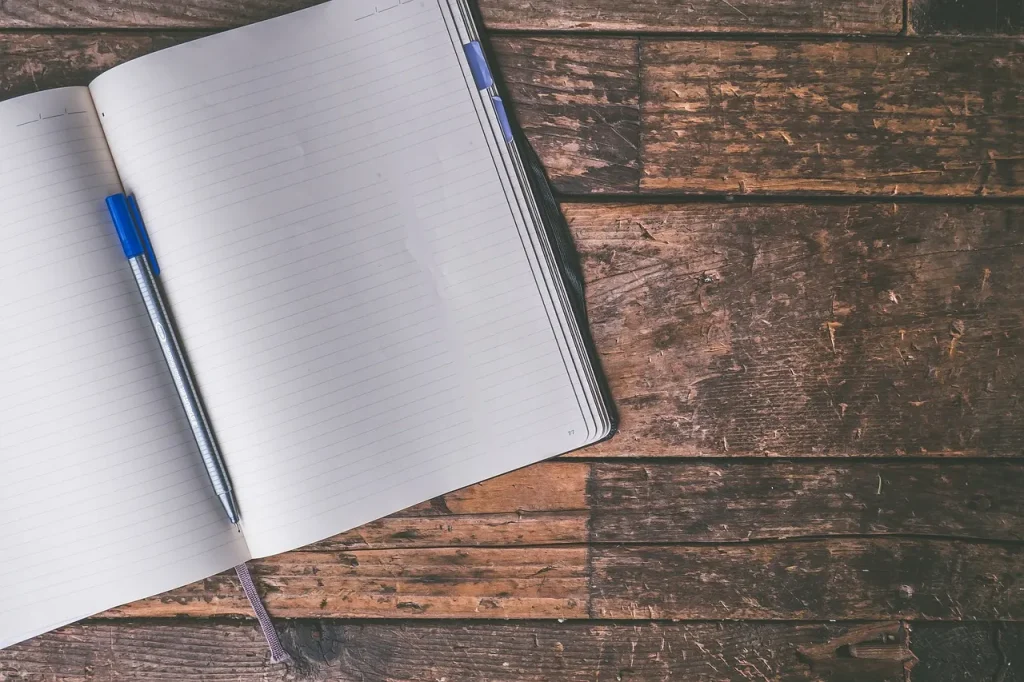
「親子で見る中学受験面接ブック」のおすすめポイント
- 面接の攻略ポイントの他にも「服装や持ち物」といった部分の情報も解説されている
- 面接が出題された学校のデータを元に志望校対策ができる



中学受験の面接対策本自体発売が少ないジャンルです。声の教育社の豊富な一次データを元に書かれているので、非常に信頼できる一冊です。
まとめ


面接は少しの対策でパフォーマンスを劇的に向上できる
中学受験の面接は、学力試験に比べると対策がおろそかになりがちですが、少しの対策でもお子様のパフォーマンスを劇的に向上させることが可能です。面接は、お子様の人柄やコミュニケーション能力、学校への適応性など、学力試験では測れない部分をアピールする貴重な機会です。事前に頻出質問への回答を準備し、模擬面接を繰り返すことで、お子様は自信を持って本番に臨むことができます。
また、入退室の仕方やお辞儀、話し方といった基本的なマナーを習得するだけでも、面接官に与える印象は大きく変わります。限られた時間でも、ポイントを押さえた対策を行うことで、お子様の持つ魅力を最大限に引き出し、合格に繋げることができるでしょう。
模擬面接を重ねて本番に挑もう
中学受験の面接において、模擬面接を重ねて本番に挑むことは、お子様の面接力を高める上で最も効果的な準備の一つです。模擬面接を繰り返すことで、お子様は様々な質問への対応力を身につけ、自分の考えを整理し、言葉にする練習を積むことができます。
また、親以外の大人に面接官役を依頼することで、本番に近い緊張感を体験し、客観的なフィードバックを得ることも可能です。繰り返しの練習は、お子様の自信を育み、本番での緊張を軽減する効果も期待できます。模擬面接を通じて、受け答えだけでなく、態度や表情、視線といった非言語コミュニケーションの部分も意識して練習することで、面接全体を通して良い印象を与えることができるようになります。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
有名中学校国語過去問に関する記事一覧
公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧
中高一貫校のデータに関する記事一覧
中学受験の面接で最も重視されるポイントは何ですか?
中学受験の面接では、お子様が自然なコミュニケーションを取れるかどうかが最も重視されます。事前に準備した模範解答を話すことよりも、面接官の質問意図を理解し、自分の言葉で適切に返答できるかが評価の対象となります。
面接対策にかける時間がない場合、どのような準備をすればよいですか?
時間が限られている場合は、頻出の質問への回答を簡潔にまとめるなど、効率を重視した対策が必要です。基本的な質問に焦点を絞り、自信を持って答えられるように練習しましょう。
面接で「知らない・わからない」質問が出た場合、どのように対応すればよいですか?
知らない質問や答えに詰まる質問が出た場合は、焦らずに「少し考える時間をいただけますか」と伝えたり、「すみません、今の質問の意味がよくわかりません」と正直に伝えることが好印象に繋がります。
中学受験の面接で好評価を得るために、どのような事前準備が重要ですか?
徹底した事前準備として、志望校の学校HPや説明会の内容を入念にチェックし、その情報を自身の言葉で語れるようにしておくことが非常に重要です。また、10~20個の質問を用意し、模擬面接を繰り返すことも効果的です。
面接対策はいつから、どのくらいの頻度で行うのが効果的ですか?
面接準備は、本番の1~2か月前から週に1~2回ほどの頻度で取り組むのが効果的です。無理なく継続して練習することで、お子様の記憶にも残りやすく、着実にスキルアップを図ることができます。
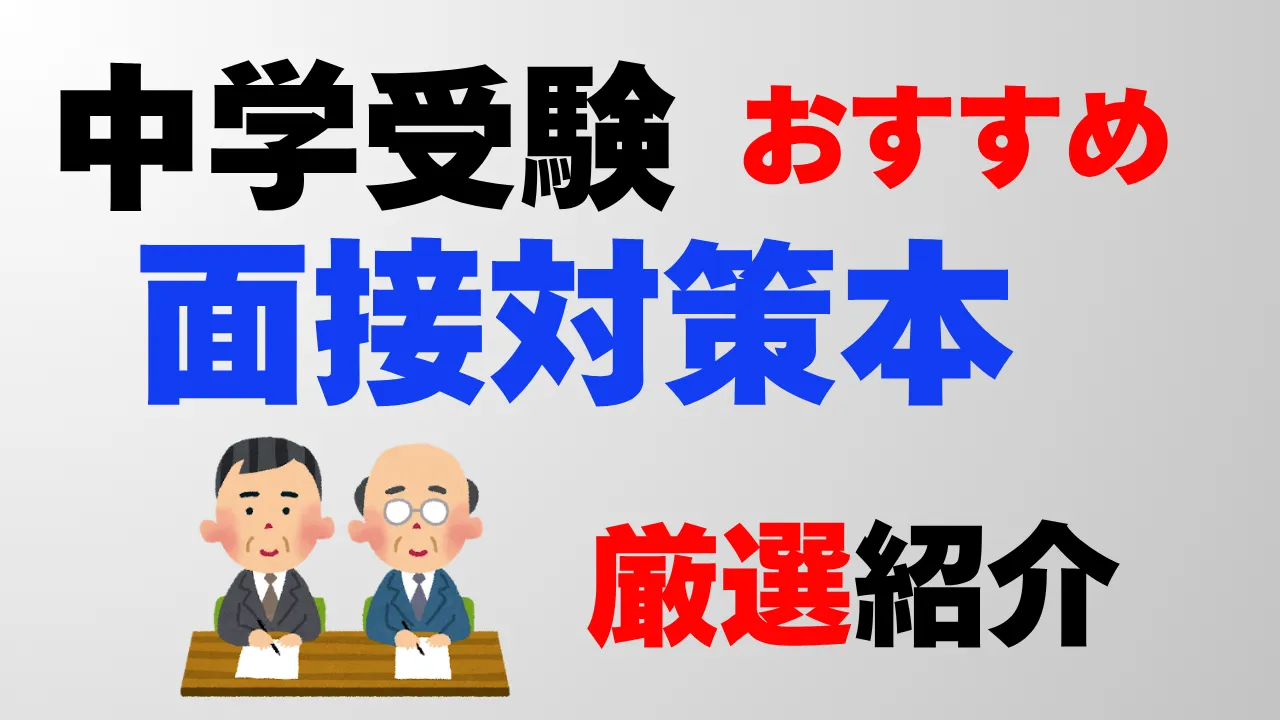

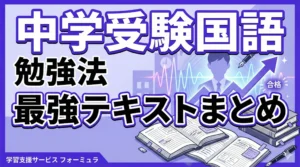
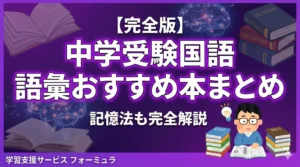


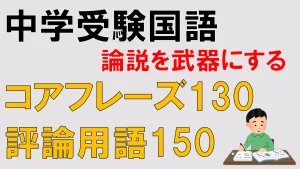
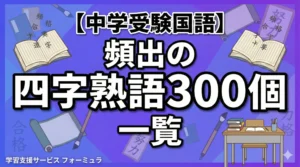
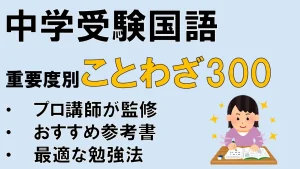
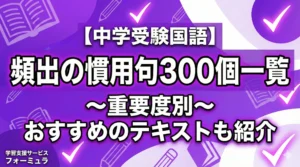
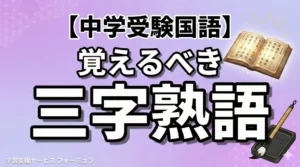


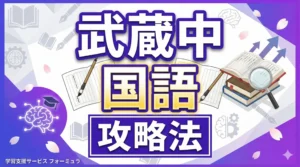


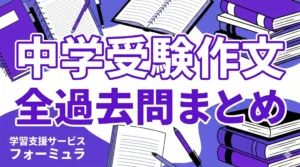
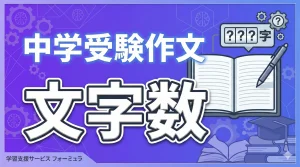
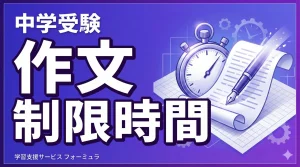
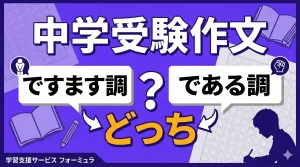
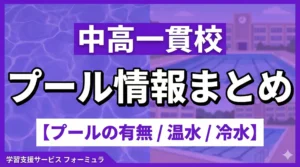

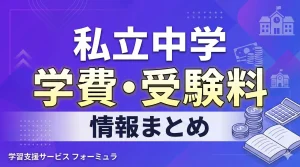
コメント