この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
- 「わが子は桜修館に向いているのだろうか?」
- 「都立中高一貫校の適性検査対策、何から始めれば…」
人気の桜修館受検、親子で悩むことも多いですよね。
知識だけでなく思考力・記述力が問われる適性検査、そして報告書(内申点)も重視される桜修館合格には、総合的な力と特別な対策が必要です。一般的な中学受験とは違う難しさに、戸惑いを感じていませんか?
この記事では、2013年から10年以上にわたり600人以上の桜修館を含む中学受験生を指導してきたプロ講師、神泉忍が、その経験と実績に基づき解説します。著書やYouTube、Xでも情報発信を行う指導のプロが、合格へのヒントを具体的にお伝えします。
桜修館に合格しやすいお子様の性格・思考・学習習慣の共通点から、最新の入試情報(偏差値・合格最低点の目安)、適性検査Ⅰ(作文)・Ⅱの効果的な対策、そしてご家庭でできるサポート術まで、合格に必要な情報を網羅しました。
この記事を読めば、桜修館合格に必要な具体的な人物像と対策が分かり、お子様に合った学習の進め方や、家庭での関わり方のヒントが得られます。漠然とした不安が解消され、自信を持って受検本番を迎えられるはずです。
この記事でわかること
- 桜修館に合格しやすい子の共通点
- 桜修館の偏差値・合格最低点と適性検査対策
- 家庭でできる効果的なサポート方法
桜修館受検、我が子は大丈夫?

桜修館をはじめとする都立中高一貫校の受検は、一般的な私立中学受験とは異なる難しさがあります。まずは、多くの保護者様が抱える悩みや疑問について見ていきましょう。
どんな子が桜修館に合格するの?
保護者様から最も多く寄せられる質問の一つが、「桜修館には、どのような個性や能力を持った子が合格しやすいのでしょうか?」というものです。
- 活発なリーダータイプの子?
- コツコツ努力するタイプの子?
合格する子のイメージが掴めず、わが子に桜修館が合っているのか、不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、多くの合格者を見てきた経験から、その共通点を具体的に紐解いていきます。
公立中高一貫校ならではの受検対策の難しさ
都立中高一貫校の入試は「適性検査」と呼ばれ、単なる知識の暗記量ではなく、知識を活用する思考力や、自分の考えを表現する記述力が重視されます。私立中学受験でよく見られる特殊算のような知識は必要ありませんが、小学校で学んだ知識を基に、問題文から意図を読み取り、論理的に考え、説明する力が求められます。特に桜修館の適性検査は、文章量が多く、記述させる問題も多いのが特徴です。 この特殊性から、どのような対策をすればよいのか、戸惑う保護者様も少なくありません。
桜修館合格には総合的な力が求められる
中学受験というと、どうしても偏差値に目が行きがちです。しかし、桜修館の合否は、学力テストの点数だけで決まるわけではありません。思考力や表現力はもちろん、日々の学習態度を示す「報告書(通知表)」も評価の対象となります。桜修館合格のためには、ペーパーテスト対策だけでなく、小学校での学習や生活態度も含めた総合的な力が求められるのです。 この点も、桜修館受検の対策を考える上で重要なポイントとなります。
桜修館に合格しやすい子の共通点【性格・思考編】

では、具体的にどのような性格や思考の傾向を持つお子様が、桜修館に合格しやすいのでしょうか。多くの合格者を見てきた中で見えてきた共通点を解説します。
桜修館に合格しやすい子の共通点【性格・思考編】
- 「素直さ」と「柔軟さ」がある
- 「コツコツ努力を続けられる粘り強さ」がある
- 「なぜ?」を追求できる
- 物事を多角的に捉えられる
- 言語化能力に長けている
「素直さ」と「柔軟さ」がある
桜修館の合格者に共通して見られる最も重要な資質の一つは「素直さ」です。塾の先生や親からのアドバイスを、まずは「やってみよう」と受け入れ、実践できる子は、効率的に力を伸ばしていくことができます。自己流に固執せず、効果的な学習方法を素直に取り入れられる柔軟性が、成長の大きな鍵となります。 最初から自分のやり方だけで進めようとすると、合格への道のりが遠回りになってしまう可能性があります。
「コツコツ努力を続けられる粘り強さ」がある
桜修館の適性検査で問われる応用力は、知識を基にした「経験」の積み重ねによって養われます。そのため、日々の学習にコツコツと地道に取り組む継続力が非常に重要です。難しい問題に直面してもすぐに諦めず、粘り強く考え抜く力、一問一問に真摯に向き合い、深く掘り下げていく姿勢が、合格に必要な思考力を育てます。 要領よく進めることよりも、一つ一つの課題に丁寧に取り組むことが、最終的な伸びにつながります。
「なぜ?」を追求できる
身の回りの出来事や学習内容に対して、「なぜ?」「どうして?」と疑問を持ち、その答えを知りたい、調べたいと思える知的好奇心旺盛な子は、適性検査に向いています。適性検査では、社会の事象や科学的なテーマなど、幅広い分野からの出題が見られます。日頃から様々なことに興味関心を持ち、疑問を放置せず探求する姿勢が、知識の幅と思考の深さを育みます。
物事を多角的に捉えられる
桜修館では、教育目標の一つとして「論理的思考力の育成」を掲げており、国語や数学とは別に「論理」の授業があるほどです。これは、物事を一つの側面からだけでなく、様々な角度から捉え、多角的に考察する力を重視していることの表れといえるでしょう。適性検査でも、与えられた情報から本質を見抜き、多角的な視点から考察する力が求められます。 結論だけでなく、そこに至るプロセスを論理的に考えられることが大切です。
言語化能力に長けている
桜修館の適性検査、特に適性検査Ⅰ(作文)では、自分の考えを筋道立てて、分かりやすく文章で表現する力が非常に重要視されます。頭の中で考えていることを、採点者に伝わるように的確な言葉で記述する能力は、一朝一夕には身につきません。日頃から、考えたことや学んだことを自分の言葉で説明したり、文章にまとめたりする練習を積み重ねることが不可欠です。 書くことを面倒くさがらずに取り組む姿勢が、合格への道を拓きます。
桜修館に合格しやすい子の共通点【学習習慣編】

性格や思考の傾向に加え、日々の学習習慣も合否に大きく影響します。どのような学習習慣が桜修館合格につながるのでしょうか。
桜修館に合格しやすい子の共通点【学習習慣編】
- 日頃から、文章に親しんでいる
- 書くことで思考を整理している
- 机に向かう習慣があり、計画的に学習できる
- 間違いを恐れず、学びにつなげられる
日頃から、文章に親しんでいる
適性検査では長文の課題文が出されることが多いため、読書習慣があり、文章を読むことに慣れている子は有利です。多くの文章に触れることで、語彙力や読解力が自然に向上し、背景知識も豊かになります。必ずしも「勉強のため」と意識する必要はなく、物語、図鑑、新聞など、ジャンルを問わず活字に親しむ習慣が、適性検査対策の土台となります。 頭の中で内容を整理しながら読み進める練習にもなります。
書くことで思考を整理している
桜修館の適性検査では、最終的な答えだけでなく、考え方や途中の説明を記述させる問題が多く出題されます。そのため、日頃からノートを丁寧に書き、自分の思考プロセスを文字に起こす練習をしておくことが非常に重要です。 書くことを面倒くさがらず、結論だけでなく、なぜそう考えたのかをノートに書き残す習慣が、記述力を養い、合格に必要な説明力を高めます。合格者のノートは、やはりしっかりと書き込まれている傾向があります。
机に向かう習慣があり、計画的に学習できる
毎日決まった時間に学習する、週単位で学習計画を立てて実行するなど、主体的に学習に取り組む習慣が身についていることも大切です。「コツコツ努力を続けられる粘り強さ」とも関連しますが、計画性を持って学習を進められる自己管理能力は、膨大な適性検査の対策範囲をこなしていく上で不可欠な力となります。 やるべきことを着実にこなしていく習慣が、合格への確かな歩みとなります。
間違いを恐れず、学びにつなげられる
問題を間違えることは、決して悪いことではありません。大切なのは、間違えた原因を自分で考え、次に同じ間違いを繰り返さないように対策することです。「ちょっとした計算ミスだから大丈夫」「本当は分かっていた」などと安易に流さず、なぜ間違えたのかを分析し、次に活かそうとする前向きな姿勢が、学力向上には欠かせません。 このような経験の積み重ねが、本番での得点力を高めます。
【注意】桜修館合格を遠ざかるかもしれない習慣

これまで合格しやすい子の特徴を見てきましたが、逆に、どのような点が合格から遠ざかってしまう可能性があるのでしょうか。お子様の学習態度を見直す際の参考にしてください。ただし、当てはまるからといって悲観する必要はありません。意識して改善していくことが大切です。
受け身の学習姿勢で、自分から動かない
先生や親に言われたことだけをこなす、疑問点があっても質問しない、といった受け身の学習姿勢では、思考力や応用力が問われる桜修館の適性検査に対応するのは難しいかもしれません。また、アドバイスを聞き入れずに自分のやり方に固執しすぎるのも、成長の妨げになる可能性があります。 まずはやってみる、という前向きな姿勢が求められます。
解けない問題があるとすぐに諦めてしまう
難しい問題にぶつかったとき、すぐに「分からない」と諦めてしまう、考え続けることを放棄してしまう、という姿勢も注意が必要です。適性検査では、粘り強く多角的に考える力が求められます。すぐに答えを求めるのではなく、試行錯誤しながら少しずつでも考え続ける経験が、思考力を鍛えます。 一問一問に丁寧に向き合う粘り強さを養いましょう。
作文や記述問題への苦手意識が強すぎる
「作文は苦手」「文章を書くのは面倒くさい」といった強い苦手意識から、記述問題の対策を避けてしまうと、桜修館の合格は非常に厳しくなります。適性検査Ⅰ(作文)はもちろん、適性検査Ⅱでも記述力が求められる問題が多く出題されます。最初から完璧を目指す必要はありませんので、短い文章からでも、書く練習をコツコツと積み重ね、苦手意識を克服していくことが重要です。
【桜修館入試】偏差値と適性検査の概要

桜修館合格のためには、まず入試の仕組みを正確に理解することが不可欠です。ここでは、偏差値の目安や適性検査の内容、報告書の扱いについて解説します。
桜修館の偏差値レベルと位置づけ
桜修館の偏差値は、一般的に都立中高一貫校の中でも上位に位置づけられています。
- 偏差値70:東京都立小石川中等教育学校
- 偏差値69:千葉県立千葉中学校
- 偏差値67:東京都立両国高等学校附属中学校
- 偏差値65:横浜市立南高等学校附属中学校
- 偏差値65:東京都立桜修館中等教育学校
- 偏差値65:東京都立武蔵高等学校附属中学校
参照:「公立中高一貫教育校 偏差値ランキング(2024年度)/シリタス<2025年4月18日時点>」
こちらの偏差値ランキングでは、6位になっています。ただし、中学受験における偏差値は、模試の種類や受験者層によって変動するため、あくまで一つの目安として捉えることが大切です。偏差値の数値に一喜一憂するのではなく、桜修館の入試で求められる力を着実に身につけることに焦点を当てましょう。 大切なのは、偏差値の高さではなく、適性検査に対応できる総合的な学力です。
適性検査Ⅰ(作文)の特徴と評価ポイント
適性検査Ⅰ(作文)は、桜修館の独自問題が出題されます。近年は、二つの異なる文章(文章A・文章B)を読み、それぞれの内容を理解・比較した上で、自分の考えや意見を記述する形式が主流です。単に文章を要約するだけでなく、課題文のテーマについて深く考察し、自分の体験や知識と結びつけて論理的に意見を述べる力が求められます。 採点は、字数を満たしているかだけでなく、内容の論理性や表現の的確さなどが厳しく評価される傾向にあります。結論の良し悪しよりも、そこに至る思考プロセスが重視されます。
適性検査Ⅱ(総合)の特徴と評価ポイント
適性検査Ⅱは、算数・国語・理科・社会の要素を融合した総合的な問題が出題されます。大問は3つで構成され、そのうち大問2と大問3は他の都立中高一貫校との共同作成問題、大問1が桜修館の独自問題となることが多いです。小学校で学んだ知識を基に、資料(グラフ・表など)を正確に読み解き、問題文の条件を整理し、論理的に考えて答えを導き出し、その過程を記述する力が問われます。 知識の暗記量よりも、知識をいかに活用できるかが重要となります。
報告書(内申点)はの配点比率は高い傾向にある
桜修館の入試では、報告書(調査書)の点数が1000点満点中300点を占めており、他の都立中高一貫校と比較しても高い比率です。これは、小学校での学習態度や成績も重視されていることの表れです。評価の対象となるのは主に5年生と6年生の成績です。近年、報告書の評価は、授業態度といった主観的なものだけでなく、ノートの提出状況やテストの点数、課題への取り組みなど、客観的な成果物(アウトプット)に基づいて行われる傾向が強まっています。 日々の授業に真剣に取り組み、提出物を丁寧に行うことが、報告書の評価につながります。
桜修館の合格最低点は「非公開」

まず、大前提として知っておかなければならないのは、桜修館中等教育学校は、正式な合格最低点を公表していないということです。そのため、インターネット上などで見かける点数は、あくまで過去の受験生のデータなどから推測された目安となります。しかし、「じゃあ、何点を目指せばいいの?」と不安になりますよね。そこで、多くの受験生を指導してきた専門塾が分析する「目標とすべきライン」について見ていきましょう。
目標は男子670点・女子700点前後
1000点満点中、男子であれば670点前後、女子であれば700点前後が、ギリギリ合格できるかどうかのボーダーライン(目標点)になることが多いようです。もちろん、これは年度ごとの難易度によって多少変動しますが、一つの大きな目安として、この点数を意識しておくと良いでしょう。
なぜ最低点は毎年変動する?記述式の影響
桜修館の入試が一般的な私立中学と異なるのは、「適性検査」であり、特に作文(適性Ⅰの一部)と適性検査Ⅱが記述式中心である点です。マークシートとは違い、記述式の採点は、採点基準によってある程度の幅を持たせることが可能です。そのため、問題の難易度が高かった年は採点を少し甘めに、易しかった年は厳しめにするなどして、学校側がある程度、合格最低ラインを意図した範囲(例:7割前後)に調整している可能性が考えられます。これが、年度によって合格最低点が変動する(ように見える)理由の一つです。
報告書(内申点)は280点を目指そう
報告書(いわゆる内申点)は300点満点です。小学校での成績や活動が評価されますが、これは入試本番前にほぼ点数が決まっています。目標としては、280点前後(9割以上)あると、適性検査に向けて有利なスタートを切れるでしょう。ただし、報告書の点数が多少足りなくても、適性検査の結果次第で十分に逆転合格は可能です。諦めずに本番の試験対策に力を入れましょう。
作文は120点が目標ライン
適性検査Ⅰに含まれる作文は200点満点です。ここで満点に近い高得点を取るのはなかなか難しいとされています。まずは安定して120点(6割)あたりを取れるように練習することが現実的な目標ラインとなるでしょう。日頃から書く練習を重ね、時間内に自分の考えを論理的にまとめられるように対策しておくことが重要です。
適性検査Ⅱは最低300点以上を
配点が500点と最も大きい適性検査Ⅱが、桜修館入試の合否を分ける最も重要な科目と言っても過言ではありません。ここでどれだけ得点できるかが勝負の鍵を握ります。目標としては、最低でも300点(6割)以上は確保したいところです。ただし、合格者全体のデータを見ると、実際の合格ライン上の受験生の適性検査Ⅱの点数は、必ずしも300点に達していない可能性もあります。それでも、ここで高得点を取ることが合格への大きなアドバンテージになるため、重点的な対策が不可欠です。
トータル7割前後を目指して対策を
桜修館入試の合格最低点は非公開ですが、これまでの分析から、3科目合計(1000点満点)で7割(700点)前後が合格ラインの目安と考えられます。800点を取れればほぼ安心、600点台後半でも十分に合格の可能性があります。
【適性検査Ⅰ】の対策
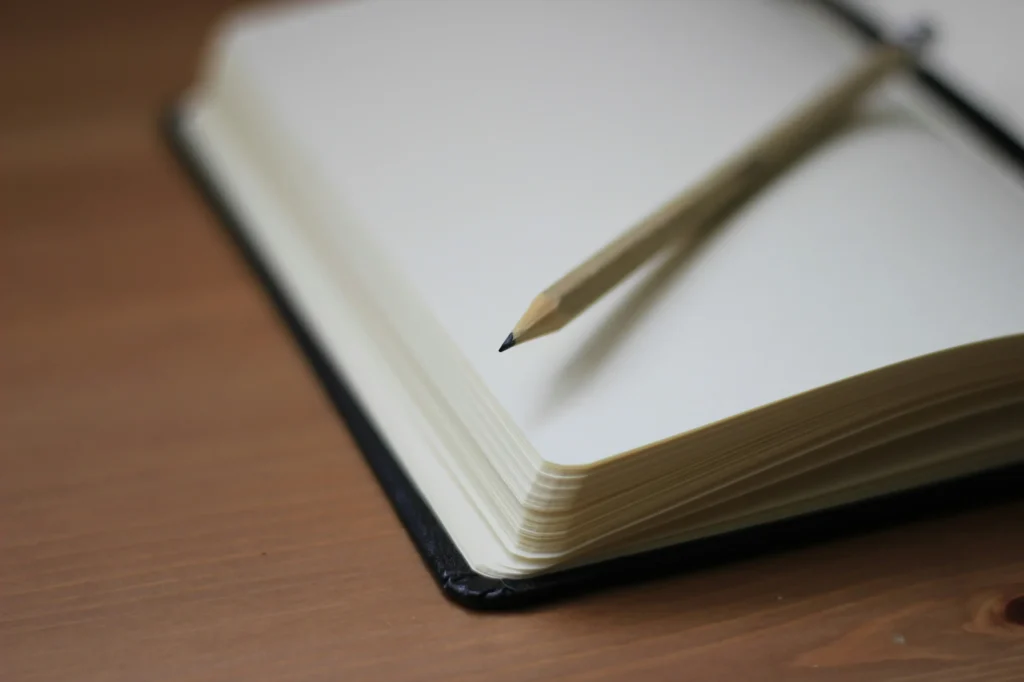
桜修館の合否を大きく左右する適性検査Ⅰ(作文)。ここでは、高得点を取るための具体的な対策方法を解説します。
文章の要点を正確に読み取る練習
まず基本となるのが、課題文の内容を正確に読み取る力です。複数の文章が出されることが多いので、それぞれの文章の主題や筆者の主張、共通点や相違点を的確に把握する練習が必要です。漫然と読むのではなく、「何が問われているのか」「筆者は何を伝えたいのか」を常に意識しながら読む訓練をしましょう。 要点をメモしながら読むのも効果的です。
自分の考えを論理的に構成する力
適性検査Ⅰで求められるのは、感想文ではなく「意見文」です。意見文には、論理的で分かりやすい構成が不可欠です。一般的には、「序論(問題提起・自分の意見提示)→本論(意見の根拠となる理由や具体例)→結論(意見の再提示・まとめ)」という型を意識すると、説得力のある文章が書けます。 ただ、公立中高一貫校の入試では制限文字数が400文字程度です。一般的な型を用いると、文字数が足りなくなってしまうので、「結論」+「具体例」という型で解答を作っていきましょう。「結論」というのは、設問に対する解答です。具体例はそれに付随する事実のことです。
 塾長 神泉
塾長 神泉中学受験作文の文章構成法については「【公立中高一貫校 作文】そもそも書き方が分からない!作文が全く書けない人でも明日から使える鉄板の文章構成術」という記事でより詳しく解説しています。
短い文から練習し、書くことに慣れる
いきなり長文を書こうとすると、苦手意識が先に立ってしまうお子様もいます。まずは、「主語と述語を明確にする」「一文を短くする」といった基本的なルールを守り、正しい日本語で短い文章を書く練習から始めましょう。 語彙力を増やすために、類義語辞典を活用したり、日頃から様々な言葉に触れたりすることも大切です。少しずつ書くことに慣れていくことが、長文作成へのステップとなります。本格的な長文演習は、基礎が固まった6年生の春以降でも間に合います。
時間内に書き上げるための構成メモ活用術
試験時間は限られています。時間内に質の高い作文を完成させるためには、書き始める前に構成を練る時間が重要です。課題文を読んだ後、いきなり書き始めるのではなく、数分間で簡単な構成メモ(アウトライン)を作成する習慣をつけましょう。 各段落で何を書くか、どのような具体例を入れるかなどをメモしておけば、途中で話が逸れたり、時間切れになったりするのを防ぐことができます。
【適性検査Ⅱ】の対策
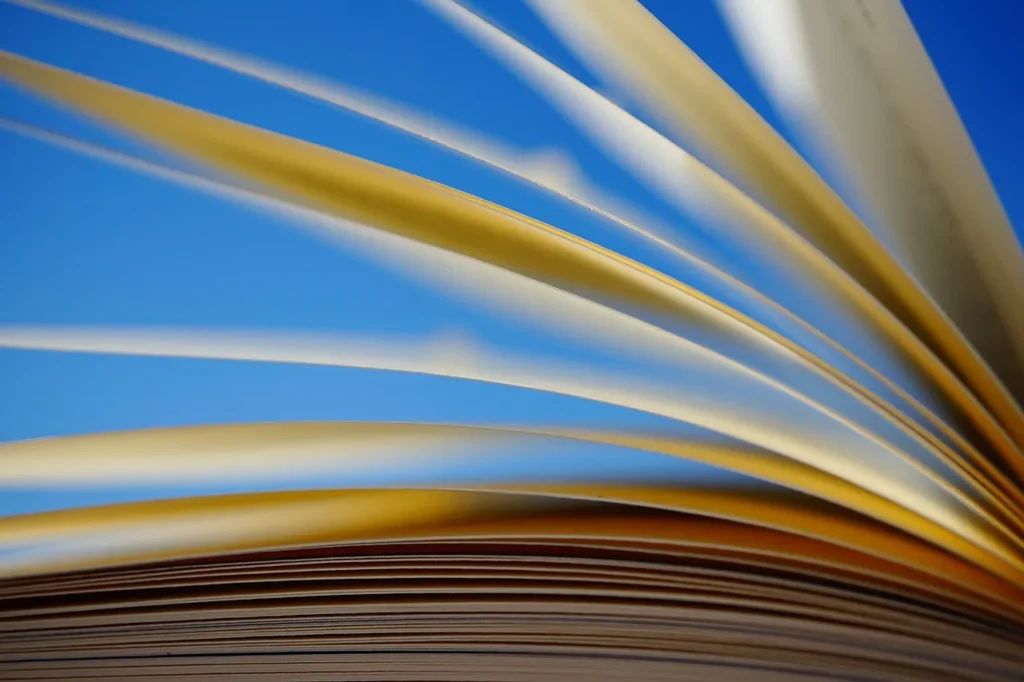
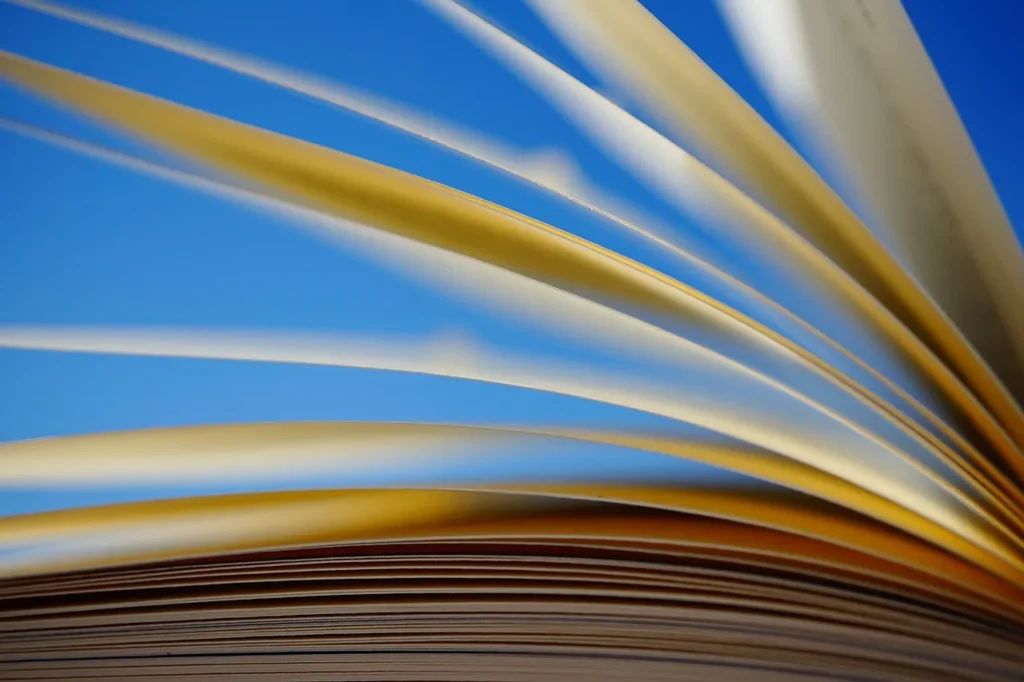
算数・国語・理科・社会の知識を総動員して解くのが適性検査Ⅱです。多様な問題形式に対応するための対策ポイントを解説します。
資料(グラフ・表)の正確な読み取り
適性検査Ⅱでは、グラフ、表、地図、実験データなど、様々な形式の資料が提示され、そこから情報を読み取って考察する問題が多く出題されます。資料の種類によって注目すべきポイントは異なりますが、まずはタイトルや単位、注釈などをしっかり確認し、何を表している資料なのかを正確に把握することが基本です。 複数の資料を比較検討させる問題も多いため、情報を整理しながら読み解く練習が必要です。
問題文の条件整理と論理的な思考力
適性検査Ⅱの問題文は、長文で条件が複雑に設定されている場合が少なくありません。問題文を正確に読み、与えられた条件を整理し、何を問われているのかを的確に把握する力が求められます。 そして、整理した条件に基づいて、筋道を立てて答えを導き出す論理的な思考力が不可欠です。普段から問題文を丁寧に読み、条件を図や箇条書きで整理する習慣をつけましょう。
算数・理科・社会の融合問題への対応
適性検査Ⅱでは、算数的な考え方、理科的な知識、社会的な視点などが複合的に問われる問題が多く見られます。単に各教科の知識を暗記するだけでなく、それらの知識を様々な場面で活用し、結びつけて考える力が重要です。 例えば、グラフの読み取り(算数)と環境問題(理科・社会)を結びつけるような問題です。小学校で学んだ知識をベースに、分野を横断した問題演習に取り組むことが有効です。
考察した内容を分かりやすく記述する力
適性検査Ⅱでも、考え方や理由を記述させる問題が多く出題されます。計算問題であっても、答えだけでなく、なぜその式になるのか、どのように考えたのかを、採点者に伝わるように分かりやすく記述する練習が必要です。 必要に応じて図や表を用いたり、順序立てて説明したりするなど、相手に「説明する」ことを意識した記述を心がけましょう。日頃のノート作りから、途中式や考え方を丁寧に書く習慣が役立ちます。
【家庭学習】桜修館合格を近づけるサポート術


桜修館合格のためには、塾での学習だけでなく、ご家庭でのサポートも非常に重要です。お子様の力を最大限に引き出すために、保護者としてできることをご紹介します。
子供の考えを「承認」し、待つ姿勢
お子様の成長には個人差があります。すぐに結果が出なくても、焦らず、お子様の可能性を信じて「待つ」姿勢が大切です。また、お子様が自分の考えを話したり、学習に取り組んだりした際には、まずはその頑張りを認め、「よく考えたね」「頑張っているね」と「承認」してあげましょう。 これは甘やかしとは異なります。お子様の自己肯定感を育み、主体的に学ぶ意欲を引き出すための重要な関わり方です。勉強の内容に口を出しすぎず、見守ることも時には必要です。
日常会話から思考力・表現力を引き出す
ご家庭での日常会話は、お子様の思考力や表現力を自然に伸ばす絶好の機会です。「今日は学校でどんなことがあった?」「このニュースについてどう思う?」など、保護者様が「インタビュアー」になったつもりで、お子様に質問を投げかけ、話を引き出してあげましょう。 答えが合っているか間違っているかよりも、自分の考えを話すプロセスを大切にし、良いリアクションで応えてあげることで、お子様は話すことの楽しさを感じ、考える力を養うことができます。
新聞やニュースで社会への関心を高める
適性検査では、時事問題や社会的なテーマに関連する出題も見られます。お子様と一緒にニュースを見たり、新聞(子供向け新聞でも可)を読んだりする習慣は、社会への関心を高め、適性検査対策にもつながります。 「この問題についてどう思う?」などと話し合い、親子で考える時間を持つのも良いでしょう。幅広い知識や多様な視点を養うきっかけになります。
効果的な学習計画と環境づくり
お子様が集中して学習に取り組める環境を整えることも、保護者様の大切な役割です。学習に適した静かなスペースを確保したり、スマートフォンやゲームなどの誘惑から距離を置けるようルールを決めたりするなど、環境面でのサポートを心がけましょう。 また、お子様と一緒に無理のない学習計画を立て、主体的に学習に取り組む態度を育むことも重要です。日々の学習習慣の確立をサポートしましょう。
まとめ
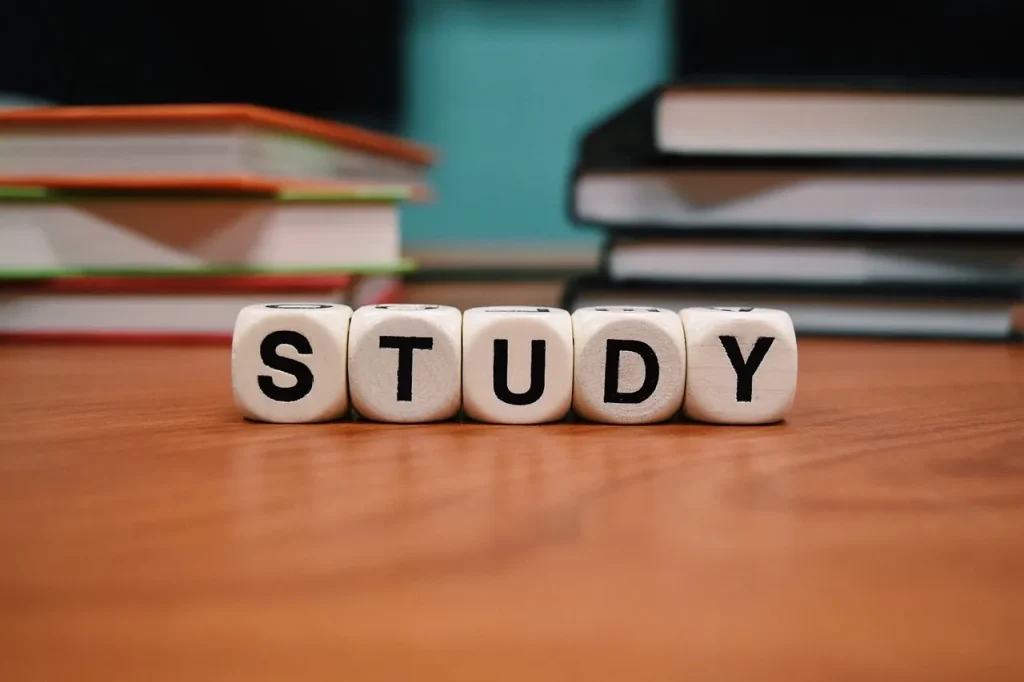
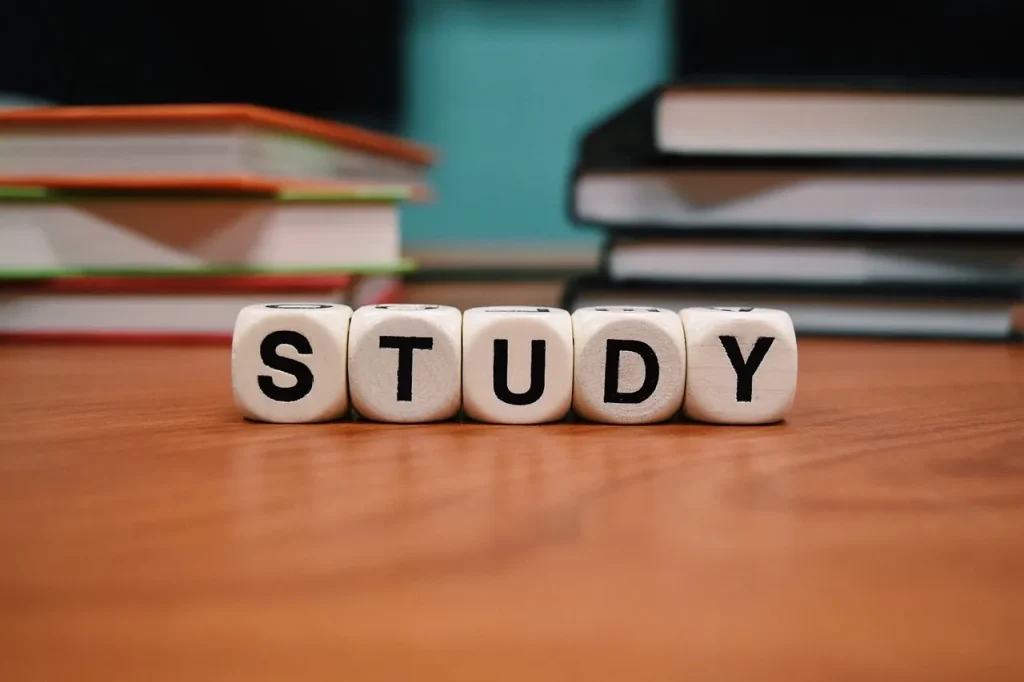
ここまで、桜修館に合格しやすい子の特徴や、具体的な対策方法、家庭でのサポート術について解説してきました。最後に、桜修館合格を目指す保護者様とお子様へ、メッセージをお伝えします。
「合格する子の特徴」はあくまで目安
この記事で紹介した「合格しやすい子の特徴」は、多くの合格者に見られた傾向であり、絶対的なものではありません。たとえ現時点で当てはまらない特徴があったとしても、決して悲観する必要はありません。 大切なのは、お子様自身の個性や長所を認め、それを伸ばしていくことです。実際に、大人しいタイプのお子様が見事に合格を勝ち取った例もたくさんあります。お子様の可能性を信じましょう。
保護者の前向きなサポートがお子様の力になる
中学受験は、お子様一人だけでなく、ご家族全体で乗り越える挑戦です。特に保護者様の精神的なサポートは、お子様にとって何よりの力となります。結果に一喜一憂しすぎず、お子様の頑張りを認め、励まし、そして成長を信じて待つという前向きな姿勢が、お子様のモチベーションを支え、困難を乗り越える原動力となります。 親子で力を合わせ、自信を持って桜修館合格への道を歩んでいってください。応援しています!
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
有名中学校国語過去問に関する記事一覧
公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧
中高一貫校のデータに関する記事一覧
桜修館に合格しやすい子には、どんな性格や考え方の特徴がありますか?
素直で柔軟な姿勢、コツコツ努力できる粘り強さ、物事の理由を探求する好奇心、多角的な視点、自分の考えを言葉で表現する力などが共通して見られます。自己流に固執せず、アドバイスを受け入れられる素直さが特に重要です。
桜修館に合格しやすい子の学習習慣には、どんな特徴がありますか?
日頃から読書などで文章に親しんでいること、考えをノートに書き出す習慣があること、計画的に学習を進められること、間違いを恐れずに原因を分析し次に活かせることなどが挙げられます。特に思考プロセスを記述する習慣が重要です。
桜修館の入試(適性検査や報告書)にはどんな特徴がありますか?
適性検査Ⅰ(作文)では思考力と記述力、適性検査Ⅱでは教科横断的な知識活用力や資料読解力、論理的思考力が問われます。報告書(内申点)の配点比率が300点と高いのも特徴で、小学校での学習態度も重視されます。
桜修館の合格最低点の目安はどのくらいですか?
学校は最低点を公表していませんが、1000点満点中、男子670点、女子700点前後が目標ラインとされています。ただし記述式の採点調整があるため変動の可能性があり、トータル7割前後を目指すのが目安です。
家庭でできる桜修館合格のための効果的なサポート方法はありますか?
お子様の考えをまず承認し、焦らず待つ姿勢が大切です。日常会話で思考力や表現力を引き出したり、一緒にニュースを見て社会への関心を高めたりすることも有効です。また、集中できる学習環境を整え、計画的な学習習慣をサポートしましょう。
おまけ〜桜修館の文化祭の様子〜
桜修館中等教育学校の文化祭の様子


学校の玄関に各クラスの出し物のポスターが貼り出されています。




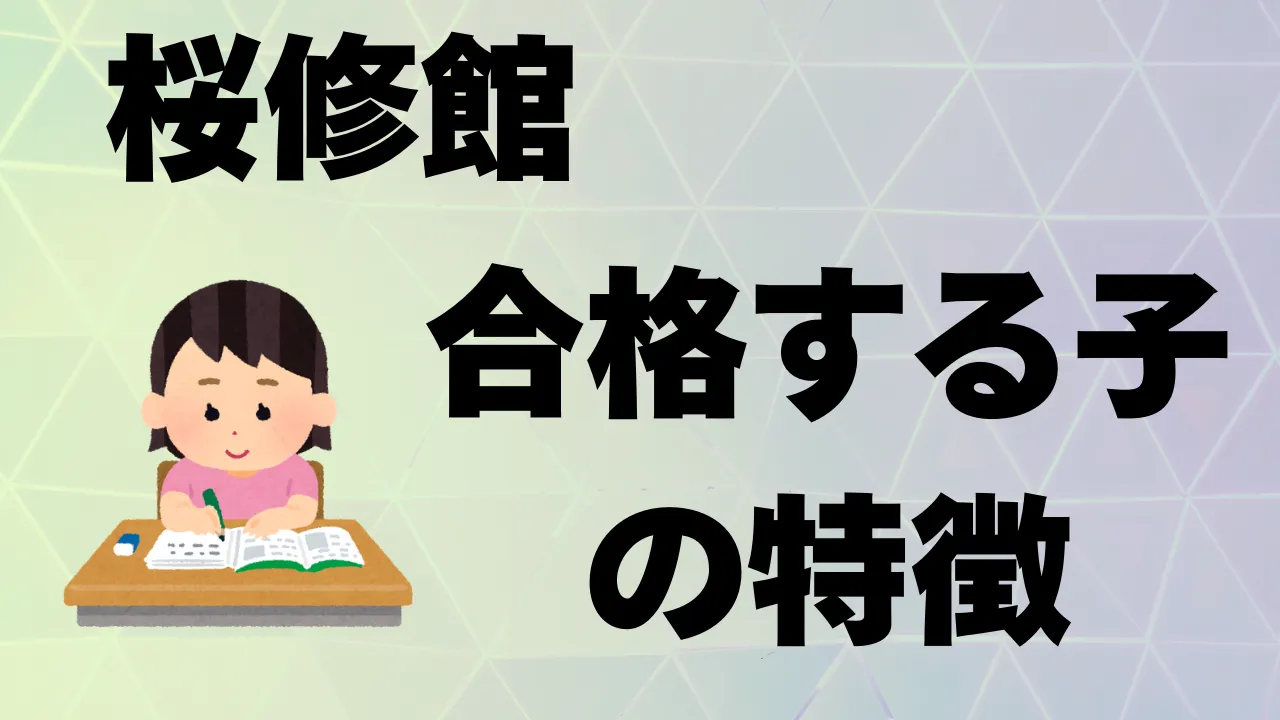
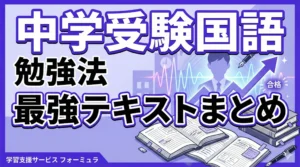
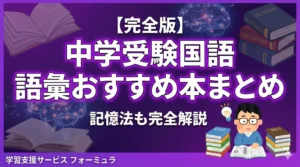


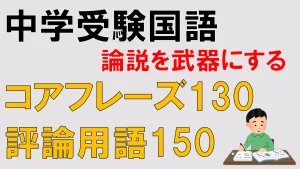
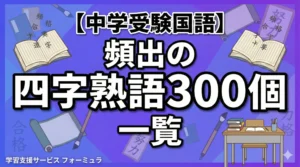
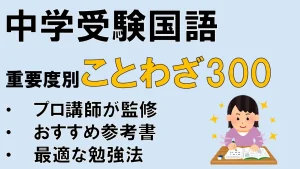
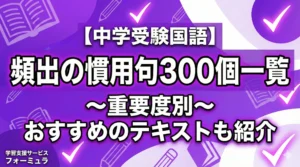
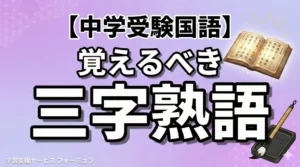


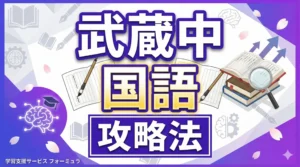


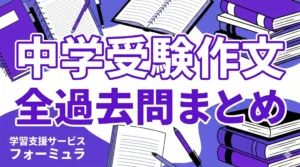
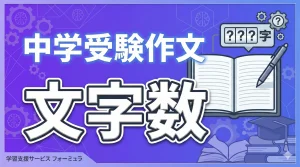
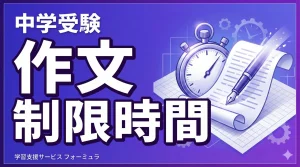
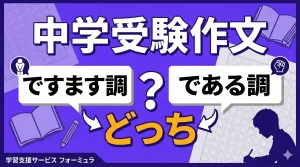
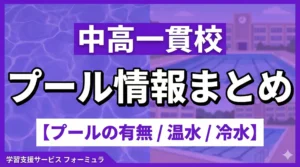

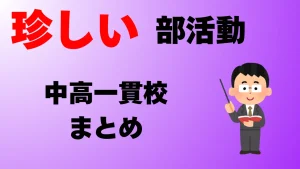
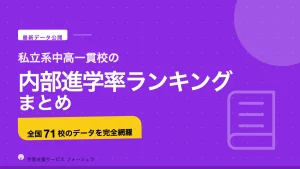
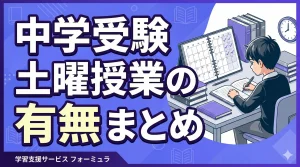
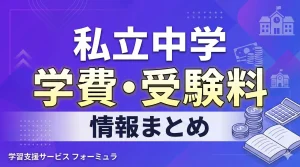
コメント