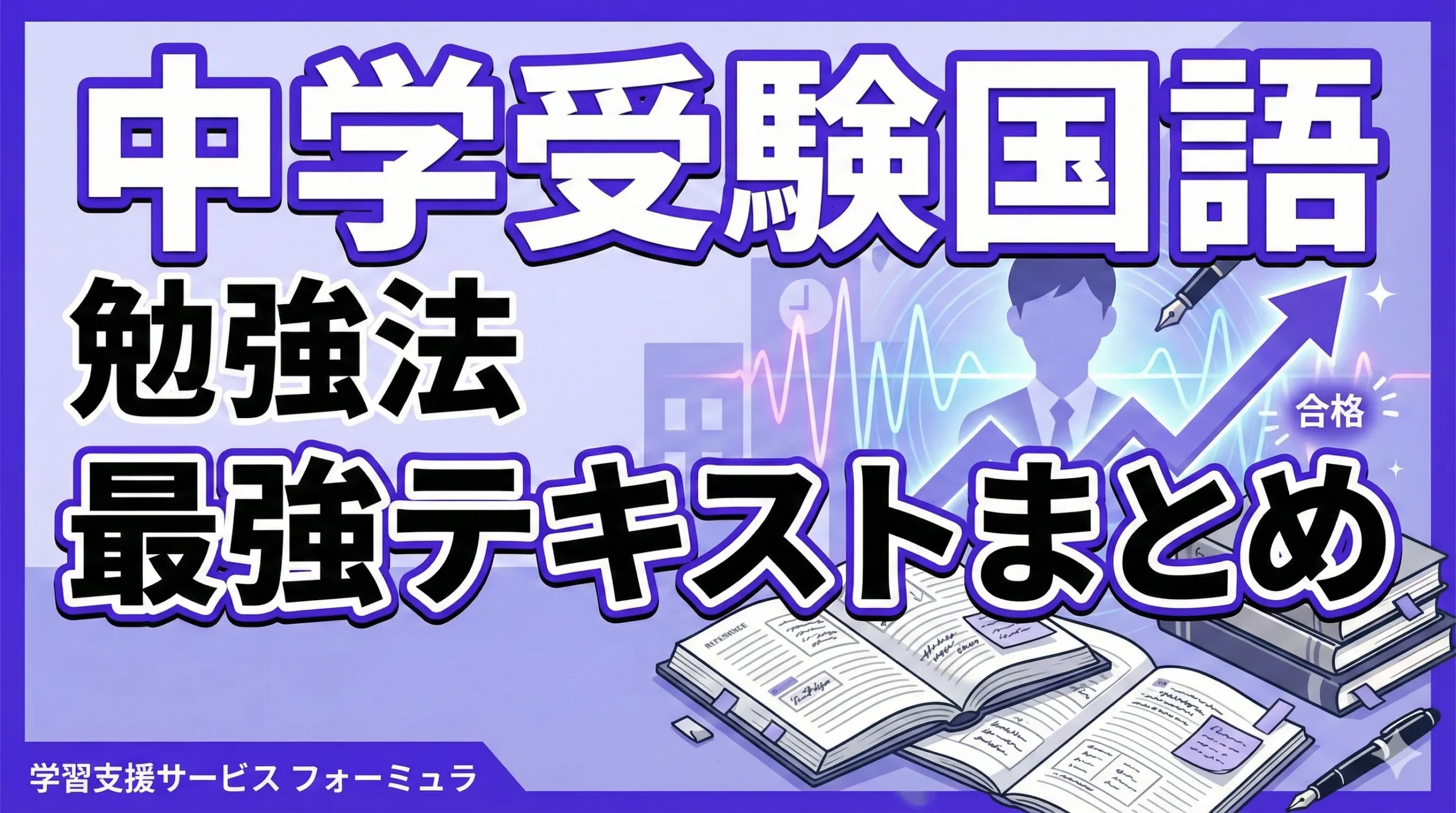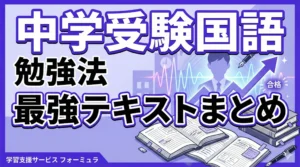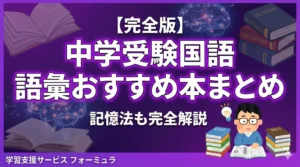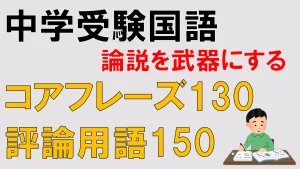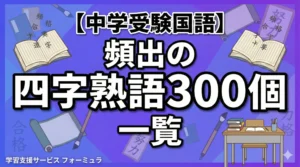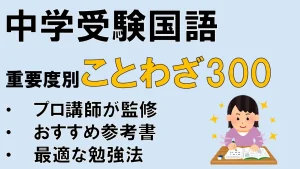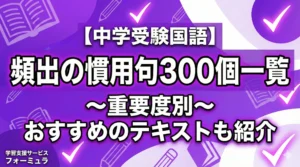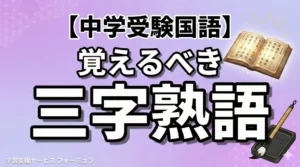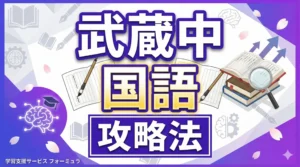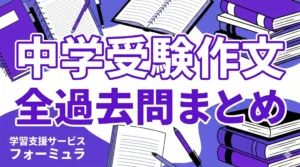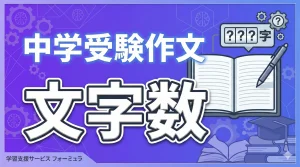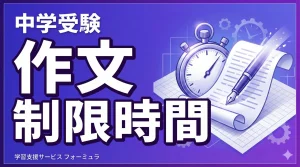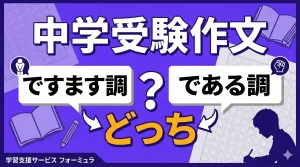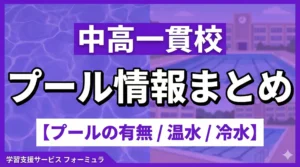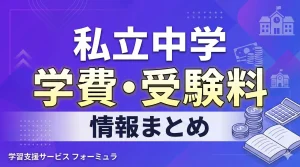中学受験国語の勉強法は?プロ講師が解説します
この記事書いた人「神泉忍」について
- 慶應義塾大学総合政策学部卒
- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる
- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設
- 国語と作文指導が専門
- YouTubeで受験関連の情報を発信中
- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中
- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています
学年や状況ごとに最適な勉強法を紹介します
中学受験の国語は、多くの保護者の方が対策に悩む科目です。一口に国語の勉強法といっても、お子様の学年や現在の学習状況によって、最適なアプローチは大きく異なります。たとえば、小学3年生と小学6年生では、求められる知識や読解レベルが全く違うため、同じ勉強法では効果が薄いでしょう。
また、語彙力が不足しているのか、文章の論理構造を理解できていないのか、それとも記述問題の対策が必要なのか、お子様の弱点によって重点を置くべきポイントも変わります。この記事では、お子様の現状に合わせた具体的な勉強法を、学年別に詳しく解説していきますので、ぜひご家庭での学習計画に役立ててください。
中学受験国語の成績の伸ばし方を具体的に解説します
中学受験国語で成績を伸ばすためには、ただやみくもに問題を解くだけでは不十分です。まずは、お子様の得意な分野と苦手な分野を正確に把握することが重要になります。漢字や語彙などの知識系が弱いのか、それとも長文読解、特に論理的文章や文学的文章の読解に課題があるのかを見極めましょう。次に、それぞれの弱点に特化した対策を講じます。例えば、知識不足であれば反復学習を徹底し、読解力不足であれば文章の構造を意識した読み方や、記述問題のポイントを押さえた練習が必要です。また、過去問演習を通して出題傾向を分析し、戦略的に得点するための力を養うことも大切です。このセクションでは、具体的な対策方法を詳しくご紹介し、お子様が国語の成績を確実に伸ばせるようサポートします。
この記事でわかること
- 中学受験国語の勉強法
- 中学受験国語において求められる15のチカラと鍛え方
- 中学受験国語におけるおすすめテキスト一覧
中学受験国語で高得点を取るために必要な15のチカラ

中学受験国語で高得点を取るために必要な15のチカラまとめ
- マインドセット系グループ
- 自分で調べる力
- やりぬく力
- 継続する力
- ポジティブ思考力
- 集中力
- 知識情報系グループ
- 漢字力
- 語彙力
- 文法力
- 論理フレーズ力
- 一般常識力
- 理解思考系グループ
- 論理的思考力
- 記述力
- 論理的文章読解力
- 文学的文章読解力
- 戦略的得点力
1.自分で調べる力
わからない言葉や背景知識に直面したとき、自力で調べて理解する力は、中学受験国語において非常に重要です。 辞書や参考書を活用し、疑問を解消する習慣をつけましょう。
2.やりぬく力
目標達成に向けて、困難な状況でも諦めずに最後まで努力し続ける力です。模試の結果に一喜一憂せず、粘り強く学習に取り組む姿勢が求められます。
3.継続する力
日々の学習を習慣として定着させ、途切れることなく学び続ける力は、成績向上に不可欠です。 毎日少しずつでも国語に触れる時間を作りましょう。
4.ポジティブ思考力
中学受験は長期戦です。うまくいかない時でも前向きな気持ちを保ち、失敗から学びを得る力は、お子様の精神的な成長を促します。
5.集中力
限られた時間の中で、目の前の学習に深く没頭できる力は、効率的な学習に直結します。 短時間でも質の高い学習を意識しましょう。
6.漢字力
中学受験国語の基礎の基礎となるのが漢字です。正確な読み書きはもちろん、熟語の意味まで理解していることが高得点に繋がります。
7.語彙力
文章を正確に理解するためには、豊富な語彙力が不可欠です。 知らない言葉に出会ったら、その場で意味を調べる習慣をつけ、語彙を増やしましょう。
8.文法力
文の構造を理解し、主語や述語、修飾語などの関係性を把握する力は、論理的な文章読解の土台となります。
9.論理フレーズ力
しかし」「したがって」といった接続語や指示語など、文章の論理展開を示すフレーズを正確に読み取る力は、長文読解で威力を発揮します。
10.一般常識力
文章の背景にある社会や文化、科学などの幅広い知識は、文章内容の理解を深める助けとなります。 日頃から様々な情報に触れる機会を作りましょう。
11.論理的思考力
文章の主張や根拠、結論を正確に把握し、筋道を立てて考える力は、論説文や説明文の読解に必須です。
12.記述力
自分の考えや文章の要点を的確かつ論理的に表現する力は、記述問題で高得点を取るために最も重要なスキルの一つです。
13.論理的文章読解力
説明文や論説文といった論理的文章を、筆者の主張や論拠、構成を正確に捉えながら読み解く力は、中学受験国語の要となります。
14.文学的文章読解力
物語文や随筆文など、登場人物の心情や情景描写を読み取り、作品全体のテーマを深く理解する力は、文学的文章で高得点を取るために必要です。
15.戦略的得点力
限られた時間の中で、どの問題から解くか、どこに時間をかけるかなど、効率的に得点するための戦略を立てる力は、本番で差をつけます。
15のチカラは大きく3グループに分類できる

マインドセット系グループ=自分で調べる力・やりぬく力・継続する力・ポジティブ思考力・集中力
このグループは、お子様が学習に臨む上での心構えや姿勢、そして学習効率を高めるための土台となる力を指します。具体的には、わからないことがあった時に自ら積極的に解決策を探す「自分で調べる力」や、困難な問題に直面しても最後まで諦めずに取り組む「やりぬく力」が含まれます。また、毎日コツコツと学習を続ける「継続する力」や、失敗を恐れずに前向きに挑戦する「ポジティブ思考力」、そして限られた時間で最大限の成果を出すための「集中力」もここに分類されます。これらの力は、国語だけでなく全ての科目の学習において、お子様の成長を支える基盤となります。日々の学習の中で意識的に育んでいくことで、主体的に学ぶ姿勢を養うことができます。
知識情報系グループ=漢字力・語彙力・文法力・論理フレーズ力・一般常識力
このグループは、文章を正確に理解し、表現するために必要不可欠な基礎知識を網羅しています。具体的には、文章の土台となる「漢字力」はもちろんのこと、言葉の意味を正確に捉える「語彙力」が挙げられます。また、文の構造を理解し、正しい文章を読み書きするための「文法力」も重要です。文章の論理的なつながりを示す「論理フレーズ力」は、特に説明文や論説文を読み解く上で欠かせません。さらに、文章の背景を理解するための「一般常識力」もこのグループに含まれます。これらの知識は、一朝一夕で身につくものではなく、日々の積み重ねが重要です。地道な反復学習を通じて、これらの基礎力を着実に定着させることで、より高度な読解力や表現力の習得に繋がります。
理解思考系グループ=論理的思考力・記述力・論理的文章読解力・文学的文章読解力・戦略的得点力
このグループは、習得した知識を基盤として、文章を深く理解し、それに基づいて思考し、表現する応用力を指します。具体的には、文章の主張や根拠を明確に捉える「論理的思考力」や、自分の考えや文章の要点を的確に伝える「記述力」が含まれます。また、説明文や論説文の構成や筆者の意図を正確に読み解く「論理的文章読解力」、そして物語文や随筆文の登場人物の心情や情景を深く読み取る「文学的文章読解力」もここに分類されます。さらに、入試本番で限られた時間の中で効率的に得点するための「戦略的得点力」も、このグループの重要な要素です。これらの力は、単なる暗記では身につかず、多くの演習と試行錯誤を通じて、実践的に養っていく必要があります。
基本的には知識情報系グループを先に固め、理解思考系グループの学習に移行しよう
中学受験国語の学習を進める上で、まずは「知識情報系グループ」の基礎固めを最優先にするべきです。 漢字や語彙、文法といった基本的な知識が不足していると、いくら読解問題を解いても、文章の意味を正確に理解することが困難になるからです。例えば、漢字が読めない、言葉の意味が分からない、文の構造が把握できないといった状態では、筆者の主張や登場人物の心情を読み解くことはできません。土台がしっかりしていない建物が崩れてしまうように、基礎知識が曖昧なまま応用問題に取り組んでも、効率的な学習には繋がりません。これらの知識が定着して初めて、「理解思考系グループ」である論理的思考力や読解力、記述力といった応用的な力を効果的に伸ばすことができるようになります。焦らず、段階を踏んで学習を進めましょう。
マインドセット系グループは常に向き合ってベストを尽くすことが大切
「マインドセット系グループ」に分類される力は、他の知識や理解力とは異なり、特定の学習時期に集中して取り組めば良いというものではありません。学習期間を通じて、常に意識し、向き合い続けることが極めて重要です。 例えば、わからない問題に出くわしたときに、すぐに諦めるのではなく「自分で調べる力」を発揮する、難しい問題でも「やりぬく力」で粘り強く考える、日々の学習を「継続する力」で習慣化するなど、常にこれらの力を発揮する意識を持つことが大切です。ポジティブな気持ちで学習に取り組む「ポジティブ思考力」や、集中して学習する「集中力」も同様です。これらのマインドセットは、お子様が困難に直面した時に乗り越える原動力となり、学習効果を最大限に引き出すために不可欠な要素です。
自分で調べる力の攻略ポイント
たいていのことは自分で調べられると知ることが大事
お子様が「わからない」と感じたときに、すぐに大人に聞くのではなく、「自分自身で解決できることが多い」という意識を持たせることが非常に重要です。 この認識が、自律的な学習姿勢の第一歩となります。辞書を引いたり、参考書を読み返したりすることで、疑問が解消できるという成功体験を積ませることが大切です。最初は時間がかかっても、自分で調べたことは深く記憶に残りやすく、応用力も身につきます。保護者の方はお子様が質問してきた際に、すぐに答えを教えるのではなく、「どうしたら調べられるかな?」と問いかけたり、「一緒に調べてみようか」と促したりすることで、この力を育むサポートができるでしょう。
 塾長 神泉
塾長 神泉自分で調べる力が養われないと中学受験の勉強量は乗り越えられません。
わからないことはテキストで調べる
学習中にわからない言葉や概念に出会った場合、まずは今使っているテキストや参考書を読み返すことが、最も効率的で確実な調べ方です。 新しい情報を探しに行く前に、既に学習した範囲の中にヒントが隠されていることがよくあります。テキストには、その単元を理解するために必要な情報が体系的にまとめられており、関連する知識や具体例も近くに掲載されていることが多いです。これにより、単なる言葉の意味だけでなく、その文脈における意味や、他の知識との繋がりも同時に理解を深めることができます。テキストを最大限に活用する習慣を身につけることで、知識の定着も促進されます。
おそらくわかっていないであろうこと(もっと調べた方が良いこと)を察知できる状態を目指そう
自分で調べる力を高める最終的な目標は、「表面的な理解で終わらせず、さらに深く掘り下げるべき点」を、お子様自身が察知できるようになることです。 例えば、一つの言葉の意味を調べた後でも、「この言葉がこの文脈で使われるのはなぜだろう?」「他の使い方はあるのだろうか?」といった疑問が自然と湧いてくる状態が理想的です。これは、単に知識を増やすだけでなく、思考力を伴う学習姿勢と言えます。お子様がこのような疑問を持つようになったら、積極的に調べさせ、その探求心を尊重してあげてください。この「もっと知りたい」という知的好奇心が、学習を継続する大きな原動力となります。
まずは、一日最低10回辞書を引くところから始めよう
「自分で調べる力」を身につけるための具体的な第一歩として、お子様に一日最低10回は辞書を引く習慣をつけさせることを強くお勧めします。 最初は難しいと感じるかもしれませんが、目標回数を決めることで、無理なく習慣化を進めることができます。例えば、読書中や問題演習中に知らない言葉に出会ったら、その都度辞書を引くように促しましょう。スマートフォンやタブレットの辞書アプリも便利ですが、紙の辞書を引くことで、目的の言葉だけでなく、その前後にある言葉にも自然と目が行き、語彙力を多角的に広げる効果も期待できます。この小さな積み重ねが、やがて大きな力となります。



読解問題の文章を読めば、10個以上は確実にわからない言葉が出てくるはずです。出てこない場合は、「わからないかも」というアンテナを張ることを意識しましょう。
やりぬく力の攻略ポイント
小さな目標から始めて成功体験を積み重ねる
「やりぬく力」を養うためには、最初から高すぎる目標を設定するのではなく、達成可能な小さな目標から始めることが効果的です。 例えば、「漢字を100問完璧にする」のではなく、「今日は漢字を10問だけ解く」といった具体的な目標を設定します。そして、その小さな目標を達成できたときに、お子様を褒め、達成感を味わわせてあげてください。この成功体験の積み重ねが、お子様の自信となり、「もっとできる」という意欲を引き出します。少しずつ目標のレベルを上げていくことで、やがては大きな目標に対しても粘り強く取り組むことができる「やりぬく力」が自然と身についていくでしょう。
困難に直面したときに、なぜ始めたのかを思い出す
学習の過程で必ず訪れる困難な状況に直面したとき、お子様が「なぜ中学受験をするのか」「なぜ今、この勉強をしているのか」という最初の目的や動機を思い出すことは、やり抜くための重要な支えとなります。 たとえば、志望校への強い思いや、将来の夢、あるいは単純に「この科目を克服したい」という気持ちなど、最初に学習を始めた時の純粋な動機を改めて問いかける時間を設けてみてください。原点に立ち返ることで、一時的な挫折感から立ち直り、再び前向きな気持ちで学習に取り組むことができます。これは、お子様自身が自己の目標を再認識し、内発的なモチベーションを維持する上で非常に効果的な方法です。
完璧を目指さず、まずは「最後までやりきる」ことを意識する
「やりぬく力」を育む上で、最初から完璧な状態を目指すのではなく、「まずは最後までやりきる」という意識を持つことが非常に大切です。 特に国語の学習においては、難解な問題や長文読解に直面すると、「完璧に理解しなければ」というプレッシャーから途中で挫折してしまうことがあります。しかし、たとえ途中であやふやな部分があったとしても、まずは与えられた課題や問題を最後まで解き切ることを目標にしましょう。完璧主義は時に、行動を阻害する要因となります。最後までやり遂げることで、達成感を得られ、次に繋がる自信になります。その後で、間違えた問題や理解が不十分だった箇所を復習し、知識を深めるサイクルを繰り返すことで、着実に力がついていきます。
継続する力の攻略ポイント
習慣化するために、決まった時間に決まった行動をとる
学習を「継続する力」を身につけるには、毎日のルーティンに組み込むことが最も効果的です。 例えば、「学校から帰ったらすぐに、まずは国語の漢字練習を15分行う」「夕食後、お風呂に入る前に読解問題を1題解く」といったように、特定の時間や行動に紐づけて学習することを決めましょう。これにより、お子様は「この時間になったら国語の勉強をする」という意識が自然と芽生え、学習を始めるまでのハードルが下がります。最初のうちは保護者の方も声かけをする必要がありますが、習慣として定着すれば、お子様が自律的に学習に取り組むようになるでしょう。
完璧でなくて良いと割り切る
学習の継続において、「毎日完璧にこなさなければならない」というプレッシャーは、むしろ継続を妨げる原因になることがあります。 時に体調が優れない日や、どうしても気が乗らない日もあるでしょう。そのような時に「今日は何もできなかった」と落ち込むのではなく、「少しでも取り組めたらOK」「今日はここまでで良い」と割り切る気持ちが大切です。例えば、本来30分勉強する予定だったが10分しかできなかったとしても、全くやらないよりははるかに良いことです。完璧を目指しすぎず、柔軟な姿勢で学習に取り組むことで、心理的な負担が軽減され、結果として長く学習を継続できるようになります。
スキマ時間学習を徹底し、勉強していない状態を作らないようにする
「継続する力」を高めるには、まとまった学習時間だけでなく、日々のちょっとした「スキマ時間」を有効活用することが非常に重要です。 電車での移動中、塾の始まる前、食事の準備ができるまでの数分間など、意識すれば勉強に充てられる時間は意外とたくさんあります。このスキマ時間を漢字の復習、語彙の確認、短い文章の音読などに充てることで、「勉強していない状態」を極力減らすことができます。短時間でも集中して取り組むことで、学習のリズムが途切れず、結果として継続が容易になります。お子様と一緒に、どのようなスキマ時間があるかを見つけ、効率的な学習計画を立ててみましょう。



スキマ時間学習については「【中学受験】スキマ時間学習を制す者が受験を制す」にて詳しく解説しています。
ポジティブ思考力の攻略ポイント
中学受験の難易度はどの受験よりも難易度が高い
多くの方がイメージする以上に、中学受験の難易度は、高校受験や大学受験に退官する難易度よりも高いと言われることがあります。 特に難関校の入試問題は、小学校で習う範囲をはるかに超える深い思考力や応用力が求められ、大人でも手こずるような問題が出題されることも珍しくありません。この事実を保護者が理解しておくことは、お子様が困難に直面した際に、不必要にプレッシャーを与えず、ポジティブな言葉をかけ続ける上で非常に重要です。難しいからこそ、つまずくのは当然であると認識し、「頑張っているね」「よく考えているね」といった前向きな励ましで、お子様の挑戦を支えてあげてください。
若いうちに勉強してつまずくのは当たり前
中学受験に挑戦するお子様は、まだ心身ともに成長過程にあり、学習の途中でつまずいたり、思うように成績が伸びなかったりするのは、むしろ当たり前のことです。 まだ知識も経験も少ない中で、高度な内容に触れるわけですから、理解に時間がかかったり、間違えたりすることは自然な学習プロセスの一部と捉えるべきです。このことを保護者の方が理解し、お子様が失敗したときに責めるのではなく、「つまずきは成長の機会だよ」「次に繋がる経験だね」と励ます姿勢が、お子様のポジティブ思考力を育みます。失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えてあげましょう。
受験ができるチャンスが一個多くなったと肩の力を抜いて挑む
中学受験は、人生における数多くの選択肢の一つであり、お子様にとって「新しい学びの場に進むチャンスが一つ増えた」という前向きな捉え方をすることが大切です。 過度に結果にこだわりすぎると、お子様も保護者も精神的に疲弊してしまいます。たとえ第一志望校に合格できなかったとしても、中学受験で得た知識や経験、そして「やり抜く力」は、その後の人生において必ず大きな財産となります。中学受験を通して得られる成長そのものに価値を見出し、「受験を経験できてよかった」と思えるように、肩の力を抜いて、お子様と一緒に前向きな気持ちで取り組む姿勢が、結果として良い方向へ導くことでしょう。
集中力の攻略ポイント
短時間でも良いので、まずは取り組む時間を決める
集中力を高める第一歩として、「まずは短時間でも良いので、学習に取り組む時間を具体的に決めること」が重要です。 例えば、「15分だけ漢字練習をする」「20分だけ読解問題に取り組む」など、タイマーを使って時間を区切る方法も有効です。長時間集中し続けるのが難しいお子様でも、短い時間であれば「この時間だけは頑張ろう」と意識しやすくなります。この短い時間での集中を繰り返すことで、少しずつ集中力を維持できる時間が伸びていきます。始めは集中が途切れても、設定した時間は席を立たない、他のことをしないというルールを守ることから始めましょう。
誘惑になるもの(スマートフォンなど)を視界に入れないようにする
学習中の集中力を阻害する最大の要因の一つは、スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、お子様の興味を引く誘惑物です。 これらのアイテムが視界にあるだけで、無意識のうちに意識がそちらに向いてしまい、学習に集中できなくなります。学習を始める際には、お子様の周囲からこれらの誘惑になるものを完全に片付けることが重要です。できれば、別の部屋に置くか、保護者が預かるなどして、お子様の視界に入らないように徹底しましょう。物理的に誘惑を排除することで、お子様は目の前の学習に集中しやすくなり、効率的な学習時間を確保できるようになります。



デジタルデトックスについては、「ネットを遮断して勉強に集中」にて詳しく解説しています。
適度な休憩を取り、脳をリフレッシュさせる
集中力を長時間維持するためには、適度な休憩を挟むことが非常に重要です。 人間の脳は、長時間同じ作業を続けると疲労し、集中力が低下します。例えば、25分間の学習と5分間の休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」なども効果的です。休憩時間には、ストレッチをする、水分補給をする、少し体を動かすなど、学習とは全く異なる活動で脳をリフレッシュさせましょう。ただし、休憩中にスマートフォンやゲームに触れてしまうと、集中力が途切れてしまう可能性があるため注意が必要です。休憩の取り方を工夫することで、メリハリのある学習習慣が身につき、集中力の維持に繋がります。
漢字力の攻略ポイント
小学校指導要領範囲を網羅できる漢検5級を先回りして取得しよう
中学受験において漢字は必須の項目ですが、その対策として小学校の指導要領範囲をカバーできる漢検5級の取得を目標とすることをお勧めします。 漢検5級は小学校6年生修了程度のレベルであり、これに先回りして取り組むことで、受験で求められる漢字の基礎力を盤石にできます。漢字の学習は早期に着手するほど効果が高く、余裕を持って取り組むことで、受験直前の負担を軽減し、他の科目の学習に時間を割けるようになります。また、漢検の合格は、お子様の自信にも繋がり、学習へのモチベーションアップにも寄与するでしょう。計画的に学習を進め、早めの取得を目指しましょう。
初めて覚える段階で正しい書き順で習得する
漢字を覚える際、最初に正しい書き順で習得することは、後々の学習効率と定着率に大きく影響します。 間違った書き順で一度覚えてしまうと、後から修正するのは非常に困難であり、無駄な労力と時間を要することになります。正しい書き順は、漢字のバランスを整え、美しく書くためだけでなく、漢字の構造を理解し、効率的に覚える上でも重要です。また、入試によっては書き順も採点対象となる場合があるため、日頃から意識して正しい書き順で練習するように心がけましょう。書き順を意識した反復練習を習慣化することで、漢字の定着を促進できます。
漢字がもつ意味に注目して丸暗記を避けよう
漢字学習において、単に形をなぞって丸暗記するのではなく、漢字が持つ「意味」に注目して学習することが非常に重要です。 例えば、「聞」という漢字は「門」と「耳」から成り立っており、「門ごしに耳を傾ける」という成り立ちを知ることで、意味と形が結びつき、記憶に残りやすくなります。また、部首の意味を理解することも、漢字の意味を推測する上で役立ちます。このように意味を理解しながら漢字を覚えることで、応用力が身につき、類義語や対義語、熟語の意味も推測しやすくなります。丸暗記に頼るのではなく、漢字の成り立ちや意味に興味を持って取り組むことで、より深い理解と定着を促しましょう。
習った漢字はなるべく使って慣れよう
漢字を覚えるだけでなく、実際に文章の中で使用したり、音読したりする機会を増やすことで、知識として定着し、自然と使える漢字が増えていきます。 例えば、漢字練習帳で覚えた漢字を使って短い文を作ってみる、日々の会話の中で積極的に使ってみる、読書中に習った漢字が出てきたら意識して読み書きする、といったアウトプットの機会を設けることが大切です。また、書き順や読み方が曖昧な漢字は、何度も書いて確認し、正しい形と音を体に覚え込ませましょう。このように、インプットとアウトプットを繰り返すことで、漢字はより深く記憶に刻まれ、実践的な漢字力へと繋がります。
語彙力の攻略ポイント
語彙力と読解の精度は比例する
中学受験国語において、お子様の語彙力は文章の読解精度に直接的に比例します。 知らない言葉が多いと、文章全体の意味を正確に捉えることができず、筆者の意図や登場人物の心情を誤解してしまう可能性が高まります。たとえ文章の論理構造を理解できていても、個々の単語の意味が分からなければ、設問に対する正しい解答を導き出すことは困難です。逆に言えば、語彙力が豊富であればあるほど、文章の細部まで正確に読み解くことができ、結果として読解問題の正答率が向上します。日々の学習の中で、積極的に語彙を増やし、言葉のニュアンスまで理解するよう努めましょう。
最低2000語、理想は2800語覚えよう
中学受験国語で高得点を目指すには、最低でも2000語、できれば2800語程度の語彙を習得していることが望ましいとされています。 これは、中学受験の頻出語彙や、読解問題で問われる可能性のある一般的な語句を含んだ目標数値です。市販されている語彙集や、塾で配布されるテキストの語彙リストなどを活用し、計画的に語彙を増やしていく必要があります。ただ単語を羅列して覚えるのではなく、例文とともに意味や使い方を理解すること、そして類義語や対義語、多義語にも目を向けることで、より実践的な語彙力が身につきます。継続的な学習で、着実に語彙数を増やしていきましょう。
アウトプット学習を主軸に覚えていこう
語彙力を効率的に高めるためには、ただ単語帳を眺めるだけのインプット学習に留まらず、積極的にアウトプットを取り入れることが非常に重要です。 例えば、覚えた言葉を使って短文を作ってみる、日常会話の中で意識的に使ってみる、読書中に知らない言葉が出てきたら意味を推測しながら読み進め、後で確認するといった方法があります。また、語彙問題集を解くだけでなく、自分で覚えた言葉のリストを作成し、定期的にテストを行うのも効果的です。アウトプットを通じて、言葉を実際に「使う」ことで、その意味や用法がより深く記憶に定着し、実践的な語彙力として身についていきます。
習った語彙はどんどん使って体にしみこませる
習得した語彙を単なる知識で終わらせず、実際に「使える」力にするためには、積極的にアウトプットの機会を増やすことが不可欠です。 漢字と同じく、覚えた語彙は、音読や作文、日常会話の中で意識的に使ってみましょう。例えば、新聞記事や書籍を読んだ際に、覚えたばかりの語彙が使われている場面に遭遇したら、その文脈での使われ方をしっかり確認します。また、自分で文章を書く練習をする際にも、積極的に新しい語彙を取り入れてみてください。実際に言葉を使うことで、その意味やニュアンスがより深く体にしみこみ、自然と語彙力が向上します。お子様が抵抗なく言葉を使えるようになるまで、何度も繰り返すことが大切です。
文法力の攻略ポイント
最低限覚えるべきは「文の成分(主語・述語など)」の見分け
中学受験国語において、文法学習の第一歩として最も重要なのは、文の「主語」や「述語」、「修飾語」といった主要な成分を正確に見分けられるようになることです。 これらが理解できていれば、複雑な構造の文章でも、誰が(何が)どうしたのか、どのような状態なのかといった、文章の骨格を正確に捉えることができるようになります。特に、主語と述語の関係を正しく把握することは、文章全体の意味を理解し、ひいては記述問題で正確な解答を作成する上での土台となります。まずは、短い文から練習を始め、徐々に長い文でも文の成分を見分けられるようにトレーニングを積んでいきましょう。
助動詞と助詞もできるだけやろう
文の成分の把握に加えて、助動詞と助詞の役割を理解することも、中学受験国語の文法力向上には欠かせません。 助動詞は動詞や形容詞などに付いて、可能、受身、意志、推量など、多様な意味を付け加えます。また、助詞は名詞などについて、文の中での役割(主語、目的語など)を示したり、意味を補ったりします。これらの言葉の働きを理解することで、文章のニュアンスや筆者の意図をより正確に読み取ることができるようになります。最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返し問題を解いたり、文章の中で実際にどのように使われているかを確認したりすることで、徐々に感覚を掴むことができます。
学校によっては文法全範囲を対策する必要がある
中学受験の国語における文法の出題範囲は、学校によって大きく異なります。難関校の中には、中学校で学習するような文法事項、例えば敬語や品詞の詳しい分類、古典文法の一部まで出題する学校もあります。 そのため、志望校の過去問を分析し、どの程度の文法知識が求められているのかを正確に把握することが重要です。



仮に文法全範囲を出題されていたとしても、配点は小さいので他の学習リソースを鑑み、最低限の対策に抑えることも一案です。
時間はかかる分野だけどマスターすれば確実に国語力のそこあげになる
文法学習は、地道で時間のかかる分野に思えるかもしれません。しかし、一度基本的な文法をマスターしてしまえば、国語力全体の底上げに繋がり、読解力と記述力の両面で大きなアドバンテージとなります。 文法を理解することで、文章の構造が明確に見えるようになり、筆者の意図や論理展開を正確に把握できるようになります。また、自分で文章を書く際にも、論理的で分かりやすい文章を作成する土台となります。最初は忍耐が必要ですが、文法を味方につけることで、中学受験国語における得点力は確実に向上するでしょう。諦めずに、こつこつと取り組むことが大切です。
個別指導などを利用してピンポイントで鍛えるのもアリ
文法は、独学では理解しにくい、あるいは苦手意識を持ちやすい分野の一つです。もしお子様が文法でつまずいている、あるいは効率的に学習を進めたいと考えているのであれば、個別指導などの専門家を活用するのも有効な選択肢です。 個別指導であれば、お子様の理解度や苦手なポイントに合わせて、ピンポイントで必要な文法事項を徹底的に指導してもらえます。分からない部分をその場で質問し、疑問を解消できるため、効率的に弱点を克服できます。また、自分では気づきにくい弱点も、プロの視点から指摘してもらえるため、効果的な学習に繋がるでしょう。
論理フレーズ力の攻略ポイント
接続語を中心とした論理的文章に頻出のフレーズを集中的に覚える
「論理フレーズ力」を養う上で最も効果的なのは、「しかし」「したがって」「例えば」「つまり」といった接続語を中心に、論理的文章で頻繁に使われるキーフレーズを集中して覚えることです。 これらのフレーズは、文章の論理展開を示す標識のような役割を果たしており、筆者の主張や理由、結論、具体例などを素早く見抜く手助けとなります。それぞれのフレーズが持つ意味合いを正確に理解し、文章中でどのように機能しているかを意識しながら読解練習を重ねましょう。これにより、文章の全体構造を瞬時に把握できるようになり、読解スピードと正答率が飛躍的に向上します。
論理コアフレーズ一覧
読解コアフレーズ130個一覧
「接続語」パート
【帰結】だから 従って よって それゆえ そのため すると
【逆接】しかし だが でも ところが にもかかわらず が けれども
【並列】また そして そのうえ さらに しかも
【対比】一方 もしくは あるいは それに対して
【列挙】第一に・第二に・第三に 最初に・ついで・最後に まず・つぎに・さらに
【換言】すなわち つまり 要するに むしろ
【例示】例えば とくに とりわけ
【理由】なぜなら というのは
【転換】さて ところで では
【結論】いずれにしても やはり
「評論用語」パート
抽象⇔具体
一般⇔特殊
絶対⇔相対
本質⇔現象
理性⇔感性
客観⇔主観
本音⇔建前
概念
観念
逆説(パラドックス)
皮肉
ジレンマ
「助詞」パート
【順接】ので/から
【逆接】のに/けれど/ても
【主語・定義】は/が
【同類・並立・強調】も
【強調】こそ
【類推・限定・添加】さえ
【類推・例示】でも
【類推】すら
【限定】しか
【限度・類推】まで
【程度・限定】だけ
【例示】など
「助動詞」パート
【受身・尊敬・自発・可能】れる/られる
【使役】せる/させる
【希望】たい/たがる
【断定】だ/です
【様態・伝聞】そうだ/そうです
【推定】らしい
【意思・推量・勧誘】う/よう
【推定・たとえ・例示】ようだ(です)/みたいだ(です)/ごとし
【打消意思・打消推量】まい
【打消】ない
【過去・完了・存続・確認】た
【丁寧】ます
「呼応の副詞」パート
【疑問】なぜ~のか。/どうして~だろう。
【たとえ】まるで~ようだ。/ちょうど~ようだ。/さも~ようだ。/あたかも~ようだ。
【仮定】もし~ならば/たとえ~ても/仮に~ても/いくら~ても
【願望】ぜひ~たい。/どうか~ください。/どうぞ~ください。
【否定】決して~ない。/必ずしも~ない。/とうてい~ない。/全く~ない。/少しも~ない。
【推量】たぶん~だろう。/おそらく~だろう。/きっと~だろう。
「その他の重要表現」パート
【譲歩構文】<なるほど/たしかに/もちろん/むろん>+<しかし○○/でも○○/だが○○/であるが○○等>
【否定構文】××ではなく○○/××ではなく、むしろ○○
【二重否定=強い肯定】○○ではないということはない
【その他重要表現】
・本質的に○○/本質は○○
・○○といっても過言ではない
・一般的に
・特に
・そもそも
・このように
・昔(かつて)は~&今(現代)は~
論理コアフレーズ部分が出題者が注目する箇所なのでフレーズ暗記で正答率大幅にアップ
中学受験国語の論理的文章において、「論理コアフレーズ」と呼ばれる接続語や指示語、言い換え表現などは、出題者が最も注目する箇所であることが非常に多いです。 これらのフレーズが使われている部分には、筆者の主張や重要な情報が隠されている可能性が高いため、正確に読み取ることができれば、設問に対する正答率を大幅に向上させることができます。したがって、単にフレーズの意味を覚えるだけでなく、それが文中でどのような論理関係を示しているのかを深く理解し、マークするなどして意識的に読み解く練習を重ねましょう。これにより、効率的に重要ポイントを掴み、得点に繋げることが可能になります。
一般常識力の攻略ポイント
中学受験では公立高校入試レベルの文章が出題される
中学受験の国語、特に説明文や論説文では、小学校で習う範囲をはるかに超え、時には公立高校入試レベル、あるいはそれ以上のテーマや内容の文章が出題されることがあります。 環境問題、科学技術、社会情勢、倫理など、小学生には馴染みの薄い抽象的なテーマや専門的な内容が扱われることも珍しくありません。これは、単なる知識だけでなく、文章の背景にある社会や文化への理解、そしてそれらを論理的に捉える力を問われているためです。お子様がこれらの文章にスムーズに対応できるよう、日頃から様々な分野の知識に触れ、視野を広げる準備をしておくことが重要です。
大人にとっては当たり前の一般常識・背景知識を習得しておく必要がある
中学受験の国語で出題される文章には、大人にとっては「当たり前」と感じられるような一般的な社会の仕組みや文化、科学に関する背景知識が前提となっているケースが少なくありません。 例えば、経済の仕組み、民主主義の概念、環境問題の基本的な考え方、伝統文化の意義などです。これらの知識が不足していると、文章の内容を表面でしか捉えられず、筆者の意図や主張を深く理解することが難しくなります。日頃からニュースに関心を持ったり、社会科の知識を深めたりするだけでなく、受験対策用の一般常識問題集などを活用し、中学受験に頻出する背景知識を意図的に習得していくことが大切です。
一般常識力を鍛える参考書に書いてあることを覚えておこう
中学受験国語の「一般常識力」を効率的に高めるためには、市販されている一般常識力や背景知識を鍛えるための参考書を積極的に活用することが非常に有効です。 これらの参考書には、中学受験で頻出する社会や科学、文化、時事問題など、多岐にわたる分野の知識が分かりやすくまとめられています。単に読み込むだけでなく、重要語句や概念をノートにまとめたり、簡単な問題を解いて定着度を確認したりするなどのアウトプット学習を取り入れましょう。網羅的に知識を習得することで、未知のテーマの文章に出くわした際も、冷静に対応できる力が身につきます。
日々の文章読解をしていて登場した話で知らなかった話はノートにまとめておこう
中学受験国語の文章読解を進める中で、これまで知らなかった社会の仕組み、科学技術、歴史的背景、文化など、様々な「新たな情報」に出会うことがあります。 そのような場合、ただ読み流すのではなく、ノートにまとめておく習慣をつけましょう。例えば、「GDPとは何か」「サステナブルとはどういう意味か」「浮世絵が世界に与えた影響」といった具体的なテーマごとに、簡単な説明やキーワードを記録していきます。このノートは、お子様独自の「一般常識集」となり、繰り返し見返すことで知識が定着します。また、自分でまとめる過程で思考力が養われ、新たな知識を吸収する喜びを感じられるでしょう。
論理的思考力の攻略ポイント
言い換え・対比・因果関係をふくしま式で習得しよう
論理的思考力を養う上で、「言い換え」「対比」「因果関係」という3つの視点を意識して文章を読み解くことは非常に重要です。 これらの関係性を明確に捉えることで、筆者の主張や論理展開を正確に把握できるようになります。特に「ふくしま式」のような具体的な読解メソッドは、これらの関係性を見抜く訓練に役立ちます。例えば、言い換えは筆者の主張をより明確にするために使われ、対比は二つの事柄を比較して特徴を際立たせ、因果関係は原因と結果を明確にします。これらの関係性を意識して文章を読むことで、論理的に物事を捉える力が飛躍的に向上します。
高度な論理思考というよりも、基本的な論理思考を問われている
中学受験国語で求められる論理的思考力は、大学の哲学や専門分野で必要とされるような高度なものではなく、あくまで「基本的な論理思考」です。 具体的には、文章中の情報から、筆者の主張、その主張を支える根拠、結論、そしてそれらの間の因果関係や対立関係を正確に読み取れるかどうかが問われます。複雑なロジックを組み立てる能力よりも、提示された情報を正確に分析し、論理的な筋道を追えるかどうかが重要です。日々の学習では、この基本的な論理思考を意識して、文章の骨格を掴む練習を繰り返すことで、着実に力を伸ばすことができます。
記述力の攻略ポイント
論理的表現が含まれる短い文を書く訓練から始めよう
記述力を向上させる第一歩として、まずは論理的なつながりを持つ短い文を書く練習から始めることが重要です。 例えば、「〜なので、〜だ。」(因果関係)、「〜だが、〜である。」(対比)、「〜とは、〜のことである。」(定義・言い換え)といったシンプルな文型を用いて、自分の考えや文章の要点を表現する練習を繰り返しましょう。最初から長い文章を書くのは難しいかもしれませんが、短い文で正確かつ論理的に表現する力を身につけることが、長文記述の土台となります。日常生活の中でも、自分の意見を短く論理的に伝える練習を意識してみるのも効果的です。
対比・言い換え・因果関係が100文字以内の文章で表現できるようになればOK
中学受験国語の記述問題では、与えられたテーマや文章内容に基づき、対比、言い換え、因果関係といった論理的な関係性を、およそ100文字以内の短い文章で的確に表現する能力が求められることが多いです。 長々と書くのではなく、キーワードを盛り込みつつ、簡潔に要点をまとめる力が問われます。例えば、「Aという現象はBという原因から生じ、その結果Cという状況になった」といった因果関係を、文字数制限の中で明確に表現する練習を重ねましょう。このレベルの記述ができるようになれば、ほとんどの中学受験の記述問題に対応できる力が身についたと言えるでしょう。
論理的文章読解力の攻略ポイント
論理的関係がどの文章を読んでも抽出できるようにトレーニングしよう
論理的文章読解力を高めるためには、どのような説明文や論説文を読んでも、「これは言い換え」「これは対比」「これは原因と結果」といったように、文章中の論理的関係性を正確に抽出できるようになるまでトレーニングを積むことが重要です。 筆者の主張がどこにあり、それを支える根拠は何か、どのような具体例が挙げられているのか、という文章の骨格を掴む練習を徹底しましょう。接続語や指示語、表現の重複などに着目し、文章全体を俯瞰しながら、論理の流れを追う意識を持つことが大切です。これにより、複雑な文章も構造的に理解できるようになります。
難問奇問に目を奪われるのではなく、文章の構造理解により正答できる問題を確実に抑えよう
中学受験国語の論理的文章では、時に非常に難解な問題や、一見すると奇問に思えるような問題が出題されることがあります。しかし、そのような難問奇問にばかり目を奪われるのではなく、まずは文章の構造を正確に理解することで確実に正答できる、基本的なレベルの問題を落とさないことが得点力アップの鍵となります。 筆者の主張や根拠、結論といった文章の骨子を捉え、問いに対する直接的な答えが書かれている箇所を正確に見つける練習を重ねましょう。基本的な構造理解に基づいた問題で満点を取ることを目標にすることで、安定した得点力を築き、合格に近づくことができます。
論理的文章で登場する背景知識はどの文章にも共通するものが多いのでテーマやトピックの理解も深めよう
論理的文章、特に説明文や論説文では、環境問題、情報化社会、科学技術、文化論など、共通のテーマやトピックが繰り返し取り上げられる傾向があります。 したがって、単に文章を読み解くだけでなく、そのテーマやトピックに関する背景知識を深めておくことが、読解力向上に大きく貢献します。例えば、環境問題に関する文章をいくつか読めば、「SDGs」「カーボンニュートラル」「生物多様性」といった関連キーワードや概念が共通して登場することに気づくでしょう。こうした背景知識を事前に持っていると、初めて読む文章でも内容を素早く理解し、深い洞察を得られるようになります。関連書籍を読んだり、ニュースに関心を持ったりして、知識の幅を広げましょう。



論理的文章における頻出テーマについては「【中学受験国語】説明文&論説文が得意になる用語150語を一覧化!」にて一覧化しています。
文学的文章読解力の攻略ポイント
心情語200語を手元において(最終的には暗記して)読解に挑もう
文学的文章、特に物語文の読解において、登場人物の心情を正確に捉えることは非常に重要です。そのため、頻出する「心情語」を200語を手元に置いておき、最終的には暗記してしまうことをお勧めします。 例えば、「安堵」「畏敬」「困惑」「慨嘆」といった言葉が、どのような感情を表すのかを正確に理解していることが大切です。これらの心情語の意味やニュアンスを事前に把握しておくことで、物語の登場人物がどのような気持ちでいるのかを、より深く、そして素早く理解できるようになります。感情表現に豊かな語彙力を身につけることで、物語の読解精度は格段に向上するでしょう。



200語の心情語については、「小説・物語読解が苦手な小学生必見!覚えるべき心情語180語を一挙解説」にて詳しく解説しています。
心情を客観的に読み取れるか(もしくは表現できるか)が試されている
文学的文章の読解において、単に物語を読んで感動するだけでなく、登場人物の心情を「客観的に」読み取り、それを論理的に説明できるかが問われています。 例えば、「主人公はなぜそのような行動をとったのか」「この場面で、登場人物はどのような気持ちだったと考えられるか」といった問いに対し、本文中の根拠に基づいて具体的に記述する力が求められます。自分の主観や感想を述べるのではなく、本文の描写や言葉遣いから、登場人物の感情を分析する練習を重ねましょう。また、記述問題では、その心情を的確な言葉で表現する力も重要になります。
物語や小説においても定番の展開やテーマがあることを見抜いていこう
物語や小説には、実は「定番の展開」や「普遍的なテーマ」が存在することがよくあります。例えば、「困難に直面した主人公が成長していく過程」「異なる価値観を持つ者同士の葛藤」「自然との共生」といったテーマは、多くの作品で繰り返し描かれています。これらのパターンを事前に知っておくことで、初めて読む物語でも、ある程度の展開を予測したり、テーマを素早く見抜いたりすることが可能になります。様々な物語を読み、共通する要素を見つける練習をすることで、読解のスピードと深さを向上させることができます。物語の構造やテーマのパターンを意識しながら読解に取り組みましょう。
難問奇問に目を奪われず、基本標準レベルの難易度を安定して得点できているかを注視する
文学的文章においても、難解な語句や複雑な表現を用いた難問奇問が出題されることがあります。しかし、そのような問題にばかり時間を費やすのではなく、まずは基本的な内容理解や心情把握を問う、標準レベルの設問で安定して高得点を取れているかを注視することが重要です。 大半の合否は、これらの基本・標準レベルの問題をいかに確実に得点できるかにかかっています。本文を丁寧に読み込み、登場人物の心情変化や物語の筋道を正確に追う練習を重ねましょう。基礎を固め、標準的な問題を確実に解ける力を養うことが、結果的に難問への対応力にも繋がります。
戦略的得点力の攻略ポイントの攻略ポイント
基本標準レベルの問題をいかに時間内で得点していくかを常に考えよう
中学受験国語で合格点を取るためには、「難問を解けること」よりも、「基本から標準レベルの問題を、いかに制限時間内に正確に、そして確実に得点していくか」という戦略的な視点が非常に重要です。 多くの受験生が苦戦する難問に時間を費やすよりも、確実に得点できる問題を見極め、それをスピーディーに処理する能力が合否を分けます。日頃の演習から、一問一問にかけられる時間を意識し、時間配分を常に念頭に置きながら問題を解く練習を重ねましょう。解ける問題を確実に拾い上げることが、総合得点の安定に繋がります。
過去問分析を行い、問題の特徴から逆算して解き方を習得していこう
「戦略的得点力」を高める上で最も重要な学習は、志望校の「過去問分析」を徹底的に行うことです。 過去問を解くだけでなく、その学校がどのような文章を好み、どのような形式で、どのような力を問う問題を出しているのかを深く分析しましょう。例えば、漢字の出題傾向、記述問題の文字数制限、物語文と説明文の比率、選択肢問題の選択肢の作り方など、詳細な特徴を把握します。そこから逆算して、「このタイプの問題は、このような解き方でアプローチすれば効率的だ」という自分なりの戦略を立て、それを実際の演習で実践する練習を重ねることで、本番で最大限の力を発揮できるようになります。
テクニックにおぼれるのは本末転倒だがテクニックが使えていなければ合格も遠ざかる
中学受験国語において、「テクニック」に過度に依存するのは本末転倒ですが、適切なテクニックを習得していなければ合格が遠ざかることも事実です。 例えば、選択肢問題で正答を絞り込むための消去法、記述問題でキーワードを漏らさずに盛り込む方法、時間がないときに優先すべき問題の見極め方などは、単なる知識だけでなく、効率的に得点するためのテクニックと言えます。これらは、基礎的な読解力や思考力が身についている上で初めて有効に機能します。テクニックはあくまで道具であり、基礎力が伴ってこそその真価を発揮します。基礎とテクニックのバランスを意識しながら学習を進めましょう。
ケース別のおすすめ勉強ステップまとめ
「国語がとにかくひどい(偏差値40以下)」という場合
お子様の国語の偏差値が40以下と低迷している場合、まずは基礎中の基礎である「知識情報系グループ」の徹底的な強化から始めましょう。 漢字、語彙、基本的な文法(文の成分の把握など)の定着が最優先です。これらが不十分だと、いくら読解問題を解いても、文章の意味を正確に捉えることができません。具体的には、毎日決まった時間に漢字練習を行う、語彙集を繰り返し学習する、主語と述語を見分ける簡単なドリルに取り組むなど、非常に基礎的な内容を反復学習してください。焦らず、一歩ずつ確実に知識を積み重ねることが、成績向上の第一歩となります。この段階では、難しい長文読解問題は一旦後回しにして、基礎固めに専念することが重要です。
「文章を読めてはいるけど得点が伴わない」という場合
お子様が文章を読めている感覚はあるのに、模試や過去問で得点が伸び悩んでいる場合、読解の「精度」や「記述力」、そして「戦略的得点力」に課題がある可能性が高いです。 まず、漠然と読むのではなく、筆者の主張、根拠、結論、そして論理展開を意識しながら読む「論理的読解力」を強化しましょう。次に、読み取った内容を正確に、かつ効率的に解答用紙に表現する「記述力」の訓練が必要です。特に、制限字数内で的確にまとめる練習を重ねてください。また、時間配分や解く順番など、本番で得点を最大化するための「戦略的得点力」も意識して過去問演習に取り組み、弱点を克服していきましょう。
「論理的文章が苦手」という場合
お子様が論理的文章(説明文、論説文など)の読解に苦手意識を持っている場合、「論理的思考力」と「論理フレーズ力」、そして「一般常識力」の強化に重点を置きましょう。 まずは、文章中の接続語や指示語、言い換え表現といった「論理フレーズ」に注目し、それらが示す論理的なつながりを正確に読み取る練習を徹底してください。次に、「言い換え」「対比」「因果関係」といった論理の型を意識して文章を読む練習を重ね、筆者の主張と根拠を正確に把握する「論理的思考力」を養います。また、環境問題や社会問題など、論理的文章で頻出するテーマの「一般常識」を深めることで、内容理解が格段に進みます。
「文学的文章が苦手」という場合
お子様が文学的文章(物語文、随筆文など)の読解に苦手意識がある場合、「語彙力」、特に心情語の理解と、登場人物の「心情を客観的に読み取る力」に課題があることが多いです。 まずは、物語の登場人物が抱く様々な感情を表す「心情語」を体系的に覚え、その意味やニュアンスを正確に理解しましょう。次に、自分の感情移入だけでなく、本文中の描写(言葉遣い、行動、情景など)から、登場人物の心情を客観的に推測し、論理的に説明する練習を重ねてください。また、物語には「定番の展開」や「普遍的なテーマ」が存在することを知り、それらを見抜く練習も効果的です。読書量を増やすことも、感覚を養う上で重要になります。
「模試や過去問の得点が安定しない」という場合
模試や過去問の得点が安定しないお子様は、特定の弱点があるというよりは、「戦略的得点力」や「集中力」に課題がある可能性が高いです。 まずは、制限時間内で解ける問題とそうでない問題を見極め、得点できる問題を確実に拾い上げるための「戦略的得点力」を磨きましょう。過去問分析を通じて、学校ごとの出題傾向や時間配分のコツを掴むことも重要です。また、本番の緊張感の中でも「集中力」を維持できるように、日頃から時間を計って問題に取り組む練習を重ね、環境を整えることも大切です。さらに、弱点分野の復習を徹底し、苦手な問題でも基礎的な部分を確実に得点できるよう対策を講じましょう。
「長文読解のコツが感覚的にしかつかめていない」という場合
長文読解の「コツ」を感覚的にしか掴めていないお子様は、読解のプロセスを「論理的」に言語化し、再現可能なスキルとして身につける必要があります。 まずは、文章の「骨格」を掴む訓練を徹底しましょう。具体的には、段落ごとの要点、筆者の主張、根拠、結論、そしてそれらの論理的な繋がり(言い換え、対比、因果関係など)を明確にしながら読む練習を重ねてください。また、設問形式ごとの解答の導き出し方(選択肢問題の消去法、記述問題の要素抽出など)も、感覚ではなく、明確な手順として習得することが重要です。これにより、どのような文章や問題形式にも対応できる、盤石な読解力を築くことができるでしょう。
学年別に勉強すべきことまとめ
小学校低学年
小学校低学年のうちは、中学受験を意識した本格的な学習というよりも、国語の基礎体力と学習習慣を養うことに重点を置きましょう。 まずは、読書の習慣をつけ、様々なジャンルの本に触れることで、豊かな語彙力と文章に慣れる感覚を育みます。読み聞かせも効果的です。また、ひらがな、カタカナ、簡単な漢字の読み書きを確実に身につけさせ、語彙の基礎固めを始めましょう。漢字は、正しい書き順を意識しながら、毎日少しずつ練習することが大切です。無理なく、楽しみながら国語に親しむことで、将来の本格的な学習への土台を築きます。



小学校低学年における中学受験国語対策については「【完全版】中学受験国語〜低学年から国語を得意にする最強勉強法」にて詳しく解説しています。
小学校4年生
小学校4年生になると、中学受験を視野に入れた本格的な学習がスタートする時期です。この学年では、漢字・語彙といった「知識情報系グループ」の強化と、基本的な文章読解の習慣化が重要になります。 漢字は、小学校で習う範囲を先取りして習得し、漢字検定5級合格を目指すのも良い目標です。語彙力を高めるために、語彙集に取り組んだり、読書で知らない言葉に出会ったら辞書を引く習慣をつけたりしましょう。また、簡単な説明文や物語文を読み、主語と述語の関係を意識するなど、文の構造を意識した読解の初歩的な練習を始めると良いでしょう。
小学校5年生
小学校5年生は、中学受験の学習内容が本格化し、難易度も上がってくる時期です。この学年では、「理解思考系グループ」である論理的・文学的文章読解力の基礎を固めることが特に重要になります。 論理的文章では、筆者の主張や根拠、結論を意識して読み、対比、言い換え、因果関係といった論理的な関係性を把握する練習を重ねましょう。文学的文章では、登場人物の心情変化や情景描写に着目し、客観的に読み取る力を養います。また、記述問題対策として、短い文で論理的に表現する練習も始めましょう。これまで培った知識を土台に、より深い読解力を目指します。
小学校6年生前半
小学校6年生の前半は、入試本番を意識した実践的な学習が求められる時期です。この時期までに、「知識情報系グループ」と「理解思考系グループ」の基礎を盤石にし、苦手分野を重点的に克服していく必要があります。 過去問演習を本格的に開始し、志望校の出題傾向を分析しましょう。特に、時間配分を意識して問題を解き、どの問題にどれくらいの時間をかけるべきか、戦略を立てる練習を重ねることが重要です。記述問題は、採点基準を意識しながら、より完成度の高い解答を作成する練習に取り組みましょう。模試の成績や過去問の点数から、お子様の弱点を見つけ出し、効率的に対策を進めることが大切ですす。
小学校6年生後半
小学校6年生の後半は、いよいよ中学受験直前期に入ります。この時期は、新たな知識を詰め込むよりも、これまで学習した内容の総復習と、過去問演習を通じた実践力の向上に重点を置くべきです。 漢字や語彙など、知識系の抜けがないか最終確認を行い、確実に得点できる部分を増やしましょう。過去問は、時間を計って本番さながらに解き、間違えた問題や理解が不十分だった箇所を徹底的に復習してください。特に、志望校の過去問は複数年分繰り返し解き、出題傾向と解き方のパターンを体に染み込ませましょう。体調管理にも気を配り、万全の状態で入試本番を迎えられるよう準備を進めることが大切です。
塾の授業にはついていけていない…家庭学習だけで解決できるものなの?
塾の授業についていけていない場合の対処法まとめ
- やることではなく「やらないこと」を決める
- 基礎が固まっていない可能性が高いので基礎固めを優先する
- 原則「知識⇒論理的文章⇒文学的文章」の順で仕上げる
- 「基本的な選択肢問題」「基本的な記述問題」のみをターゲットとして難問はいったん切り捨てる
やることよりも「やらないこと」を決める方が大事
塾の授業についていけていないと感じる場合、家庭学習で全てを解決しようとすると、お子様にとって大きな負担となり、かえって学習意欲を失わせてしまう可能性があります。このような状況では、「あれもこれも」と手をつけるのではなく、「今、何を最優先でやるべきか、そして何をやらないか」を明確に決めることが非常に重要です。 全ての範囲を完璧にこなそうとせず、お子様の現状のレベルと志望校の傾向を考慮し、本当に必要な学習に絞り込みましょう。例えば、基礎ができていないのに難易度の高い問題集に手を出すのは避け、まずは基礎固めに集中するといった具体的な取捨選択が求められます。
国語は積み上げ型の科目なので、基礎がない状態で発展的な問題演習をやっても効果が薄い
国語は、漢字や語彙、文法といった基礎知識の上に読解力や記述力が積み上げられていく「積み上げ型」の科目です。したがって、もし基礎がしっかり固まっていない状態で、発展的な長文読解や記述問題の演習ばかりを行っても、学習効果は非常に薄いでしょう。 例えば、漢字が読めない、語彙の意味が分からない、文の構造が把握できないといった状態では、いくら多くの問題を解いても、文章を正確に理解することはできません。まずは、お子様の苦手な基礎分野を特定し、そこから着実に復習を重ねることが、遠回りに見えても最も効率的な成績向上の道となります。焦らず、段階を踏んだ学習計画を立てましょう。
学年や時期によって結論は変わるが、原則「知識⇒論理的文章⇒文学的文章」の順で仕上げる
家庭学習で国語の苦手を克服していく際、お子様の学年や受験までの残り時期によって学習の優先順位は変わりますが、原則としては「知識系」を固め、次に「論理的文章」、最後に「文学的文章」の順で仕上げていくのが効果的です。 知識(漢字、語彙、文法)はすべての土台となるため最優先です。次に、比較的客観的な読解が求められる論理的文章の構造理解に重点を置き、最後に心情把握などより繊細な読解力が求められる文学的文章に取り組むと、効率的に力を伸ばすことができます。もちろん、お子様の得意不得意に合わせて柔軟に調整する必要はありますが、この順序を参考に学習計画を立ててみてください。
読解では「基本的な選択肢問題」「基本的な記述問題」のみをターゲットとして難問はいったん切り捨てる
家庭学習で国語の成績を上げていく際、特に読解問題では、全ての難易度の問題に手を出すのではなく、「基本的な選択肢問題」と「基本的な記述問題」にターゲットを絞り、難問は一旦切り捨てる勇気が必要です。 全てを網羅しようとすると時間が足りなくなり、結果として中途半端な学習に終わってしまう可能性が高まります。まずは、確実に得点できる基本レベルの問題を完璧にすることを目指しましょう。これにより、着実に得点力を上げることができ、お子様の自信にも繋がります。基本問題で安定して得点できるようになってから、余裕があれば少しずつ難易度の高い問題に挑戦していくのが賢明な戦略です。
【中学受験国語】分野別おすすめ問題集まとめ
漢字
サピックス漢字の要ステップ1
- 「頻出の書き読み」「同音異義/同訓異字」「四字熟語/三字熟語」「類義語/対義語」「筆順/画数」「部首」「送り仮名」「かなづかい」「音読み/訓読み」「熟語の構成」等、中学受験国語で出題される重要論点が網羅されている
- ”入試で気をつけるべきポイント”という観点で情報が整理されている
- パート1のみで中堅校から難関校まで対応できる
語彙
中学入試 語彙力トレーニング 1400 基礎&発展編
- A・B・Cランクで語彙がレベル分けされており、志望校別に覚える量を調整できる
- 五十音順に並べられており辞書としても機能する
- 2800語と網羅性が高いので、一冊で勉強を完結できるので機能性が高い
- 演習用テキストが併売されており、アウトプット学習も可能
語彙のおすすめテキストに関しては、「【完全版】中学受験国語 語彙おすすめ本まとめ記憶法も完全解説」でより詳しく解説しています。
文法
- サイパーシリーズで重要論点をアウトプットするだけでOK
- 国語が苦手ならば「主語述語の識別」「指示語」をまずクリアしていく
文の組み立て特訓
指示語の特訓
文法学習の全体戦略については、「【中学受験国語】文法学習法徹底解説~ケース別参考書ルートも紹介~」にて紹介しています。
論理フレーズ
【中学受験国語】読解コアフレーズ暗記&線引き方法解説講座
こちらから受講可能
一般常識
「小学生の必須常識」が身につく問題集
- 論説&小説の頻出テーマを教養として身につけることができる
- 単なる暗記ではなくテーマ理解なので、再現性の高い読解力を身につけることができる
- 中学受験に最適化されているので、難しい話題もわかりやすく書かれている
- 実際の入試出題文が掲載されているので、納得感をもって学習できる
合格する国語の授業 説明文・論説文 得点アップよく出るテーマ編
合格する国語の授業 物語文 得点アップよく出る感情語&パターン編
論理的思考力
ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集〔小学生版〕
- 「言い換え」「対比」「因果関係」について簡単な題材でトレーニングできる
- アウトプット演習が中心なので論理思考を実践的に習得できる
- レベル分けされているのでどの学年/習熟度でも取り組むことができる
記述力
ふくしま式国語問題集 一文力編
論理的文章読解力
合格する国語の授業 説明文・論説文入門編
文学的文章読解力
合格する国語の授業 物語文入門編
戦略的得点力
中学入試 国語 塾技100
- 100個のトピックに分け、テクニックと演習がセットで学べる
- 論説/小説以外にも詩・短歌・俳句・図表の問題等も幅広く網羅されている
- 中学受験に最適化されているので、学習効率が高い
- 実際の入試出題文が掲載されているので、納得感をもって学習できる
まとめ
中学受験の国語は、単に文章を読むだけでなく、多岐にわたる力が総合的に求められる科目です。本記事では、国語の学習に必要な15のチカラを「マインドセット系」「知識情報系」「理解思考系」の3つのグループに分類し、それぞれの攻略ポイントを詳しく解説しました。まずは漢字や語彙、文法といった「知識情報系グループ」の基礎固めを徹底し、その上で「理解思考系グループ」である読解力や記述力を養っていくことが、成績アップへの近道となります。 また、日々の学習においては、「自分で調べる力」や「やりぬく力」といった「マインドセット系グループ」の力を常に意識し、ポジティブな姿勢で継続的に取り組むことが重要です。お子様の学年や現在の状況に合わせて、最適な学習計画を立て、着実に目標達成に向けて進んでいきましょう。
当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。
中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ
- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾
- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~
- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ
- 【完全版】勉強法紹介
- 【息抜き】コンテンツ
中学受験国語に関する記事一覧
有名中学校国語過去問に関する記事一覧
公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧
中高一貫校のデータに関する記事一覧
中学受験国語で成績を伸ばすために、まず何から始めるべきでしょうか?
中学受験国語の成績を伸ばすためには、まずお子様の得意・苦手分野を正確に把握することが重要です。特に、漢字や語彙などの知識系が弱いのか、長文読解に課題があるのかを見極め、それぞれの弱点に特化した対策を講じることが効果的です。
中学受験国語で高得点を取るために必要な15の力は、どのように分類されていますか?
中学受験国語で高得点を取るために必要な15の力は、「マインドセット系グループ(学習への心構え)」、「知識情報系グループ(基礎知識)」、「理解思考系グループ(応用力)」の大きく3つに分類されています。
国語の学習において、「知識情報系グループ」を先に固めるべきなのはなぜですか?
漢字、語彙、文法といった知識情報系の基礎が不足していると、文章の意味を正確に理解することが困難になるためです。土台となる知識が定着して初めて、論理的思考力や読解力といった応用的な力を効果的に伸ばせるようになります。
中学受験国語の「一般常識力」を効率的に高める方法はありますか?
一般常識力は、市販の参考書を活用して中学受験で頻出する社会や科学、文化などの知識を習得することが有効です。また、日々の文章読解で知らなかった内容はノートにまとめ、知識の幅を広げていくことも大切です。
塾の授業についていけていない場合、家庭学習では何を意識すべきですか?
塾の授業についていけていない場合は、全てを解決しようとせず、「今、何を最優先でやるべきか、そして何をやらないか」を明確に決めることが重要です。基礎固めに集中するなど、優先順位をつけて学習負担を軽減しましょう。